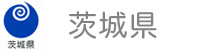2026年01月19日14:57 公表
グループホーム 花束取手
空き人数
-
空き数/定員
0/18人 -
定員18人中、現在の空き数0人です。
(2025年10月21日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当グループホームでは、「その人らしく、安心して暮らせる生活」を目指し、認知症のある高齢者の方々に対して、家庭的な環境の中での共同生活を支援しています。入居定員は18名(1ユニット9名×2)で、少人数制ならではの個別的で温かいケアを提供しています。
施設の基本理念は、「尊厳を大切にした寄り添いのケア」です。認知症の方々が感じる不安や混乱を少しでも和らげられるよう、職員は日々の関わりを通じて信頼関係を築き、入居者一人ひとりに合わせた生活支援を行っています。
当施設では、以下のような特徴的なサービスを提供しています。
【1. 生活に密着した個別ケア】
入浴、排泄、食事、整容といった日常生活動作(ADL)に対し、入居者の状態や意向に応じた介助を提供しています。特に、できることはできる限りご本人に行っていただき、自立支援の視点を大切にしています。一人ひとりの「これまでの暮らし方」を尊重しながら、その人らしい生活が継続できるよう支援します。
【2. 認知症に配慮した環境と対応】
施設内は落ち着いた色合いとわかりやすい動線を意識した設計となっており、認知症の方でも安心して移動できる環境です。また、同じ職員が継続して関わる「顔なじみの関係」を大切にし、見慣れた職員・見慣れた環境の中で安心感を持って過ごしていただけるよう配慮しています。
【3. 家庭的な食事と日常】
食事は、栄養バランスはもちろん、味や季節感、そして「食べる楽しみ」を大切にしています。施設内のキッチンで職員が調理を行い、できたての温かい食事を提供しています。調理の音や香りがリビングに自然と広がることで、家庭的な雰囲気の中で食事を楽しんでいただける環境を整えています。
以前は、入居者の方々にも野菜の皮むきや盛り付けなどの簡単な作業を通して、調理に関わっていただく機会がありましたが、近年は介護度の高い方が増え、ADLの低下が進んでいるため、こうした関わりが難しくなってきています。そのような中でも、食事の時間を楽しみにしていただけるよう、好みや嚥下機能に配慮した個別対応や、行事食・手作りおやつの提供など、日々の食に工夫を凝らしています。
また、食事の場面では、職員が一人ひとりのペースに合わせて声かけや見守り・介助を行い、安心して食事ができるよう配慮しています。栄養だけでなく、食べることを通じた「心の満足」も大切にしたサービス提供を心がけています。
【4. 季節感を大切にした行事・レクリエーション】
四季折々の行事(節分・ひな祭り・花見・夏祭り・敬老会・クリスマス会など)を大切にしており、地域の季節感を感じながら生活できるよう工夫しています。また、日々のレクリエーション活動や体操、手芸、園芸なども実施しており、認知機能や身体機能の維持・向上にもつなげています。
【5. 医療・看取りへの連携】
当施設では、地域の医療機関と連携し、健康管理や必要な医療的対応を行っています。定期的な訪問診療や往診が可能な体制を整え、急変時には迅速に医療機関と連絡を取り合う体制を確保しています。また、看取り期に入った入居者に対しては、ご本人・ご家族の意思を尊重し、穏やかで dignified(尊厳ある)な最期を迎えられるよう支援しています。
【6. 職員の安定と温かいケア】
当施設の職員は50代・60代のベテランが中心で、経験と落ち着きのある対応が可能です。認知症介護に関する知識や技術を有する職員が多く、日々の声かけや対応にも一貫性があり、入居者の不安を和らげることにつながっています。また、新人職員の育成にも力を入れており、職員間のチームワークを重視した環境で、安定したケアを提供しています。
【7. ご家族との協力】
入居者の生活を支えるうえで、ご家族との連携は欠かせません。当施設では、日々の生活の様子を定期的にご家族へ報告し、必要に応じて面談を行うことで、信頼関係を築いています。ご家族の思いやご意見を伺いながら、入居者にとって最善の支援が行えるよう心がけています。
以上のように、当グループホームでは、認知症の方が地域の一員として、家庭的な雰囲気の中で自分らしく生活できるよう、心を込めた介護サービスを提供しています。今後も、地域に根差した福祉の一拠点として、入居者とご家族の安心を支える施設運営に努めてまいります。
サービスの質の向上に向けた取組
当グループホームでは、認知症のある高齢者が安心してその人らしく暮らしていけるよう、日々のケアの質を高める取り組みを継続的に行っています。入居者の尊厳を守り、心身の状態に応じた適切な支援を提供するため、以下のような多角的な取り組みを実施しています。
【1. 職員研修の充実と継続】
サービスの質を支えるのは、現場の職員一人ひとりの知識と技術、そして入居者に寄り添う姿勢です。当施設では、介護技術や認知症ケア、感染症対策、虐待防止などをテーマに、年間計画に基づいた職員研修を定期的に実施しています。
また、ベテラン職員による実地指導や、新人職員向けのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)体制も整えており、職員が経験年数に応じて成長できる環境を構築しています。
【2. ケアの標準化と記録の見直し】
介護の質を均一かつ安定して提供するために、ケア内容の標準化に取り組んでいます。各入居者に対して個別の介護計画を作成し、定期的なカンファレンスや職員会議で見直しを行っています。また、介護記録の記入方法も見直しを行い、「気づき」や「変化」に基づいた観察記録ができるよう、職員全体で記録の質の向上に努めています。
こうした情報共有を徹底することで、入居者の状態変化を見逃さず、タイムリーな対応が可能となり、事故防止や状態悪化の予防にもつながっています。
【3. 多職種との連携強化】
地域の医療機関や訪問看護、薬局、ケアマネジャーとの連携を強化し、入居者の健康管理や医療的ニーズへの対応体制を整えています。定期的な訪問診療や服薬管理、緊急時の連絡体制など、医療とのつながりを意識した運営を行うことで、安心して生活を継続できる環境づくりに取り組んでいます。
また、看取りケアにおいては、ご家族・医師・訪問看護師・職員が協力し合い、最期まで穏やかに過ごしていただけるよう、ケアの質と連携体制の強化を図っています。
【4. 入居者満足と自己決定の尊重】
サービスの質を高めるためには、入居者本人の満足や意向の尊重が不可欠です。当施設では、日々の生活の中で「何を望んでいるか」「どう過ごしたいか」を丁寧に聴き取り、その声をケアに反映しています。たとえば、起床・就寝の時間、食事内容の好み、日中の過ごし方など、可能な限り個別の希望に添った支援を行うことで、「その人らしい暮らし」を実現できるよう努めています。
【5. 家族や地域との連携】
ご家族との連携も、サービスの質を高める大切な要素と考えています。定期的な面談や電話連絡、生活の様子を伝える写真の共有などを通じて、ご家族と信頼関係を築いています。また、介護方針や看取りケアに関する同意・説明の場を丁寧に設けることで、ご家族が安心して任せられる施設であることを目指しています。
地域とのつながりについても、防災訓練や交流会、ボランティア受け入れなどを通じて、地域福祉の一端を担う施設として積極的に取り組んでいます。
【6. ヒヤリ・ハットの共有と事故防止対策】
サービスの安全性も質の一部と捉え、ヒヤリ・ハット事例の共有を職員間で徹底しています。定期的なリスクマネジメント会議を開催し、転倒や誤薬、誤嚥などのリスクに対する予防策を検討・実行しています。また、事故が発生した場合も、その原因分析と再発防止策の検討を迅速に行い、チーム全体での学びに活かしています。
このように当施設では、介護サービスの質の向上に向けて、職員の育成、情報共有、連携体制の強化、入居者視点の尊重、安全管理など、多方面からの取り組みを継続的に実施しています。今後も、小規模施設ならではのきめ細やかなケアを強みに、入居者一人ひとりにとって安心と満足を感じられる環境づくりを目指してまいります。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
-
-
-
-
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
-
-
-
-
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
-
-
-
-
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
-
-
-
-
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
-
-
-
-
-
-
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
-
-
-
-
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当グループホームでは、入居者さまが安心して穏やかに生活できるよう、職員一同、思いやりの心を大切にしながら日々のケアに取り組んでいます。職員の年齢層は50代・60代が中心で、人生経験が豊富で落ち着いた対応ができるスタッフが多数在籍しています。長年の介護経験を活かし、入居者さまの小さな変化にも気づく観察力と、柔軟な対応力を持ち合わせていることが当施設の大きな強みです。
当施設は定員18名の家庭的なグループホームであり、職員と入居者さまとの距離が近く、日常的な会話やふれあいを大切にしています。少人数だからこそ可能な、きめ細やかな個別ケアを実現しています。職員は単なる介護業務だけでなく、入居者さまの生活の質を高めるための関わりを大切にし、「その人らしさ」を尊重した支援に努めています。
また、介護福祉士や認知症ケアに関する資格を有する職員も在籍しており、専門的な知識と技術に基づいた対応が可能です。日々の業務の中で、職員同士が積極的に情報共有や意見交換を行い、チームとしての一体感を持ってケアにあたっています。
さらに、職員全員が感染症対策や虐待防止、認知症ケアなどに関する研修を定期的に受講しており、継続的な学びとスキルアップにも力を入れています。ベテラン職員が中心ではありますが、新人や異業種から転職してきた職員の受け入れ・育成にも取り組んでおり、職員間で助け合いながら働ける職場環境づくりを進めています。
入居者さまやご家族との信頼関係を大切にし、地域とのつながりも意識しながら、これからも「この施設で暮らせてよかった」と感じていただけるようなケアを目指してまいります。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
当グループホームの入居者は、主に認知症の診断を受けた高齢者の方々で構成されており、介護度は要介護1~5まで幅広く、要介護4・5の方も複数名入居されています。年齢層は70代から90代が中心で、身体的・認知的な支援が必要な方が多く、医療的ケアは必要最小限にとどまる範囲の中で、日常生活全般にわたるサポートを行っています。
要介護度の高い入居者に対しては、職員が日常的な見守りと介助を丁寧に行い、安心・安全に暮らしていただける環境を整えています。具体的には、移動や移乗、食事、排泄、入浴などの基本的な生活動作において、個別の身体状況に応じた介助を実施しており、自立支援の考えを基にしながらも、無理のない範囲で生活機能の維持を目指しています。
また、認知症の進行により意思の表出が難しい方や、夜間の不安・混乱が見られる方に対しても、職員が一人ひとりの生活歴や性格、これまでの習慣を理解したうえで、落ち着いて過ごしていただけるよう、接し方や声かけに工夫を凝らしています。身体的な介護だけでなく、精神的な安定や安心感を得られるようなケアを心がけています。
一方で、介護度が比較的軽度な方も在籍しており、施設内での調理補助や洗濯物たたみ、花の水やりなど、役割を持って生活することができています。少人数のグループホームという特性を活かし、それぞれの方の能力を活かせる場面を大切にしながら、可能な限り「その人らしい暮らし」が続けられるよう支援しています。
当施設では、入居者同士の関係も穏やかで、職員との距離も近く、日々の会話や季節行事、レクリエーション活動を通じて、温かい人間関係が築かれています。認知症の症状によりコミュニケーションに制限がある方でも、表情やしぐさを通して思いを感じ取り、職員が丁寧に対応しています。
また、看取り期に入った方に対しても、医療機関やご家族と連携を取りながら、できる限り苦痛のない、穏やかな時間が過ごせるよう寄り添ったケアを行っています。ご家族とのつながりを大切にしながら、最期までその方の尊厳を守る支援に取り組んでいます。
今後も、入居者一人ひとりの状態に応じた個別ケアの充実を図り、「ここで暮らしてよかった」と思っていただけるような安心できる生活環境を提供してまいります。
ケアの詳細(具体的な接し方等)
入浴形態(一般浴、機械浴)
一般浴(個浴)