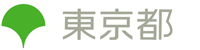2025年12月26日14:26 公表
オハナohanaリハビリデイサービス

| 介護サービスの種類 |
地域密着型通所介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-6-9 DeLCCS南長崎1号室
|
| 連絡先 |
Tel:03-3565-1087/Fax:03-3565-1087
|
サービスの内容に関する写真
-

機能訓練指導員によるマンツーマン指導
アセスメント結果から個別訓練内容を提案!
複数の機能訓練指導員が異なる視点から、意見交換し、より充実した訓練内容となるように努めております。 -

「外歩き」訓練
当事業所の特徴のひとつです。
より日常生活に近い訓練を実施します! -

全員でおこなう体操訓練
楽しみながら体を動かします!
無理のない範囲で行います。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
15/20人 -
最大受け入れ人数20人中、現在の受け入れ可能人数15人です。
(2025年10月20日時点)
サービスの内容に関する自由記述
CGTトレーニングについて:①高齢者の身体機能の向上を目指す…通常行われている維持目的のトレーニングでは、虚弱高齢者の改善は見込まれません。適切な負荷をかけた運動トレーニングにより身体機能の向上を目指します。②筋力、持久力、柔軟性、バランス能力を包括的にトレーニング…年齢と共に運動機能は低下しますが、体力の要素のみ低下することはごくまれと言われており、諸要素の包括的トレーニングが全体的な体力の向上をもたらします。③国家資格者である介護福祉士と柔道整復師がトレーニングをバックアップ…利用者が安心してトレーニングでき、かつ、運動プログラムの実施効率を上げるために、各専門分野のスタッフが協同してバックアップします。④トレーニング期間を限定し、個々の目標を設定…1回90分程度を目安とし、運動トレーニングを週1~3回、3か月のサイクルで実施。3か月間の「コンディショニング期」「筋力増強期」「機能的トレーニング期」に分割。各期の目標を個別に設定し、利用者の意欲を持続させる。
サービスの質の向上に向けた取組
従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を強化する。①採用時研修:採用後2か月以内 ②継続研修:年2回以上
研修内容は以下の通り。認知症及び認知症ケア、身体拘束等の排除、排せつ介助、健康管理方法、利用者の状況に応じた送迎方法、相談・苦情・事故対応、事故発生予防、非常災害時の対応、感染症及び食中毒の発生予防、AEDの使い方、個別機能訓練について、悪天候時の訓練参加について、熱中症予防対策、めまい・意識混濁について、動悸・呼吸困難・息切れ、高齢者骨折の特徴について等。また、利用者のプライバシー保護に取組み、倫理及び法令順守、介護サービスに関する研修等を実施し、職員の資質向上に努める。会議、研修、勉強会は全員参加を前提とし、欠席者には関連する資料を回覧するなど情報共有に努める。毎日の終礼や申し送りノートを活用し、介護サービスの提供に関する情報の共有を図っている。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
-
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
-
-
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
-
-
-
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
-
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
-
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
-
-
併設されているサービス
-
サービスの内容に関する動画へのリンク
- あとだしジャンケンゲーム
- 頭を活性化するには頭と同時に指先の活用が効果的といわれています。じゃんけんは頭と指を同時に動かせる画期的なゲームです。「あとだしジャンケンゲーム」→普通のジャンケンですとあまり頭を使いません。あとだしジャンケンにして「勝ってください」「負けてください」という条件を提示して、じゃんけんをいたします。脳の活性につながります!
- グーパーゲーム
- 両手を握ったり開いたりすることで脳を刺激します。通常の進め方は、グーパーと言いながら手を開いたり握ったりします。当事業所では応用編を行っております。右手をグーで前に、左手をパーで胸に当てて構えます。「いち、に」の掛け声で、右手、左手を変えて、腕の曲げ伸ばしをします。参加者全員で元気に声を出しながら行います。みなさんが楽しく、ストレスなく取り組めるような脳トレを行っております!!
- 個別機能訓練
-
ご利用者様の苦痛、不自由、障害をもたらしている原因を把握するために、現在のご様子を伺い、体力測定結果などを分析して評価していきます。これらを正確に行うことなく訓練内容を決めることはできません。当事業所では『SOAP(ソープ)システム』に従って評価・プログラム作成・訓練実施を進めていきます。
S:Subjective/主観的情報の収集…ご利用者様の自覚症状や現在までの経過などを詳しくお聞きします。
O:Objective/客観的情報の収集…ご利用者様との面談から、障害の原因と考えられる部分を絞り込み、外見上の変化を観察し、必要に応じて体を動かして様子を確認します。医療機関での各種検査(X線、CT、MRI等から内科的検査も含めて)も問題の解決や機能訓練上の参考になるため、併せて確認し検討していきます。
A:Assessment/評価・分析…得られた情報を分析・評価し、「障害の原因は何か?」「障害を改善するための方法」など、体の現状や課題についてわかりやすく説明いたします。
P:Plan/個別機能訓練プログラムの提示…科学的な根拠に基づき、機能訓練士(柔道整復師)が問題解決のための計画を立てます。ご利用者様個々の体の特性に合わせることはもちろん、生活スタイルなども考慮した上で、ご希望などを確認しながら、機能訓練方針を決定します。
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
20代~30代の若いスタッフがメインで活躍しております。いつも明るく前向きな気持ちにさせてくれる元気なスタッフから、落ち着いた雰囲気で安心感を与えてくれるスタッフまで様々です。明るく、アットホームな雰囲気の中でリハビリテーションに取り組んでいただけるはずです。また、管理者を始め所属するスタッフ全員が国家資格者であり、機能訓練プログラムを実践するスタッフは全員柔道整復師の資格を有しております。介護支援専門員とのWライセンスを所持しているスタッフもおり、ご利用者様のお身体の悩みや日々の体調の変化はもちろん、他のケアサービスや居宅介護のアドバイス等、多様なニーズに対応できることが当事業所の強みです。また、ご利用者様個々に適切なケアサービスを提供するため、スタッフ間の綿密なコミュニケーションによる正確な情報共有と抜群のチームワークによるリハビリアプローチが当事業者最大の自慢です。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
脳血管障害の後遺症をお持ちの方、骨折の手術後の方、お一人暮らしで外出機会が減ってしまっている方、ご夫婦で仲良く通所されている方など、ご利用者様の心身の状態は様々ですが、皆様積極的にリハビリプログラムに参加されております。入院加療を経て、在宅に戻られた後、働きかけが減少することで身体機能が低下してしまう方が多くいらっしゃる中、当事業所に通所されているご利用者様は、日常生活動作レベル向上や生活の質の向上を目的として、他のご利用者様とも関りを持ちながら、リハビリプログラムを継続されております。屋内での歩行訓練を実施した後、「外歩き」訓練に移行し、一人で外出する自信を取り戻され、行動範囲が広がったり、外出機会が増えたり、お仕事に復帰された方などもいらっしゃいます。ほとんどのご利用者様が、入浴施設や食事の提供がない分、身体機能の向上、能力低下の予防・向上を目的に通所されております。