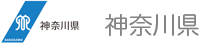2025年10月21日09:43 公表
訪問看護ステーション芍薬

サービスの内容に関する写真
-

多職種で在宅ホスピス緩和ケアを提供しています。 -

看護スタッフです。 -

看護管理者と主任です。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
30/100人 -
最大受け入れ人数100人中、現在の受け入れ可能人数30人です。
(2025年09月02日時点)
サービスの内容に関する自由記述
在宅療養が難しいとされるがん末期のご利用者様だけではなく、すべての疾患と対象者(高齢者だけではなく小児も対象とする)に対するホスピス・緩和ケアを専門性の柱とした訪問看護を行っています。例えば、アルツハイマー病等の現在の医療技術では完治することが不可能な認知症に対しては緩和ケアのアプローチでしか対処する方法がない、と言われています。そこで訪問看護ステーション芍薬では、このようなタイプの認知症に対しては緩和ケアを適用することでご利用者・ご家族の心の安寧を図っています。
その緩和ケアの定義(WHO~世界保健機構~が2002年に公表したもの)は以下の通りです。
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なあせすめんとと対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。
上記の定義のポイントは、①生命を脅かす疾患に罹患しているご利用者様を対象としたものであり、必ずしも末期に限ったものではないが、いずれの場合も死に直面されている方(完治不可能であり長期の療養期間を経ていずれ亡くなる疾患であることが医学的にも対象にしたものであること②ご利用者だけではなく、ご家族をも対象にしたものであること、そして、③身体的苦痛だけではなく、人間の心理的側面やスピリチュアルな側面(生きる意味の追求など)を対象にした、全人的なケアであるということです。人間の最大の危機であると言われる死。人間は、人生の中で数えきれない程の危機的状況に直面し苦悩しますが、死は人間にとってそれまでの危機とは比較しようもない程の、途方もない大きさで迫り来る、人生最大の危機です。ここに直面されているご利用者様、そして、大切な方を亡くすかもしれないという耐えられない程の苦悩の渦中にあるご家族様を、緩和ケアに思いを傾け、長年に渡ってこのケアに従事し、ここに精通している看護師がしっかりとサポートしていきます。
これらの専門性を発揮する基礎として、ご利用者様は24時間365日、常に私達のサービスのご利用が可能です。営業時間は月曜日から土曜日までの朝8時半から夕方5時半までですが、この営業時間外であっても、看護師が必要と判断した場合には、常に緊急対応を致します。夜中の緊急訪問での出動は、私達の訪問看護ステーションでは日常茶飯事です。ご心配なことがありましたら、決して朝で待つことなく、すぐにお電話下さい。お電話での相談だけで、安心してお休みになれる場合も多々ありますが、お電話でのご様子から、緊急訪問が必要と看護師が判断した場合には、御自宅まで看護師がかけつけます。療養されているそのご自宅が病棟だと思って、ナースコールを鳴らすように、どうぞ私達に気がねなくお電話下さい。ご利用者様・ご家族様が常に安心していられる状態・・・これこそが私達が目指すものなのですから。
ホームページでも私達のことが詳しく紹介されていますので、そちらも是非ご覧ください。
http://gci-zaitaku.co.jp/
サービスの質の向上に向けた取組
サービスの質の向上は、組織理念から始まり、人員採用と教育、組織構造や業務プロセス整備など組織開発と一体となって初めて実現可能となります。訪問看護ステーション芍薬では、下記のような包括的組織開発施策でサービスの質向上に取り組んでいます。
(1)組織理念:世界最高水準の在宅ホスピス緩和ケアを目指す組織目標
(2)経営戦略:狭い領域への集中、専門家としての誇りの醸成、多職種協働、長期的人材育成による真の信頼関係の育成
(3)求めるスキル/能力:臨床スキルとマネジメントスキルの双方(リーダーシップ能力とチームワーク能力を含む)
(4)経営スタイル/社風:権限委譲とチームワーク重視、自主性と提案、自由裁量性、全スタッフの公平性を尊重、公正性と社会的責任の心
(5)人員:ホスピス緩和ケアに対する思い(緩和ケア病棟での勤務経験者も多い)、専門性(専門看護師や認定看護師、その他のホスピス緩和ケア系の専門的研修修了)、リーダーシップ/チームワーク
(6)システム/制度:リーダーシップ能力評価、パフォーマンスボーナス制度、多様な研修制度、キャリア形成支援制度、評価面接、全拠点を通じた業務の標準化
(7)組織構造:マトリックス組織:事務、看護師教育、ボランティア、ソーシャルワークは本部に所属
上記の組織全体の施策策定と導入にあたって日本看護協会の「看護職の生涯学習ガイドライン」(2023年6月)の次の考え方を盛り込んでいます。
(1)生涯学習は看護師職個人が主体となって生涯にわたり行う
(2)生涯学習は学んだことを実践に活かし実践から学ぶという循環によって行う
(3)生涯学習は看護職個人の責務として、個人の主体性を尊重して行う
(4)生涯学習は看護職を雇用している組織等の責務として行う。
- 取組に関係するホームページURL
-
-
組織理念:リーダーシップ、チームワーク、世界最高水準の質
https://www.gci-zaitaku.co.jp/category-40/about-gci-mission-vision-values-leadership/ -
看護管理者の専門性:世界最高水準の質の実現の為にリーダーシップを発揮する
https://www.gci-zaitaku.co.jp/nurse-specialty/expertise-of-nursing-management/ -
2025年度芍薬会:リーダーシップ、チームワーク、世界最高水準の質を育む
https://www.gci-zaitaku.co.jp/category-40/2025syakuyakukai/
-
組織理念:リーダーシップ、チームワーク、世界最高水準の質
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
「サービスの内容に関する自由記述」と「サービスの質の向上に向けた取組」をご参照下さい。
採用は本部が窓口となり、各事業所の管理者・主任が最終意思決定権者となっています。傘下の別ステーション間での人事ローテーションや共同研修を行っています。
新卒時は一般の事業会社に就職し、その後看護学校やリハビリの専門学校に入学し資格取得した職員が複数在籍しています。50歳代以降の新入職者も受けれいています。
ご見学は随時お受けしています。同行訪問や看護職スタッフや看護管理者との気軽な面談も可能です。
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
ELNEC-J研修は全額組織からの負担で受講して頂けます。認定看護師資格取得費用の半額(約50万円)を補助しています。今後は特定行為研修にも支援の幅を広げていきます。
日本看護協会が開発したクリニカルラダーで各看護職員の段位を確認し、また、個人のキャリアプランを評価面接でお伺いし、受講する研修内容を決定したり、キャリアプラン通りのキャリア形成や資格取得ができたか否かを評価軸のひとつとしています。
新入職者には、その方のキャリアレベルに応じた教育担当が選任されます。現任者には基本的に主任か管理者がエルダー・メンターとしてサポートします。
年に数回(各職員の課題に応じて回数や内容を決定)キャリア面談を行います。
ご家庭の事情の変化があった場合など、ご本人のご希望に応じた働き方の変更についての相談は随時受けつけています。
年に最低一度8月から10月にかけて、本部幹部職員も同席したキャリア面談を行い、過去1年間の振り返りと自己評価、次の1年間のキャリア形成プランについて相談しながら合意形成します。 - 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
制度上の休業制度(育児休業、介護休業)に加え、無休ではありますが、1カ月以上の長期休暇を認めた実績がこれまで2ケースあります。休暇後復帰すれば勤続として扱われる為、ご本人の社会的信用や支給される給与面で長期的に有利になります。ご家庭のご事情やキャリア形成を目的とした看護職員の希望に沿った制度です。
(1)勤務シフト:毎月休み希望に沿ったシフトとなっています
(2)短時間勤務制度:週32時間以上の勤務であれば契約社員として常勤職員に準じた労働条件が適用されます
(3)正規職員への転換制度:看護職で希望した方は全員正規職員に転換しています。これまで5ケース以上の実績があります。有給休暇の取得希望があれば、全て希望通りに対応しています。
(1)チーム看護制の導入:ひとりの看護師のみしか訪問できないケースにならないよう、通常時から複数訪問看護師がチームとなって訪問している
(2)電子カルテ+ICTツールによる情報共有:訪問する看護師が異なっても同じ内容の看護が提供できる
(3)看護管理によるフォロー:有給休暇取得期間中に訪問の穴が空いたりトラブルが起こらないよう、看護管理は普段は担当ケースを多く設定せず、有給休暇取得期間中のフォローに入れる体制 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
各種ハラスメントについては本部に直接相談できる体制となっている
労働安全衛生法で定められた、事業者が従業員に実施することが義務づけられている健康診断の対象者には毎年最低1回の健康診断を受けて頂いています。当該法定検診の対象外である短時間勤務労働者にも、簡易的なストレスチェックを受けて頂いています。
「ピラティスから考える腰痛予防レクチャー」を実施し、職員の腰痛対策を図っている。
訪問先でのご利用者の事故から、訪問時の交通事故、災害発生、苦情に至るまで、想定される事故・トラブルについては対応マニュアルを整備しています。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
業務改善には徹底して取組んでいる。詳しくは看護管理(主任)のインタビュー記事をご覧ください。
https://www.gci-zaitaku.co.jp/nurse-specialty/expertise-of-nursing-management/
特に、下記のコメントが訪問看護ステーション芍薬が日々業務改善に尽力している現状を的確に表しています。
「私たちは世界最高水準の在宅ホスピス緩和ケアを提供するという壮大な理念で看護をしていますが、このような壮大な理念は、ひとつひとつの細かな業務が正確かつ効率的に実行されることの積み上げなくして実現できないと思っています。この壮大な理念実現の為の基礎の基礎は一件一件の訪問です。一件一件の訪問、つまりそれらの訪問にかかわるご利用者と看護スタッフひとりひとりを大切にする為に、業務を円滑化することが大切だと思っています。」(1)課題の抽出:看護管理もしくは本部独自で課題の抽出にあたります。看護管理は主に看護実践に関する課題の抽出にあたり、本部は中長期的に組織全体が存続していく為の課題抽出にあたります。
(2)課題の構造化:まずは事業所単位で解決できる課題とそうではない課題に課題を整理します。後者の課題については看護管理と本部とで協力して課題解決にあたります。
構造化のアプローチは次の通り:
1.可視化:課題の全体を可視化する
2.優先順位付け:どの課題を解決するべきかを考える:組織理念、経営戦略、問題に対処しない場合のリスク(緊急度、影響の度合など)から総合的に判断
3. 原因分析:優先順位の高い課題に関してその課題(現象/症状)がなぜ起きているのか原因を深掘りする
4. 解決策の立案:課題の原因に対応するための解決策を探索する業務効率化の為にも常日頃から整理整頓には心がけています。特に、紙ベースの情報の整理整頓には煩雑さが伴う為、なるべくペーパーレス化を図っている他、紙の書類のファイリングは可能な限り本部事務職員が行っています。
(1)看護記録の標準化と共有:看護記録はSOAPとNANDAを採用し標準化しています。クラウド型カルテの為、どこに居ても情報共有が可能です。
(2)日々の情報の共有:日報も標準化・クラウド化されており、緊急電話も含めタイムリーな情報共有が可能です。
(3)専門的ケア実践の負担軽減と情報共有:難しいとされているスピリチュアルケアに関してSpiPas(注1参照)を採用し、スピリチュアルケアの経験が少ない看護師でも一定レベルのスピリチュアルケアの提供が可能となっています。また、構造化されたパスである為、複雑なスピリチュアルペインの内容整理と介入方法のヒントを複数看護師間で共有することが可能となっています。
(注1):主に終末期患者に発生するスピリチュアルペイン(生きる意味や実存に関する痛み:全人的苦痛のひとつ)を評価するためのアセスメントシート(1)介護ソフト:カナミック(AI機能を含む)
(2)情報端末:ノートPC、スマートフォン双方の貸与(1)ビジネスチャット(LINEをチャット的に活用)
(2)カナミックAI機能の活用
(3)音声自動入力機能&AI機能による看護記録自動作成(導入予定)タスクシフトの重要性を認識しており下記の全社方針を各事業所で実践しています
(1)看護の専門性がなくてもできることは、可能な限り事務職員/看護補助が行う
(2)看護補助の活用を積極的に行う:看護補助の管理監督責任は看護師にあるという認識を全スタッフと共有している(1)各種委員会の共同設置:法人傘下の全事業所が共同で次の委員会を開催しています:虐待防止委員会、安全衛生委員会、感染症防止委員会
(2)各種指針・計画の共同策定:上記に関連した指針・計画に加え、BCPに関連した指針・計画も共同で策定
(3)物品の共同購入等の事務処理部門の集約:物品は基本本部で法人傘下の全事業所ぶんを一括購入、一括受入し、標準在庫補充方式により各事業所に週に1回補充しています。
(4)共同で行うICTインフラの整備:法人本部が法人傘下の全事業所を念頭に入れ、ICTに関連した中長期経営計画を策定。当該計画に基づき業者と製品選定と導入を主導している。一方で、各事業所の個別ニーズに対応しICTインフラの微調整も行っている。
(5)人事管理システムや福利厚生システムも法人傘下の全事業所共通化している。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
(1)定例ミーティングその1:毎週火曜日:看護職員同士のミーティング
(2)定例ミーティングその2:毎週水曜日:全職種合同ミーティング(看護職、リハ職、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、事務職)
(3)定例ミーティングその3:毎週木曜日:看護管理者と本部職員ミーティング
(4)定例ミーティングその4:毎週金曜日:個人別関心事領域別ミーティング(小児看護など)
(5)定例ミーティングその5:毎月1回:全事業所管理職と本部幹部職員ミーティング地域ケアプラザの活動を積極的に支援するという基本方針のもと、具体的には下記の活動を行った。
(1)地域ケアプラザ主催の地域住民向け講習会(テーマは「熱中症予防」:参加者訳30名)で講師を務めた:参加者からの多数の質問があり活発な質疑応答となった
(2)(1)とは別の地域ケアプラザのボランティア交流会・慰労会(参加者訳50名)で訪問看護ステーション芍薬の登録ボランティアがハープ演奏し好評を博した
(3)小規模多機能事業所で、訪問看護ステーション芍薬の看護師がACPと人生会議について講義しその後参加者からの質疑応答に対応した利用者本位のケア方針の学習について:
訪問看護ステーション芍薬は在宅ホスピス緩和ケアに特化している。ホスピス緩和ケアの定義や理念はWHOに規定されている通り「個々の利用者らしさを大切に」するというものであり、スタッフは年間を通じてホスピス緩和ケア関連の研修を受講することで、結果利用者本位のケア方針を定期的に学ぶことになっている。
法人理念の定期的学習について:
毎年一回実施される自己評価票(リーダーシップ能力評価票)には法人理念が色濃く反映されている。この自己評価票を個々のスタッフが作成することで、法人理念を定期的に学ぶことになっている。(1)学会や研究会資料の共有:ケアの好事例を学会や研究会で発表した資料を内部でいつでも閲覧できるようにしています
(2)ご利用者・ご家族アンケートの共有:ご利用者・ご家族に対するアンケート結果(自由記述欄に謝意が記載されている)を内部で共有しています
併設されているサービス
母体組織の、経営資源(思い、夢、時間、エネルギー)を訪問看護に集中して投下し、もってこの領域で絶対的に高品質なサービスを提供する、という経営方針の為、訪問看護以外のサービスは訪問看護と有機的一体として提供できるサービスに限定しています。現在、訪問看護ステーション芍薬瀬谷(横浜市瀬谷区)と居宅介護支援事業所(GCIケアリング芍薬)と指定計画相談支援事業所(指定事業所名称は同じく「訪問看護ステーション芍薬」)がこうしたサービス事業所として機能しています。但し、地域の様々なサービスを提供する事業所と密接に連携することで、ご利用者様に必要なサービスが全て包括的に提供できるよう努めています。
保険外の利用料等に関する自由記述
介護保険ご利用の場合の保険外の利用料
通常の事業の実施地域を越えて行う交通費 公共交通機関使用による最短ルートの交通費実費相当額
サービス提供時間が1時間半を超過する場合の超過料金 超過時間30分まで: 4,000円
30分以上1時間未満: 8,000円
1時間以上1時間半未満: 12,000円
利用者の都合によるキャンセル料 当日のキャンセルの場合、利用者負担額の100%相当額(但し、利用者負担割合が0%の場合にはサービス費用総額の10%に相当する額)のキャンセル料をお支払い頂きます。ただし利用者の容態の急変など、緊急の場合や、やむを得ない事情がある場合には不要です。前日までに連絡があった場合には、キャンセル料は徴収致しません。
実施記録の複写物交付 A4、A3一枚につき10円
死後の処置料 28,000円
医療保険ご利用の場合の保険外の利用料
交通費 当事業所から半径1キロ圏内については無料。半径1キロを超える利用者宅については、通常サービス提供地域(別紙2参照)については一律440円とし、通常サービス提供地域外については一律880円とする。但し、夜間(夜10時から早朝6時まで)の訪問でタクシーを利用した場合は、440円にかえて2,000円をお支払い頂きます。また、通常サービス提供地域についても、地理的状況により、ご利用者様との協議の上、440円に替えて880円をお支払い頂く場合がございます。
平均的な時間を超える訪問看護料
超過時間30分まで: 4,000円
30分以上1時間未満: 8,000円
1時間以上1時間半未満: 12,000円
以降同様に30分あたり4,000円
日曜日と年末年始(12月30日から1月3日まで)における訪問看護料 開始時刻午前8時から午後6時まで:2,000円を加算
利用者の都合によるキャンセル料 当日のキャンセルの場合、利用者負担額の100%相当額(但し、利用者負担割合が0%の場合にはサービス費用総額の10%に相当する額)のキャンセル料をお支払い頂きます。ただし利用者の容態の急変など、緊急の場合や、やむを得ない事情がある場合には不要です。前日までに連絡があった場合には、キャンセル料は徴収致しません。
日常生活上必要な物品費 当事業所の購入価格に20%上乗せした金額をお支払い頂きます。
実施記録の複写物交付 A4、A3一枚につき10円
死後の処置料 28,000円
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
訪問看護ステーション芍薬はホスピス・緩和ケアに力を入れておりますので、がん患者さんも、痛みや苦痛なく最後まで安心して、そして安楽に在宅で療養していただけるよう、24時間365日の体制で看護がサポート致します。お困りのことがあればいつでもお電話ください。必要に応じて看護師が御自宅までかけつけます。
スタッフの特徴として看護師経管が20年前後の訪問看護師多く、また、これらの看護師は訪問看護師としての経験も10年前後で、がんだけではなく、認知症や心疾患、肝疾患等、非がん疾患、小児看護の緩和ケアにも力を入れたホスピス・緩和ケアを提供しています。また、病棟での看護と在宅看護は似て非なるものです。訪問看護ステーション芍薬は在宅ケアの特徴を深く正しく理解した上で、在宅での看護を提供します。
さらには、他職種で在宅ケアに取り組んでいるのも訪問看護ステーション芍薬の特徴です。ボランティア・コーディネーターが地域ボランティアの活動をマネジメントしたり、ほかのNPOと協働しながら当ステーションのご利用者にボランティア・サービスを届けたり、社会福祉士が研究活動や学会発表を通して訪問看護ステーション芍薬が提供するホスピス・緩和ケアの質の向上に貢献しています。私たちは、ご利用者様とそのご家族が在宅で安心して療養できるよう日々ご支援しながら、日本在宅ケア推進に貢献するという使命感をもっています。
下記は私たちの管理者の自己紹介です。
2009年3月に発表された「訪問看護10ヶ年戦略」では、国民が最後まで安心して療養生活を送れるよう、他機関・他職種と連携し、24時間365日にわたり療養生活と在宅看取りの支援を行うことを目的に訪問看護の普及に努めています。訪問看護が普及することは在宅医療の充実につながり、一人ひとりが安心して自分らしく暮らせる地域社会になると考えます。そのため訪問看護認定看護師として①地域住民への普及活動、②医療関係者への普及活動、③看護学生への普及活動を行っていきたいです。普及活動を行うにあたり何を伝えたいかを考えた時、在宅生活や訪問看護の「素晴らしさ」を伝えていきたいと思います。住み慣れた地域で”家庭の暖かさ”を感じていると、表情・会話・意欲も違ってきます。このことは療養者・家族・報も看護師を含む関係職種みんなうれしいことですね。今後も実践を継続しながら、自分自身の感動を増やし、多くの方に伝えていきたいと思います。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
現在130名程のご利用者様の在宅療養をご支援しておりますが、70名程が介護保険でのご利用、残る60名が医療保険でのご利用となっております。そのうちで、癌の末期の方が5名程おられ、平均すると毎月約5名の在宅看取り看護を行っております。在宅酸素ご利用の方や胃婁増設を行ったご利用者様も多く、重度の方や要介護度の高い方に対する在宅療養のご支援も行っています。神経難病や腹膜透析の患者さんにも多数訪問しています。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
朝8時30分~17時30分(休憩1時間)
賃金体系
(I)給与
月給制と時給制とがあります。月給制は週32時間以上勤務する場合、時給制はそれ以外に適用されます。
(1)月給制
(1-1)基準内賃金:基本給与と職責手当(みなし残業代:労働契約上の週当たり労働時間をみなし残業代として固定支給)、資格手当(専門・認定資格、特定行為研修修了者)
(1-2)基準外賃金:オンコール手当、通勤手当、引越手当、引越一時金
(1-3)割増賃金:時間外、深夜、休日など法定どおりの割増賃金
(2)時給制
(2-1)基準内賃金:基本時給
(2-2)基準外賃金:通勤手当
(2-3)割増賃金:時間外、深夜、休日など法定どおりの割増賃金
(II)賞与
固定賞与(6月と12月に支給)とパフォーマンスボーナス(10月に支給)があります。
固定賞与はオンコール対応者に支給し、パフォーマンスボーナスは前年度顕著な活躍や功績があった者に支給します。
休暇制度の内容および取得状況
(1)有給休暇:法定
(2)夏休み:正社員は年間5日間、正社員以外で勤続3年以上の者は各人の週当たり勤務日数に該当する夏休みを、5月から9月の間に取得することが可能です
(3)年末年始休暇:正社員について12月30日~1月3日(正社員以外は有給休暇などを活用して休んでいます)
(4)ボランティア休暇:正社員について年間3日間取得が可能
福利厚生の状況
(1)リロクラブ会員特典の利用が可能
(2)緑法人会会員特典の利用が可能
離職率
離職率5.8%
内訳:1年間の離職者数1名、1年前の在籍者数17名
計算式:5.8%=1/17×100
その他
直行直帰や、社用車での通勤が可能となっています。自宅近くに駐車場を借り上げ、オンコール対応時の効率化を図っています。
ケアの詳細(具体的な接し方等)
内部の環境(設備等)
-

社用車での通勤と訪問が基本です:オンコール対応時は高速道路料金も事業所負担です -

車の運転ができない方、もしくはごく近隣には電動アシスト付自転車で訪問しています -

ELNEC-Jコアカリキュラムを全看護職員に受講して頂いています。
ELNEC-Jコアカリキュラムの詳細は緩和医療学会のホームページをご覧下さい。
https://www.jspm.ne.jp/seminar/elnecj/about.html
- ナーシングスキル(看護師向けe-ラーニングツール)
- 全看護職員が個人別アカウントを保有し、自由に、好きな時間で効率的に学ぶことができます。1講座15分程度で動画もある他、受講履歴が記録されるなど、個人のキャリアプランに沿った効果的な学習が可能です。
行事等のイベントの計画、記録
2025芍薬会 6月7日(土)(計画発表&研修の部、懇親会の部)
【場所】:貸会議室/貸切レストラン(詳細は下記ご参照ください)
【形式】:オンサイトのみ
【時間】:
計画発表&研修の部:8:30am-12:30pm
懇親会の部:1:00pm-3:00pm
【内容】
計画発表の部:本部より次年度経営目標の発表と各部門より次年度計画の発表
研修の部:
(1)講演「腹膜透析訪問看護の実際」(講師:訪問看護ステーションおりづる 管理者 大島香美様)
(2)BCP訓練 (ファシリテーター:社会保険労務士 相原陽二様)
【場所の詳細】
計画発表&研修の部:
開催地: 横浜市神奈川区西神奈川1-6-1 サクラピアビル4F 横浜セネックスC会議室
(東神奈川駅より徒歩1分)
懇親会の部:
開催地:横浜市神奈川区西神奈川2-9-11 SustainuS 1F
(東神奈川駅寄り徒歩圏:東白楽駅より徒歩2分)
地域との交流の様子
-

地域ケアプラザで地域住民向けに講演会を開催しました -

小規模多機能事業所でエンドオブライフケアやもしも手帳について講演会を開催しました -

特別養護老人ホームでエンドオブライフケアや終末期に特有の痛みについて講演会を開催しました
利用者の一日の流れ
毎週、ケアマネージャーが決定した曜日と時間帯に訪問看護ステーション芍薬の訪問看護を受けています。
送迎に関する情報(地区、曜日、個別対応(寝たきり等)の可否等)
通院や買い物などで移動が必要なご利用者には、看護補助制度を活用して看護師の監督のもと、安全かつ安価な移動支援をしています。
個別の機能訓練の詳細
主治医の指示のもと、訪問看護師がアセスメントし機能訓練の具体的内容を決定した上で、専門のリハビリスタッフ(理学療法士、言語聴覚士)が直接機能訓練にあたります。また、専門のリハビリスタッフのアドバイスを受け、訪問看護師が機能訓練をする場合もあります。
その他
事業所や周囲の外観
-

訪問看護ステーション芍薬外観
事業所の雰囲気
-

多職種の幅広い叡智を結集しています。 -

会議室 -

談話室
ブログやSNSへのリンク
https://www.gci-zaitaku.co.jp/category-35/non-cancer-hospice-palliative-care-nasal-high-flow/
https://www.gci-zaitaku.co.jp/category-47/expertise-of-rehabilitation-professionals/
https://www.gci-zaitaku.co.jp/category-40/about-gci-meaning-peony-japanese/
事業所のパンフレットや広報物
法人全体の離職率
離職率3%
内訳:1年間の離職者数1名、1年前の在籍者数30名
計算式:3%=1/30×100