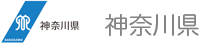2025年11月25日11:55 公表
きてケアプランセンター

サービスの内容に関する写真
-

わたしの名前はKite -

ぼくの名前はSava -

事業所外観
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
10/10人 -
最大受け入れ人数10人中、現在の受け入れ可能人数10人です。
(2025年10月05日時点)
サービスの内容に関する自由記述
きてケアプランセンターは、居宅介護支援事業所として、京浜(東京・川崎・横浜)地区を中心に、地域に根ざした総合的かつ質の高いケアマネジメントを提供しています。私たちは、「わたしが私らしく活躍できる社会づくりに貢献する」という理念のもと、ご利用者様一人ひとりの人生に寄り添い、その人らしい生活を支えるためのケアプランを策定しています。
当センターのサービスは、単なる介護計画の作成に留まらず、医療・介護・福祉・地域社会の各分野を統合した包括的支援を特徴としています。介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心となり、ご利用者様およびご家族の生活状況や健康状態、心理面、社会的環境を多角的に評価(アセスメント)し、科学的根拠に基づいたケアプランを構築します。支援過程においては、利用者様の「自分らしく生きたい」という思いを最も重要な指針とし、生活機能の維持・改善を目指した実践的な支援を行っています。
地域の医療機関や訪問看護ステーション、デイサービス、訪問介護事業所、福祉用具事業者、短期入所施設、地域包括支援センターなど、多職種・多機関との協働体制を強化しています。特に、医療依存度の高い方や在宅での医療的ケアを必要とする方に対しては、医師・看護師・リハビリ専門職との緊密な連携により、切れ目のない支援体制を構築しています。さらに、ICT(Information and Communication Technology)およびDX(Digital Transformation)を積極的に導入し、電子情報共有を通じて、効率的かつ迅速な連携を実現しています。
私たちのサービスの根幹には、「地域で暮らし続ける力を支える」ことがあります。高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護予防やリハビリテーション支援、認知症ケア、終末期支援など、ライフステージに応じた継続的なサポートを行っています。また、ご家族の介護負担軽減にも力を入れ、レスパイトケアや相談支援を通じて、在宅生活の継続を支えています。
加えて、私たちは社会的背景の変化にも柔軟に対応しています。独居高齢者や老老介護世帯、外国籍の方、就労と介護を両立する世帯など、多様なニーズに対応するための地域連携モデルを構築しています。地域包括ケアの理念に基づき、行政や企業、地域住民との協働を推進し、共生型社会の実現に向けた取り組みを継続しています。
当センターでは、専門職としての資質向上にも力を注いでいます。定期的な研修や事例検討、学会・外部講習への参加を通じて最新の知見を取り入れ、科学的介護・倫理的実践・心理的支援を融合した質の高いケアマネジメントを提供しています。また、従業員間でのチームアプローチを重視し、情報共有・相互支援を通じて安定した支援体制を維持しています。
これらの取り組みを通じて、私たちは「介護を通して人と人がつながる社会」を目指しています。介護は支援を必要とする方のためだけでなく、地域全体を温かく照らす灯火となるものです。きてケアプランセンターは、地域の皆様が「自分らしく生きる」ことを支えるパートナーとして、専門性と人間性の両面から最適な支援を提供し続けてまいります。今後も、変化する社会の中で柔軟に対応しながら、すべての人が安心して暮らせる地域づくりに貢献していきます。
サービスの質の向上に向けた取組
きてケアプランセンターは、「わたしが私らしく活躍できる社会を創る」という理念のもと、地域に根ざした居宅介護支援を通じて、ご利用者様の尊厳を守り、生活の質(QOL)を高めることを使命としています。その実現のため、私たちは「専門性の向上」「多職種・地域連携」「科学的介護とDX推進」「フィードバックと改善」の4本の柱を中心に、継続的なサービスの質の向上に取り組んでいます。
① 専門性の向上と人材育成
介護支援専門員としての専門性と倫理性を高めるため、全職員を対象とした定期研修・勉強会を体系的に実施しています。研修内容は、介護保険制度改正への対応、最新の医療・福祉・リハビリテーション・心理分野の知見、認知症ケア、終末期支援、BLS(一次救命処置:Basic Life Support) など、多岐にわたります。また、外部研修・学会参加を推奨し、科学的根拠に基づくケアマネジメント(Evidence-Based Practice)の実践力を養っています。
さらに、スタッフ個々のキャリアパスを尊重し、主任介護支援専門員や社会福祉士等の上位資格取得を支援する体制を整えています。これにより、利用者一人ひとりの状態像に応じた高水準のアセスメントとプランニングを可能にしています。
② 多職種・地域連携の強化
地域包括ケアシステムの要として、医療・介護・福祉・行政・地域住民との協働を推進しています。地域の医療機関、訪問看護ステーション、デイサービス、居宅サービス事業所との定期的な連携会議を通じて、支援の質を高める仕組みを整備しています。
特に、京浜地区特有の多様な地域特性を踏まえた包括的支援を展開し、在宅療養支援やリハビリテーション、社会的孤立防止など、地域課題の解決にも寄与しています。また、災害時や感染症流行時にも途切れない支援体制を構築するため、事業継続計画(BCP)訓練を定期的に実施し、地域防災力の一翼を担っています。
③ 科学的介護・ICT・DXの推進
サービスの質を科学的に高めるため、ICT(情報通信技術)やDX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に導入しています。電子ケアプランシステムを活用し、記録の標準化・共有化を進め、リアルタイムでの多職種連携を可能にしています。また、AIを活用したケアプラン分析や、介護記録の自動要約システムを試験的に導入し、業務効率化と支援の質の両立を図っています。これにより、職員がより多くの時間を利用者様との直接的な支援に充てることが可能となりました。
加えて、オンライン会議やリモートカンファレンスの活用により、地域や職種を超えた情報共有を促進し、広域的な支援ネットワークの形成を実現しています。
④ フィードバックと継続的改善
きてケアプランセンターでは、利用者満足度調査や家族からの意見聴取を通じて、サービスの改善点を可視化し、全職員で共有・検討しています。職員会議や事例検討会では、倫理的課題や支援困難事例を取り上げ、改善策を協議・実践しています。
また、年度ごとに短期・中長期の質的向上目標を設定し、達成度を定期的に評価・分析しています。このPDCAサイクルを通じて、個々の事例に応じた支援手法を精緻化し、常に「現場から進化する」組織運営を目指しています。
さらに、外部機関による指導・監査の結果を積極的に取り入れ、透明性と説明責任を果たしながら、社会的信頼性の高い事業所運営を継続しています。
⑤ 今後の展望
今後も、私たちは「人と人が支え合い、尊厳をもって生きられる社会」を実現するため、職員一人ひとりが専門性と創造性を発揮し続けます。DXやAIの進化を福祉の現場に適切に取り入れ、より効率的かつ温かなケアを実現するとともに、介護を担う人材の働きやすい環境整備にも力を注ぎます。
きてケアプランセンターは、地域に信頼される存在として、すべての利用者様が「わたしが私らしく」生きられるよう支援し続け、福祉と医療の未来を見据えた質の高いサービス提供を継続してまいります。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
きてケアプランセンターを運営する Kite art factory LLCは、
「わたしが私らしく活躍できる社会づくりに貢献する」 という経営理念を核としています。
この理念は、すべての人が年齢・性別・国籍・背景を超えて、自分らしく生き、尊厳をもって暮らせる社会の実現を目指すという私たちの基本的価値観を表しています。
法人として、介護・医療・福祉を通して社会の希望を育み、地域と共に成長する事業体であることを使命としています。
・ケア方針
当センターのケア方針は、
「尊厳・自立・共生」 の三原則を基盤とし、
ご利用者様の「生活の継続性(Continuity of Life)」を支えること、
科学的根拠に基づく支援(Evidence-Based Practice)を推進すること、
の三点を柱としています。
すべての支援は、ご利用者様の意思決定を尊重し、「その人らしさ」に焦点を当てたパーソン・センタード・ケアを実践します。
また、医療・介護・福祉・地域資源との多職種連携を強化し、在宅での療養支援、認知症ケア、介護予防、家族支援などを包括的に提供しています。
災害・感染症などの危機時にも支援が途絶えないよう、BCP(事業継続計画)体制の整備・訓練を行い、安定した支援を確保しています。
・人材育成方針
法人の最大の財産は「人」であり、職員一人ひとりが専門職として成長できる環境づくりを重視しています。
人材育成の基本方針は、
専門性の深化(専門資格の取得・更新支援)
人間性と倫理観の涵養(介護倫理・人権・接遇研修)
組織としての学習文化の形成(ケース検討・OJT・ピアレビュー)
の3本柱です。
新人研修から主任介護支援専門員研修、BLS(一次救命処置:Basic Life Support)・認知症ケア・医療連携研修までを体系的に整え、実践力を高めています。
また、職員同士の相互支援とチームワークを育てるため、定期的な事例検討会やリフレクションミーティングを実施しています。
これにより、「一人の専門職として」だけでなく、「チームの一員として利用者を支える力」を強化しています。
・実現のための施策・仕組み
理念と方針を実現するため、以下の仕組みを体系的に運用しています。
質の向上に向けたPDCAサイクルの確立
年度ごとに質的目標を設定し、達成度を職員全体で評価・改善。利用者満足度調査・職員アンケートも定期実施。
ICT・DXによる効率化と情報共有
電子ケアプランシステム・クラウド型記録共有を活用し、医療・介護の多職種間でリアルタイムな情報連携を実現。
AI(人工知能)を用いたアセスメント支援や業務自動化も推進。
地域との協働と社会貢献
地域包括支援センターや医療機関、行政・企業との連携強化により、京浜地区の福祉向上と地域課題の解決に貢献。
介護と就労の両立支援、介護予防啓発、地域防災ネットワークへの参加など、地域社会との共生を実践。
働きやすく学び続けられる職場環境の整備
柔軟な勤務体制、心理的安全性の高い職場づくり、定期面談・メンタルサポートの実施などにより、職員の定着率とモチベーションを維持。
・展望
きてケアプランセンターは、これからも「人が人を支える」温かいケアの本質を大切にしながら、デジタルと人間力の融合による次世代型ケアマネジメントを実現してまいります。
すべてのご利用者様が「わたしが私らしく」生きることのできる社会の創造に向け、職員一人ひとりが理念の体現者として成長し続ける組織であり続けます。-
-
-
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
-
-
-
-
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
-
-
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
-
-
-
-
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
きてケアプランセンターでは、厚生労働省が示す「介護サービス事業における生産性向上ガイドライン」に基づき、少人数体制の中でも業務効率化と支援の質の両立を図るための取組を行っています。
当センターは「わたしが私らしく活躍できる社会づくりに貢献する」という法人理念のもと、地域に根ざした居宅介護支援事業所として、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活の継続を支えるケアマネジメントを実践しています。
① 生産性向上委員会の設置と運営体制
少人数での運営であるため、形式的な委員会体制ではなく、管理者兼主任介護支援専門員を中心に事務担当者と協働しながら、日常的に業務改善を行う体制を整えています。
定期的に業務の振り返りを実施し、課題の抽出、対応策の立案、改善の実施・検証を繰り返すことで、効率化と質の向上を両立しています。
特に、ケアプラン作成手順や記録・情報共有の流れなどについては、AIを活用した議事録作成・議事要約システムを導入し、会議内容の正確な記録と改善提案の継続的な可視化を実現しています。これにより、職員間の意識共有が迅速化し、業務改善の進捗管理にも効果を上げています。
② 協働体制と役割分担による業務改善の推進
当センターは管理者と事務員の二人体制で運営しているため、課題ごとにチームを分けるのではなく、日常業務の中で課題を共有し、即時対応・改善を行う「協働型改善方式」を採用しています。
現場で発生した課題をその場で協議し、役割を分担して解決へ導くことで、業務の停滞を防ぎ、柔軟かつ持続的な改善を可能にしています。
主な改善テーマは次のとおりです。
ICT・DX推進:電子ケアプランシステム・クラウド記録の効率的運用
事務効率化:帳票整理や入力作業の省力化、テンプレート化による業務標準化
情報連携:医療・介護事業所、包括支援センターとの連携手順明確化
職員教育・支援:制度改正情報・研修資料の共有と振り返りによる実務力向上
少人数ならではの密な連携と即応性を強みとし、形式的な会議ではなく、日常の中で自然に改善を積み重ねる実践的な仕組みを確立しています。
③ 外部研修・行政情報の活用
外部講師を招いた研修や職員派遣は実施していませんが、行政や公的機関が発信する最新の研修資料やガイドラインを積極的に活用しています。
厚生労働省が公表する「生産性向上ガイドライン」「介護DX推進指針」、横浜市および神奈川県が実施するオンライン研修等を参考にし、現場改善の方向性に反映しています。
また、地域包括支援センターや近隣事業所との情報交換を通じ、連携業務や情報共有方法の効率化を図っています。
④ ICT・AIの活用と業務の標準化
当センターでは、ICT(情報通信技術)およびDX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に導入し、業務の省力化と精度向上を進めています。
電子ケアプランソフトを中心にクラウド環境を整備し、記録や情報共有を一元化することで、転記や二重入力の削減を実現しています。
さらに、AI(人工知能)を活用した文書作成支援や会議記録・議事要約の自動生成を行い、記録作業の時間を大幅に削減しています。これにより、ケアマネジャーがより多くの時間を利用者支援や多職種連携に充てられるようになりました。
業務手順や文書様式の標準化も進めており、属人的な作業を最小化し、誰が担当しても一定水準の支援を提供できる体制を整えています。
⑤ 今後の展望
今後も、生産性向上ガイドラインに基づき、少人数体制でも実行可能な改善活動を継続していきます。
AI・ICTを効果的に活用し、事務効率化と情報精度の向上を両立させながら、介護支援専門員の専門性を発揮できる環境を整備していきます。
また、地域や行政との連携をさらに強化し、地域包括ケアの中核として、より質の高い支援と業務の持続可能性を追求します。
きてケアプランセンターは、少人数だからこそできる柔軟な改善と、AI技術を活かした新しい働き方で、地域に信頼される事業所づくりを進めてまいります。きてケアプランセンターでは、厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上ガイドライン」に基づき、現場における業務課題を「見える化」することを重要な取り組みの一つとして位置づけています。
私たちは「わたしが私らしく活躍できる社会づくりに貢献する」という法人理念のもと、少人数体制の中でも持続可能な運営と高品質な支援の両立を目指し、業務の実態を客観的に把握しながら、改善に結びつける仕組みを構築しています。
① 課題の抽出と共有の仕組み
当センターでは、日常業務を通じて生じる課題を随時記録・共有する体制を整えています。
管理者兼主任介護支援専門員と事務員の間で、日々の業務の中で気づいた課題(書類作成の重複、連絡手段の非効率性、情報共有の遅延、時間外対応の発生など)を即時に整理・記録し、定期的に協議しています。
これらの課題はAIを活用した会議記録および議事要約ツールにより自動的に可視化され、改善提案や優先順位づけを容易にしています。
また、利用者支援における困難事例や制度改正に伴う対応課題もリスト化し、発生頻度や影響度を基準に体系的に分類しています。
このように「現場で感じた小さな違和感」を確実に言語化・記録化することで、問題の早期発見と再発防止につなげています。
② 課題の構造化と改善優先度の明確化
抽出された課題については、「発生要因」「影響範囲」「改善効果」「対応難易度」の4つの視点から整理・構造化しています。
たとえば、ケアプラン作成や給付管理業務に関する時間的負担は「作業工程の多層化」が要因であり、情報伝達の遅れは「連絡経路の不統一」が根底にあるなど、課題を要因ごとに可視化する分析を行っています。
これにより、単なる現象の羅列ではなく、「何を改善すれば根本的な効果が得られるか」を明確化しています。
優先度の高い課題については、対応スケジュールを設定し、改善内容を具体的な手順書に反映することで、改善サイクルを定常化しています。
また、改善結果については、AIによる議事録データを活用し、定量的な変化(処理時間の短縮・記録精度の向上など)を検証しています。
③ 業務時間調査の実施と分析
業務全体の負担を客観的に把握するため、定期的に「業務時間の可視化調査」を実施しています。
一日の業務を「利用者対応」「記録・書類作成」「情報共有」「事務処理」「相談対応」「訪問」「会議・打合せ」などに分類し、所要時間を集計しています。
AIによる記録支援ツールを活用することで、入力作業を最小限にしながら、業務量の偏りや時間配分を可視化することが可能となりました。
その結果、事務作業に要する時間が全体の約40%を占めることが判明し、記録様式の統一やテンプレート化、クラウド管理による転記削減といった具体的な改善策につなげています。
また、繁忙期や月末業務など特定時期の負荷も数値化しており、業務の平準化に向けた日程調整や作業手順の再設計に役立てています。
④ ICT・AIを活用した課題の見える化
当センターでは、AI(人工知能)およびICT(情報通信技術)を積極的に活用し、課題の抽出と改善プロセスの可視化を支援しています。
具体的には、AIによる会議記録・要約機能を利用して日々の打合せ内容を自動的に整理し、課題ごとの進捗状況や改善履歴をデジタルで管理しています。
また、クラウド型の業務管理ツールを導入し、ケアプラン作成状況や給付管理スケジュールなどをリアルタイムで確認できる体制を整備しました。
これにより、少人数でも全体の業務負荷を俯瞰的に把握し、業務配分の調整を迅速に行うことが可能となっています。
⑤ 今後の展望
今後も、業務の「見える化」を通じて、課題発見から改善までを体系的に行う仕組みを継続していきます。
AIを活用したデータ収集・分析をさらに発展させ、業務時間や事務負担を定量的に把握することで、改善効果の検証と再評価を行う予定です。
また、職員間での意見交換を重ねながら、利用者支援により多くの時間を充てられる業務体制の構築を進めていきます。
きてケアプランセンターは、少人数体制の中でも「課題を見える形にする」ことを通じて、より効率的で質の高い支援を提供し続けることを目指しています。きてケアプランセンターでは、厚生労働省が推進する「介護サービス事業における生産性向上ガイドライン」の理念に基づき、業務の効率化と働きやすい職場環境の両立を目指して、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を継続的に実践しています。
少人数体制の事業所であるからこそ、限られたスペースと時間を最大限に活用するために、環境整備を日常業務の一部として位置づけ、日々の小さな改善を積み重ねる取り組みを行っています。
① 整理(Seiri)- 不要なものを取り除く
まず、「整理」の基本として、日常業務で使用頻度の低い書類や備品の見直しを定期的に行っています。
紙媒体で保管していた文書や帳票類は、スキャン後にクラウド上で安全に管理し、物理的な書類の削減を進めています。
これにより、不要な資料や重複ファイルの保管を避け、作業スペースを確保するとともに、情報検索の効率化を実現しています。
また、介護保険制度改正などにより不要となった過去資料も定期的に整理し、常に「今必要な情報」にアクセスできる状態を維持しています。
② 整頓(Seiton)- 使いやすいように配置する
次に、「整頓」として、使用頻度の高い物品・書類を明確に区分・配置する工夫を行っています。
文書フォルダや棚のラベリング、デジタルフォルダの命名規則統一など、アナログとデジタルの両面での整頓を徹底しています。
また、業務で使用する文書テンプレートや帳票類を電子データとして統一フォルダに格納し、誰が作業しても同じ手順で業務を進められるようにしました。
これにより、無駄な検索時間を削減し、限られた職員であっても即時に業務を引き継げる環境を整えています。
③ 清掃(Seisou)- 日常的な清掃と点検の徹底
職場内の清掃は、日々の業務終了時に実施しています。
机上・共有スペース・備品・電子機器などをこまめに清掃し、清潔な環境を維持しています。
また、感染症対策の観点から、ドアノブや電話機、共有パソコンなど、接触頻度の高い箇所の消毒を定期的に行っています。
清掃を単なる衛生管理としてではなく、「職場の安全と安心を守るための点検行為」として位置づけ、環境の変化に敏感に対応できるよう努めています。
④ 清潔(Seiketsu)- 維持・標準化の仕組み化
「清潔」の段階では、整理・整頓・清掃で整えた状態を維持するための標準化を行っています。
書類や備品の配置ルール、文書の命名規則、デジタル記録の保管基準などを文書化し、業務の属人化を防いでいます。
さらに、AI(人工知能)を活用した会議記録・議事要約ツールを利用し、業務改善の進捗や環境整備に関する振り返りを自動的に記録・整理する仕組みを導入しています。
このデジタル化により、職員の手間を増やさずに職場の整頓状況を管理でき、5Sの維持が容易になりました。
⑤ 躾(Shitsuke)- 習慣化と意識の定着
5S活動の最終段階として、「躾=継続的な実践」を重視しています。
日々の業務の中で自然に整理・整頓・清掃を意識できるよう、毎週の終業時に5分間の「環境チェックタイム」を設けています。
小規模事業所である利点を活かし、管理者と事務員が互いに声をかけ合いながら、改善点をその場で話し合い、翌日にはすぐ実行に移すというサイクルを確立しています。
また、5Sを単なる物理的な環境整備にとどめず、「気持ちよく働ける職場をつくるための文化」として定着させています。
整理された空間が職員の集中力と意欲を高め、結果として利用者支援の質向上にもつながっています。
⑥ 今後の展望
今後も、5S活動を業務改善の基盤として継続し、「整った職場が正確で迅速な支援を生む」という考え方のもと、さらなる環境整備を進めます。
特に、AIやICTを活用した書類整理・情報共有の自動化を推進し、職員の事務負担軽減と時間創出を図ります。
また、業務空間の清潔維持を通じて感染症予防・安全管理の強化にもつなげ、職員が安心して働ける環境を整えることで、利用者に対しても安定した支援を提供してまいります。
きてケアプランセンターは、5S活動を単なる整理整頓の手法としてではなく、「人と仕事の質を高めるための土台」と位置づけ、少人数でも持続的に実践できる工夫を重ねながら、地域に信頼される事業所運営を続けてまいります。-
きてケアプランセンターでは、業務の効率化と情報の正確性・即時性を高めることを目的として、介護ソフトおよび情報端末(パソコン・タブレット端末・スマートフォン等)を導入しています。
これらのICTツールを活用し、記録作業の標準化、情報共有の迅速化、請求事務の効率化を実現することで、少人数体制でも安定した事業運営を可能にしています。
厚生労働省が推進する「介護DX推進指針」に基づき、デジタル化と業務の見える化を同時に進め、職員の負担軽減と利用者支援の質の向上を図っています。
① 介護ソフトの導入と活用
当センターでは、記録、ケアプラン作成、給付管理、請求事務など日常業務を一元的に管理できる介護支援ソフトを使用しています。
このソフトの導入により、ケアマネジメントの各工程で入力された情報を統合的に管理でき、業務全体の流れが整理されました。
また、過去の記録や計画書を容易に参照できるため、利用者の経過把握が円滑となり、支援の継続性と正確性が高まりました。
帳票の自動作成や検索機能を活用し、必要な情報を迅速に取り出せることで、事務負担を軽減し、ミス防止にもつながっています。
さらに、ソフト内でのコメント共有機能を活用し、ケアマネジャーと事務員がリアルタイムで情報を共有できる体制を構築しました。
これにより、情報の取りこぼしを防ぎ、限られた人員でも正確で迅速な対応が可能となっています。
② 情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)の活用
業務のデジタル化を進めるため、タブレット端末およびスマートフォン端末を導入し、外出先でも必要な情報にアクセスできる環境を整えています。
訪問時や会議の際にタブレットを使用することで、現場で即時に記録を確認・入力でき、帰所後の作業を削減しました。
クラウド環境を活用し、事業所内外で同一データを安全に閲覧・更新できるようにしており、データ通信にはアクセス制限やVPN接続などのセキュリティ対策を講じています。
スマートフォン端末では、職員間の情報連絡やスケジュール共有、緊急時対応を迅速に行う体制を整え、連携の即時性と業務の正確性を高めています。
このような環境整備により、時間と場所にとらわれない柔軟な働き方を実現し、生産性向上と職員の業務負担軽減を両立しています。
③ AI・ICT連携による文書作成・会議支援
介護ソフトに加え、AI(人工知能)を活用した文書作成支援および会議記録要約システムを導入しています。
会議や打合せ内容をAIが自動で要約し、議事録として整理・保存することで、記録作成の手間を軽減し、内容の正確性を高めています。
また、アセスメントやモニタリング記録作成時にはAI支援機能を利用し、下書き作成を自動化することで、書類作成時間の短縮を実現しました。
これらの仕組みにより、ケアマネジャーが利用者支援や多職種連携により多くの時間を充てられるようになっています。
ICTとAIの併用により、日々の業務を「記録する」から「分析し活用する」段階へと進化させています。
④ 業務効率化と生産性向上への効果
介護ソフトおよび情報端末の導入により、従来手作業で行っていた文書整理や確認業務の時間を大幅に削減しました。
特に、記録様式の統一化と検索性の向上により、情報の重複や漏れを防ぐことができています。
また、リアルタイムでの情報共有が容易となり、限られた人員でも安定したケアマネジメントを維持できるようになりました。
これらの取り組みにより、事務作業の効率化にとどまらず、利用者支援全体の質的向上にもつながっています。
⑤ 今後の展望
今後も、ICTとAIを活用した業務改善を継続し、介護現場の生産性向上と支援の質の両立を目指します。
LIFE(科学的介護情報システム)や自治体システムとのデータ連携を進め、記録・情報共有の自動化をさらに推進していく予定です。
また、セキュリティ対策や操作教育を継続し、誰もが安心してICTを活用できる職場環境を維持します。
きてケアプランセンターは、少人数体制の中でもデジタル技術と人の力を融合させ、効率的で質の高いケアマネジメントを実現し、地域社会に信頼される事業運営を続けてまいります。きてケアプランセンターでは、業務の効率化および情報共有の迅速化を目的として、ICT機器を積極的に導入しています。
当センターは居宅介護支援事業所であり、介護ロボット(見守り支援・移乗支援・排泄支援等)は導入していませんが、職員間の情報伝達や外部関係機関との連携を円滑に行うためのICTツールを活用しています。
少人数体制の中でも、正確かつ迅速な情報共有を実現することにより、利用者支援の質を維持・向上させることを目指しています。
① 連絡調整におけるICT機器の活用
職員間の連絡には、クラウド型ビジネスチャットツールおよびスマートフォン端末を活用しています。
日々の連絡事項や業務進捗、会議議題などを電子的に共有することで、電話や紙媒体による伝達に比べ、迅速で確実な情報共有が可能となりました。
また、メッセージの履歴が自動保存されるため、確認漏れや伝達ミスを防ぎ、情報の透明性と再現性を確保しています。
特に、外出や訪問の多い業務特性を踏まえ、モバイル環境でも安全にアクセスできる体制を整えており、職員が場所を問わず円滑に業務連絡を行えるようにしています。
加えて、業務用メールやカレンダー共有機能を組み合わせることで、予定調整・面談日時の確認・関係機関との打合せ調整なども効率化されました。
この結果、事務的なやり取りの簡素化だけでなく、利用者や家族への対応スピードの向上にもつながっています。
② 会議・打合せのデジタル化とAI支援の活用
定期的な会議や打合せにおいては、AI(人工知能)を活用した自動議事録作成システムを導入しています。
会議中の発言内容をリアルタイムで文字化・要約し、議事録として自動保存することで、記録作業の負担を軽減するとともに、内容の正確性を確保しています。
この仕組みにより、口頭での連絡やメモに頼ることなく、職員間の意思疎通がスムーズになりました。
また、過去の会議記録を検索・参照することが容易になり、業務改善や課題解決の経緯を振り返る際にも有効活用しています。
少人数の事業所であるため、日常的な連絡や検討は短時間で行うことが多いですが、AI支援により会議内容が自動的に整理・保存されることで、情報共有の質とスピードが大幅に向上しています。
③ スマートフォン端末による外出時の情報共有
外出先での対応や訪問時の連絡には、スマートフォン端末を活用しています。
特に、訪問先での急な予定変更や、医療機関・他事業所からの連絡対応などにも即時に対応できる体制を整えています。
これにより、事務所外でもリアルタイムで連絡が取れるようになり、迅速な意思決定と報告体制を確立しています。
また、セキュリティ面にも配慮し、端末にはアクセス制限・パスワード管理を設定し、個人情報を取り扱う通信にはVPN(仮想専用線)を活用しています。
これにより、外出時にも安全かつ安心して情報共有を行うことが可能です。
④ 情報管理・セキュリティ体制の強化
ICT機器の導入に伴い、情報セキュリティの確保にも注力しています。
すべての通信データは暗号化し、アクセス履歴を定期的に確認することで不正アクセスを防止しています。
また、重要なデータはクラウド上で安全に管理し、バックアップ体制を整えることで、万が一のデータ損失にも備えています。
個人情報保護の観点から、業務外でのデータ持ち出しを禁止し、端末利用に関する職員教育も随時実施しています。
これらの取り組みにより、ICTを活用した情報共有の利便性と、個人情報保護の両立を実現しています。
⑤ 今後の展望
今後は、既存のICT環境をさらに発展させ、関係機関(訪問看護・介護事業所・医療機関等)との情報共有をよりスムーズに行える体制を構築していく予定です。
また、AI支援ツールやビジネスチャットの活用を強化し、業務改善会議や記録整理を自動化することで、職員が利用者支援に専念できる環境を整えてまいります。
少人数体制であっても、デジタル技術を最大限に活用し、効率的かつ安全な情報連携を行うことで、介護支援専門員としての専門性を発揮できる仕組みを確立していきます。
きてケアプランセンターは、介護ロボット等の機器を導入していない事業所でありながら、ICTとAIを効果的に活用し、限られた人員でも高品質な支援を継続できる体制づくりを推進しています。
これからも、業務効率化と情報共有の質向上を両立させ、地域に信頼される事業運営を続けてまいります。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
-
-
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
きてケアプランセンターを運営する Kite art factory LLCは、「わたしが私らしく活躍できる社会づくりに貢献していく」という経営理念のもと、地域に根ざした専門職の集団として活動しています。私たちのチームは、医療・介護・福祉・心理・社会学などの幅広い分野における専門資格と実践経験を有し、科学的根拠に基づく支援を提供しています。すべての職員が、「一人ひとりの生き方を尊重し、その人らしさを支える」という共通の使命感を持ち、日々のケアマネジメントに取り組んでいます。
「きて Kite」という名称には、「気持ちが軽くなる場所へ、きて」「つながりを感じに、きて」「安心がそばにある毎日を届けに、きて」という三つの想いが込められています。この理念のもと、職員一人ひとりがご利用者様とご家族の心に寄り添い、安心と信頼を提供できるよう努めています。困難な状況においても希望を見出し、「わたしが私らしく」生きるための支援を継続的に行うことが、私たちの存在意義です。
当事業所の強みは、京浜(東京・川崎・横浜)エリアに精通した地域密着型の専門性です。都市部特有の多様な生活背景や社会課題を深く理解し、地域医療機関、行政機関、介護事業所、企業などと強固なネットワークを構築しています。こうした連携体制を活かし、医療的ケアを要する高齢者、認知症、精神疾患、難病など多岐にわたるケースに対しても、迅速かつ包括的な支援を実現しています。職員同士は「チームワーク」と「個の専門性」の調和を大切にし、ケースカンファレンスや事例検討会を通じて知識を共有しながら、常に質の高いケアを追求しています。
さらに私たちは、介護の未来を見据えた「変革の担い手」としての使命を自覚しています。DX(Digital Transformation)やICTを活用した情報共有体制の整備、AIやロボティクス技術の導入による業務効率化、職員教育の標準化を進めています。これにより、限られた人材でも持続可能なサービス提供を実現し、介護保険制度の安定運用に寄与しています。また、社会的課題の解決に向けて、行政や企業、地域住民と連携したソーシャルアクションを推進し、制度や慣習の枠を超えた新しい福祉の形を模索しています。
超高齢社会において、介護はもはや一部の専門職だけで担うものではなく、地域社会全体で支え合う時代を迎えています。私たちは「介護は社会の希望である」という信念のもと、介護を通して人と人がつながり、互いを支え合う温かいコミュニティを築くことを目指しています。そのために、介護予防の推進や家族支援、地域包括ケアの充実、働く世代への両立支援にも力を注いでいます。職員一人ひとりがその専門性を社会に還元し、介護の社会的価値を高める啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
私たちの最終的な目標は、『人々が光り輝ける社会づくり』にあります。きてケアプランセンターの職員は、利用者様・ご家族・地域社会のすべての人が自分らしく生きられるよう、「希望の光をともすケアマネジャー」として日々研鑽を重ねています。互いに尊重し、支え合いながら、笑顔と安心があふれる未来を創造していくことこそ、私たちの使命です。地域と共に歩み、社会全体を優しく照らす存在であり続けることを、全職員が誇りとしています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
きてケアプランセンターをご利用いただいている方々は、京浜(東京・川崎・横浜)地区に長くお住まいの高齢者が中心です。この地域は戦後の復興期から高度経済成長期にかけて産業・物流・商業の中核を担ってきた地域であり、多くの利用者様がその時代を支えた経験をお持ちです。かつては企業の現場や家庭、地域社会の中心で活躍されてきた方々が多く、製造業、流通業、教育、医療、行政など、幅広い分野で社会の発展に貢献されてきました。その豊かな人生経験と誇りは、地域社会の文化的・人的資源として今なお息づいています。
一方で、現在の京浜地域では高齢化が急速に進み、単身世帯や老々介護の増加、医療的ケアを必要とする方の在宅生活など、生活構造が多様化しています。利用者様の中には、複数の疾患を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく暮らしたいと願う方が多く見受けられます。そのため、医療と介護の連携が不可欠であり、在宅療養支援や服薬管理、リハビリテーション、社会参加支援など、多職種が一体となった包括的な支援体制が求められています。
また、利用者様の多くは、地域とのつながりを大切にしながら、人生の後半においても社会との関係を維持したいという意欲をお持ちです。かつて培った技能や知識を次世代に伝えたい、地域活動を通して誰かの役に立ちたいという思いを抱く方も少なくありません。こうした姿勢は、「高齢者=支援を受ける存在」という固定的なイメージを超え、「支援しながらも支え合う共生の担い手」としての新しい高齢者像を示しています。きてケアプランセンターでは、こうした利用者様の主体性を尊重し、その力を社会資源として活かすことを大切にしています。
さらに、近年は核家族化や地域コミュニティの希薄化により、社会的孤立や孤独感を訴える方も増えています。私たちは、生活支援の枠を超え、心のつながりを重視したケアを行うことを心がけています。単なる介護サービスの提供にとどまらず、「生きがい」「安心」「尊厳」を守ることを目的とした支援を展開し、精神的・社会的な安定の維持を図っています。とくに、認知症や精神的な不調を抱える方に対しては、心理的安全性を確保した関わりを重視し、本人の尊厳を損なうことのない対応を徹底しています。
また、外国籍の高齢者や、家族が遠方に住む方など、社会的背景の異なる利用者も増加傾向にあります。文化や言語の違いを理解し、それぞれの背景に寄り添った支援を行うことも、今後の地域包括ケアにおける重要な課題です。多文化共生社会の一員として、誰もが安心して暮らせる環境づくりを推進してまいります。
きてケアプランセンターでは、「わたしが私らしく」という理念のもと、利用者様一人ひとりの人生の歩みを尊重し、これまで培われた経験と知恵を未来へつなぐ支援を行っています。医療・介護・福祉の専門性を活かしながら、地域の中でその人らしい生活を継続できるよう伴走することが、私たちの使命です。私たちは、ご利用者様の「できる力」に焦点を当て、心身の回復と社会参加の機会を創出し、京浜地域における持続可能な共生社会の実現を目指しています。