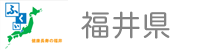2025年10月02日14:29 公表
有限会社 稲木ケア・サービス

サービスの内容に関する写真
-

当社は良質の介護サービスをご提供することで、地域の皆さまが安心して暮らせる社会づくりに貢献しております。 -

いつまでも自分らしく住み慣れた我が家でサービスを利用することができます。 -

事業所におきましては定期で研修を開催し、日々のスキルアップにつとめています。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
3/10人 -
最大受け入れ人数10人中、現在の受け入れ可能人数3人です。
(2025年09月05日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当社の介護士が利用者さまの住み慣れた家に訪問し、介護を必要とされる方の日常生活のお手伝いをします。ケアマネージャー、看護師など関係する職種の方々と連携し、介護いたします。サービス内容は大きく分けて二つ「身体介護」と「生活援助」とあり、お客様のご希望や必要性をもとに作成されたケアプランにより内容が決まります。ご利用者様やご家族の方々に喜んでいただけるサービスを提供したい。ホームヘルパーが訪問して真心の在宅介護を提供いたします。
サービスの質の向上に向けた取組
家政士認定試験の認定取得を通じて、家事全般のサービスの向上をはかっています。
オンライン動画研修サービスにて介護現場で役立つ知識・技術が学べながら、研修業務の負担を減らし、職員がスキルアップできる環境作りをすすめています。
- 取組に関係するホームページURL
-
-
わたしたちについて
https://www.inakicare.co.jp/about/ -
訪問介護サービス
https://www.inakicare.co.jp/service/nursing/
-
わたしたちについて
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
事業理念・ケア方針・人材育成方針の明確化
当事業所では、「Forever Youngこころ、みずみずしく」を事業理念の柱として掲げています。この理念を実現するために、以下のケア方針と人材育成方針を定めています。
1. ケア方針:パーソナルケアの実践
画一的なサービスではなく、ご利用者様一人ひとりの個性、生活習慣、価値観を深く理解した上で、その方に最適なケアを提供します。具体的には、以下の取り組みを行います。
個別ケア計画の徹底: ご利用者様やご家族との対話を重視し、ご本人の「したいこと」「大切にしたいこと」を反映させたケア計画を共同で作成・更新します。
多職種連携の強化: 医師、看護師、理学療法士など他職種と密に連携し、包括的な視点からご利用者様の生活をサポートします。
2. 人材育成方針:自律的な専門職の育成
私たちの理念とケア方針は、現場で働くスタッフ一人ひとりの成長によって支えられます。そのため、単なる技術指導に留まらない、自律した専門職を育成します。
「考える介護」の推進: マニュアル通りの動きだけでなく、「なぜこのケアが必要なのか」「どうすればもっと良くなるか」を常に考え、行動できる力を養います。
キャリアパスの提示: 初任者から管理者まで、個々の成長段階に応じた明確なキャリアパスを用意し、目標を持って働ける環境を整備します。■合同採用説明会・面接会の実施
複数の事業所が共同で説明会や面接会を開催することで、求職者は一度に多くの事業所の情報を得ることができ、事業所側も効率的に候補者と出会えます。これにより、多様な人材の確保につながります。訪問介護の仕事は、ご利用者様一人ひとりの生活に深く関わる仕事であり、その方の人生経験や個性、コミュニケーション能力が何よりも重要だと考えています。そのため、他産業からの転職者、子育てを終えられた主婦層の方々、これまでのキャリアを活かしたい中高年齢者の方など、幅広い層からのご応募を歓迎していますはい、承知いたしました。説明文の形式で再作成します。
■多様な人材の受け入れ
特定の経験や資格にこだわることなく、介護への熱意や人柄を重視した採用を行っています。異なる業界での経験や、これまでの人生で培ってきたスキルは、介護の現場で新たな価値を生み出す力になります。
■充実した教育・研修制度
・未経験の方でも安心してスタートできるよう、入社後のサポート体制を整えています。
・資格取得支援制度:働きながら「介護職員初任者研修」などの資格取得を目指せるよう、費用補助等で支援します。
・OJT(現任訓練):経験豊富な先輩スタッフがマンツーマンで丁寧に指導し、実践的なスキルを習得できます。
・継続的な研修:定期的な社内研修を通して、専門知識や技術の向上を継続的にサポートします。
■働きやすい環境づくり
年齢や家庭環境に関わらず、安心して長く働けるような職場環境を目指しています。個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方についても相談に応じます。
当事業所は、多様なバックグラウンドを持つ方々の力を結集し、質の高い介護サービスを提供していきたいと考えています。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度お問い合わせください。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当事業所では、職員一人ひとりの成長を応援し、専門性の向上を積極的に支援しています。働きながらスキルアップを目指せるよう、以下の研修受講支援制度を設けています。
1. 介護福祉士資格取得支援
国家資格である介護福祉士の取得を目指す職員を対象に、受験に必要な「実務者研修」の受講費用を補助します。
支援内容: 研修受講費用の全額または一部補助。勤務シフトの調整など、学習時間を確保するためのサポートも行います。
2. より専門的な介護技術の習得支援
特定の分野で専門性を高めたい職員に対して、外部研修の受講を支援します。
・ファーストステップ研修: 喀痰吸引、経管栄養などの医療的ケアを安全に実施するための研修です。
・喀痰吸引研修: 喀痰吸引の専門的な知識と技術を習得するための研修です。
・認知症ケア研修: 認知症の特性を理解し、その方に寄り添ったケアを提供するための研修です。
・サービス提供責任者研修: 訪問介護のサービス計画作成や、ヘルパーの指導・管理に必要な知識を習得するための研修です。
これらの支援制度を通じて、すべての職員が自信を持って専門職として活躍し、より質の高い介護サービスを提供できるよう、事業所全体でバックアップします。当事業所では、職員の専門性とモチベーションを高めるため、研修の受講状況と人事考課を密接に連動させています。
■研修受講の評価
職員が受講した研修(例:喀痰吸引、認知症ケアなど)は、個人の能力開発目標達成度として人事考課の評価項目に含めます。
これにより、自主的なスキルアップの努力を正当に評価します。
■スキルアップに応じた昇給・昇進
研修を通じて習得した新たな知識や技術を実際の業務で活かしているかを確認し、評価結果を昇給・昇進に反映させます。
これらの仕組みにより、職員は自身のキャリアパスを明確に描き、目標に向かって計画的にスキルアップに取り組むことができます。
また、事業所としても、質の高いサービス提供体制を維持・強化することが可能となります。定期的なキャリア面談の実施について
当事業所では、職員一人ひとりが安心してキャリアを築き、長く活躍できる環境を整えるため、上位者や担当者による定期的なキャリア面談の機会を設けています。
■目的
この面談は、単なる業務の進捗確認ではありません。職員自身のキャリアアップ、働き方、将来の目標について、率直に話し合うための貴重な時間です。
日々の業務で感じる課題や、描いているキャリアプランを共有し、事業所としてどのようにサポートできるかを共に考えます。
■面談の仕組み
定期的な実施:
半年に一度、所属長や人事担当者が個別に面談を実施します。これにより、変化する状況や職員の成長に合わせて、継続的にサポートを提供します。
■面談で話し合う内容
・スキルアップの進捗:
これまでに受講した研修の振り返りや、新しく挑戦したいことなどを確認します。
・将来のキャリアプラン:
「将来的には管理職になりたい」「特定のケア分野の専門家になりたい」といった、職員の目標を具体的に共有します。
・働き方の相談:
ライフスタイルの変化に合わせた勤務時間やシフトの調整など、柔軟な働き方について相談します。
これらの面談を通じて、私たちは職員の能力開発とキャリア形成をサポートし、個々の目標達成と事業所全体の成長を両立させていきたいと考えています。 - 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
子育てや家族の介護と仕事の両立を支援するため、就業規則に以下の制度を定めています。
■育児休業制度
子どもが3歳になるまで、育児のための休業を取得できます。また、子が小学校就学の始期に達するまで、期間を定めて短時間勤務や時差出勤も可能です。
■出生時育児休業制度(産後パパ育休)
子の出生後8週間以内に、最大4週間まで、2回に分割して休業を取得できます。
■子の看護休暇
小学校就学前の子どもがいる場合、病気やけがの看護、予防接種、健康診断のために、有給で休暇を取得できます。
■介護休暇
家族の介護が必要な場合、有給で休暇を取得できるほか、短時間勤務や時差出勤なども利用できます。当事業所では、職員一人ひとりのライフステージや事情に合わせて、仕事とプライベートを両立できるよう、柔軟な働き方を可能にする制度を設けています。
1. 職員の状況に応じた勤務シフトの導入
育児や家族の介護、自己啓発など、個々の事情に合わせて、勤務時間や日数を調整できるシフト制度を導入しています。
これにより、無理なく長く働き続けることができます。
2. 短時間正規職員制度の導入
「フルタイムでの勤務は難しいが、安定した雇用形態で働きたい」という声に応え、短時間で勤務する正規職員制度を設けています。
これにより、週の勤務日数を減らしたり、一日の勤務時間を短くしたりしても、正規職員として安定した待遇とキャリアを維持できます。
3. 非正規職員から正規職員への転換制度の整備
当事業所では、非正規職員として入職された方が、将来的に正規職員として活躍できる道を開いています。
・転換の機会
勤務経験や能力、本人の希望などを考慮し、年1回、正規職員への転換面談を実施します。
・キャリアパスの提示
非正規職員として働きながらも、正規職員と同様に研修やキャリアアップの機会を提供し、スムーズな転換をサポートします。
これらの制度を通じて、多様な働き方を受け入れ、誰もがやりがいを持って働ける職場環境を目指します。■計画的な取得の奨励
年間を通じて計画的に有給休暇を取得できるよう、シフト作成時に個々の希望を事前に確認する仕組みを導入しています。
これにより、職員が遠慮なく休暇を申請できる雰囲気を醸成します。
■管理者・リーダーの意識改革
管理職やリーダー層が率先して有給休暇を取得し、その重要性を理解することで、部下にも取得を促す模範となります。
定期的なミーティングで、有給休暇の取得状況を共有し、取得促進に向けた具体的な方策を話し合います。■業務の標準化と多能工化
特定の職員に業務が集中しないよう、マニュアル作成や情報共有を徹底し、業務を標準化します。
また、複数の業務をこなせるよう多能工化を進めることで、急な休みでも他の職員がスムーズにカバーできる体制を構築します。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
・定期的な面談
上長や同僚との定期的な面談を通じて、業務に関する悩みや不安を気軽に相談できる機会を設けます。腰痛に関する問診を含む健康診断を毎年実施し、早期発見と予防に努めます。
外部から理学療法士などの専門家を招き、正しい介助方法や体の使い方に関する研修を定期的に実施します。
福祉用具の積極的な活用: スライディングボードや腰の負担を低減するアシストスーツなど、
利用者の移動や移乗を補助する福祉用具を積極的に活用します。これにより、職員の身体的負担を大幅に軽減できます。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
-
-
・業務効率の向上
必要な書類や物品がすぐに取り出せるようになり、無駄な探し物がなくなります。
これにより、ケアに集中できる時間が増え、質の高いサービス提供につながります。
・安全性の確保
転倒や物品の落下など、職場での事故を未然に防ぎます。
特に訪問介護では、感染症対策としても重要です。
・快適な職場環境
常に清潔で整った環境は、職員の精神的な負担を軽減し、モチベーションの向上につながります。記録・報告様式はテンプレート化し、クラウドストレージにて共有して運用している。
介護記録システム導入済み。タブレット端末を用いて介護記録を登録、レセプトソフトとのシステム連携にて転記作業を削減。
介護ロボット(腰の負担を低減するアシストスーツ)、ビジネスチャットツール(Chatwork)の導入をしています。
管理者、企画室にて立案、実施をおこなっている。
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
当事業所では、職員間の円滑なコミュニケーションを促進し、一人ひとりの気づきを組織全体の改善につなげるため、以下の取り組みを行っています。
1. 定期的なミーティングの実施
・定例ミーティング
毎週または隔週で定期的に開催し、業務連絡や情報共有を行います。
この場では、利用者様の些細な変化や、ケアに関する気づきを自由に発言できる雰囲気づくりを重視しています。
・事例検討会
特定のケア事例について、多角的な視点から議論する場を設けます。
例えば、「なぜ利用者はこの行動をとったのか」「どのようなアプローチが最適か」などを深く掘り下げることで、
個々の気づきをチーム全体の知識として共有し、ケアの質の向上につなげます。
2. 個々の気づきを反映させる仕組み
ミーティングで共有された意見や気づきを、単なる情報交換で終わらせず、具体的な改善に結びつけるための仕組みを構築しています。
・「改善提案制度」の導入
ケア内容や勤務環境に関する小さな気づきやアイデアを、書面や専用のツールを通じて自由に提案できる制度です。
提案された内容は、責任者が定期的に確認し、実現可能性を検討します。
・フィードバックの徹底
提案されたアイデアについて、採用・不採用にかかわらず、必ず提案者へフィードバックを行います。
これにより、「自分の意見が聞いてもらえている」という実感を持ってもらい、さらなる改善意欲を引き出します。
これらの取り組みを通じて、職員一人ひとりが「言いたいことを言える」安心感のある職場を作り、現場の気づきを組織の成長力に変えていきます。1. オンライン動画研修の導入
時間や場所に縛られることなく、いつでもどこでも学べるオンライン動画研修サービスを導入しています。
目的: 介護保険制度の基本や法人の理念、利用者本位のケア方針について、繰り返し視聴して学ぶことができます。
効果: 業務の合間や自宅での学習が可能となり、職員一人ひとりのペースに合わせた学びをサポートします。
2. 定期的な集合研修の実施
オンラインでの学習に加え、全職員が顔を合わせて意見交換する集合研修を定期的に開催しています。
目的: 座学だけでなく、事例検討やグループワークを通じて、利用者様への具体的な対応について深く掘り下げて学びます。
効果: 職員同士がケアに対する考えを共有し、互いの気づきを活かすことで、チーム全体のケアの質を向上させます。
併設されているサービス
-
サービスの内容に関する動画へのリンク
保険外の利用料等に関する自由記述
夜間や泊り込みなど、ご家庭の状況に合わせて柔軟なサービスを提供いたします。病院への付き添いや、介護保険ではカバーされないような、よりきめ細やかなサポートも可能です。
当事業所の介護スタッフは、厚生労働大臣認定の家政士検定試験の資格を保持しており、専門的な知識と技術に基づいたサービスを提供いたします。ぜひご相談ください。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
人生100年時代を迎え、ライフスタイルの多様化や社会保障制度をめぐる環境の変化の中、稲木ケア・サービスは、新たな一歩を歩みだすべく事業理念「Forever Young こころみずみずしく」と掲げました。“Young”とは「若さ」という意味の他に「未熟」という意味もあります。だからこそ 「自分はまだ成長できる!」という「こころ」を育み、成長過程を楽しんでいきたいという思いが込められています。
「ありがとの」さりげないご利用者様の言葉に励まされ、癒されるひととき。私たちの仕事のやりがいや楽しさは、何気ない日常のなかにあります。
「ありがとう」の言葉一つひとつを励みに仲間と共に、昨日よりわずかでも小さなチャレンジを重ねていく。そんな日々の積み重ねが、やがては自分にとって、仲間にとって、地域を構成するひとりとして、大きなチカラとなり得ると信じています。わたしたちは皆さまの笑顔を原動力に、最良のサービスを提供することで成長を続け、 こころ豊かな地域社会に貢献します。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
■身体的・精神的特色
・高齢者:多くの利用者は高齢者で、加齢に伴う身体機能の低下や、認知症などの症状が見られます。
・疾病・障がい: 脳血管疾患の後遺症や難病、身体障がいなど、様々な疾病や障がいを抱える方がいます。
・ADL(日常生活動作): 食事や排泄、入浴など、ADLに何らかの介助が必要な方が利用します。
■生活環境・社会的背景
・在宅での生活: 病院や施設ではなく、住み慣れた自宅で生活を継続したいという強い希望を持つ方がほとんどです。
・家族構成: 一人暮らしの方や、老老介護、認認介護など、様々な家族構成の中で生活しています。
・地域とのつながり: 地域社会との交流が少ない方から、デイサービスなどを利用して積極的に交流を図っている方まで様々です。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働制を採用し、1ヶ月の所定労働時間は、1ヶ月を平均して週40時間以内とする。
賃金体系
基本給:日給月給制または時間給制
諸手当:役職手当、処遇改善手当※、通勤手当
※各処遇改善加算金を財源とし、法令や制度の改廃により変更する場合があります。
休暇制度の内容および取得状況
職員に対し、以下に従い年次有給休暇が付与されます。
勤務年数 6ヶ月 付与日数 10日、勤務年数 1年6ヶ月 付与日数 11日、勤務年数 2年6ヶ月 付与日数 12日、勤務年数 3年6ヶ月 付与日数 14日、勤務年数 4年6ヶ月 付与日数 16日、勤務年数 5年6ヶ月 付与日数 18日、勤務年数 6年6ヶ月以上 付与日数 20日
取得状況は82% 2025年9月1日 現在
福利厚生の状況
法定福利厚生:雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険
法定外福利厚生:確定拠出年金制度
離職率
(離職率):14.2%
(内訳):1年間の離職者数が5人、1年前の在籍者数が35人
(計算式):14.2% = 5人 ÷ 35人 ×100
2025年9月1日 現在
ケアの詳細(具体的な接し方等)
その他
事業所や周囲の外観
-

外観:事務所入口 -

右側の入り口がメインになります。 -

目印:京福バス上北野バス停を下車して東に進み、最初の小路を右折してください。(事務所まで150メートル)
ブログやSNSへのリンク
https://www.instagram.com/inakicare.co.jp/
https://www.facebook.com/inakicare.co.jp
https://page.line.me/dwq2038d