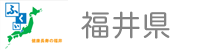2024年11月26日10:05 公表
すのうどろっぷhope
空き人数
-
空き数/定員
0/18人 -
定員18人中、現在の空き数0人です。
(2024年11月15日時点)
サービスの内容に関する自由記述
・玄関は開放し、利用者が自由に出入りできるよう配慮している。医療との連携で利用者の把握に努め、御家族と協力しながら情報の提供も行っている。
・地域と共に歩み、地域住民の健康な暮らしと地域の発展・共存の実現に努めている。具体的な取り組みとして、小学生向けの認知症劇の開催や認知症の方への声掛け方法などを公演し、地域に対する認知症への理解を深める活動や地域の公民館を活用した元気体操などを実施している。また、災害時の避難施設として行政と協定している。
サービスの質の向上に向けた取組
・認知症実践者研修の受講者を増やしながら、定期的なミーティングや訪問研修を実施しすべての職員が勉強できる機会を設けている。
・非正規雇用者に対しキャリアアップのための研修等を実施している。
・管理職や上司を対象に、女性の能力を伸ばし、活かすためのマネジメント研修を実施している。または外部研修に上司を参加させている。
・資格取得費用の助成を行っている。または、資格受験に利用できる休暇制度を導入している。
・従業員を家族の一員ととらえ、家族の健康と成長を見守り、多様な働き方を尊重することで働きやすさを追求している。具体的な取り組みとしては、お仕事相談員制度を設け、気軽に相談をしやすい人間関係の構築を図っている。また、育児休暇など各種休暇制度の充実や手厚い人員配置による職員の残業時間の削減、資格取得に向けた手厚い支援体制を整えている。本年度からは外国人実習生を受け入れ、言語サポートなどダイバーシティ経営を促進している。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
- 生産性向上のための業務改善の取組
-
- タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
併設されているサービス
共用型の認知症対応型通所介護を利用して頂き、除々に環境に慣れてから入居できるような組み立てを行っている。
保険外の利用料等に関する自由記述
地域行事に参加できる機会を増やすため、敬老会・運動会等や自治型デーサービスに参加している。博物館や菊人形等に外出した場合は、実際に要した料金を負担して頂く。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
・従業員の年齢層は、20歳から70歳と幅広く、家事業務が多いグループホームだが男性職員の数も多い。年齢層の高い職員がいる事で、畑作りや梅干し・干し柿・すこ作りといった調理を利用者の皆さんと一緒に行う事ができ、若い職員は他種類の家事を学ぶ事ができる。グループホームは男性職員は不向きと言われる事もあるが、利用者の重度化に伴い身体介護が増えたり、夜勤勤務の対応や休職者の臨時勤務の対応もスムーズなため、勤務に穴を空ける事がない。
・常勤職員と非常勤職員で構成されており常勤だけでは補えない部分を非常勤職員をプラスする事でカバーしている。
・非正規雇用から正規雇用へ転換できる制度を導入している。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
自立度の高い方がグループホーム入居の対象者とされてきたが、入居歴の長さや在宅生活が長く継続出来るようになった事で重度化されている。介護度が重くなっても入居を継続して頂けるよう職員の研修や育成に力を注ぎ、終末期まで対応出来るよう心がけている。グループホームの中でも家と同じように過ごし、自分の思いを職員に伝えられるような関係づくりに努めている。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
・所定外労働時間削減のため、ノー残業デーを実施している。
・帰りやすい職場風土に向け、管理職自身が勤務時間管理を徹底している。
・管理職の人事考課の項目に、部下の時間外労働の項目を組み入れている。
・短時間勤務制度、テレワーク等、柔軟な働き方を実現するための制度を実施している。
休暇制度の内容および取得状況
・育児・介護休業を取得しやすく、円滑に職場復帰できる制度を実施している。
・資格受験に利用できる休暇制度を導入している。
・育児中に発生する突発的な休暇についても、取得がしやすい職場の雰囲気づくりを行っている。
・男性の育児休暇取得を奨励している。
その他
《女性の応募・採用を増やすための取り組み》
・会社案内等で、社内で活躍している女性を紹介している。
・女性求職者を対象とした職場見学会や就職説明会を実施している。
・「ふくい女性活躍推進企業」のロゴマークを、名刺や封筒に印刷するなど、女性が働きやすい登録企業であることをPRしている。
《性別に関わらない男女公正な選考を行うための取り組み》
・面接担当者や採用権限のある者に女性を含め、選考の中立性を確保している。
《女性育成のための取り組み》
・経営者や人事担当者が、ダイバーシティ(多様性)マネジメントに関する研修を受講している。
・女性のキャリア形成に関する相談体制を整備している。
・仕事分担や異動において、女性にも男性と同じような機会が与えられる人事配置を行っている。
・非正規雇用者に対しキャリアアップのための研修等を実施している。
・非正規雇用から正規雇用へ転換できる制度を導入している。
・管理職や上司を対象に、女性の能力を伸ばし、活かすためのマネジメント研修を実施している。または外部研修に上司を参加させている。
・女性の意欲や能力を引き出すための面談を定期的に実施している。
・男女ともに公正な人事考課を行うための評価者研修を実施している。
・新たな知識や資格取得を目指す研修に女性を参加させている。
・資格取得費用の助成を行っている。または、資格受験に利用できる休暇制度を導入している。
・社内の会議や各種プロジェクトに、女性をメンバーとして参加させている。
・女性を中心としたプロジェクトチームをつくるなど、商品・サービスの企画・開発等に女性の意見を取り入れている。
《女性の登用について》
・管理職候補の女性をリストアップし、個別に育成している。
・子育て中の女性に応じたキャリアアップの仕組みを取り入れるなど、複数のキャリアコースを用意している。
・女性リーダーを育成するための研修を実施している。または県の「未来きらりプログラム」など社外のリーダー育成研修に女性を参加させている。