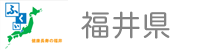2025年10月10日13:08 公表
小規模多機能型居宅介護支援事業所「わがや」
サービスの内容に関する写真
-

- -

- -

-
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
1/29人 -
最大受け入れ人数29人中、現在の受け入れ可能人数1人です。
(2025年09月25日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当事業所では、利用者様の生活の質を高めることを目的に、身体介護・生活援助・機能訓練・レクリエーションなどを組み合わせた多機能型のサービスを提供している。利用者様一人ひとりの心身の状態や生活歴を踏まえ、個別性を重視したケアを行っていることが特色である。
特に、日中の過ごし方においては「安心して、楽しく過ごせる時間づくり」を大切にしており、カラオケ・体操・季節の行事・手作業などを通じて、利用者様の笑顔と活力を引き出すよう努めている。利用者様から「一緒に歌いましょう」と職員が呼ばれる場面もあり、自然な交流が生まれることで、心の安定にもつながっている。
また、医師・看護師との連携のもと、服薬管理や健康状態の把握にも力を入れており、介護職員は利用者様に寄り添いながら「今、何を求めているか」を丁寧にくみ取り、日々のケアに反映している。
ご家族との連携も重視しており、送迎時のあいさつや日々の様子の報告を通じて、安心して任せていただける関係づくりを心がけている。利用者様・ご家族・職員が三位一体となって、穏やかで前向きな時間を共有できるよう、今後もサービスの質向上に努めていきたい。
サービスの質の向上に向けた取組
- 職員の内部・外部研修、勉強会への参加を推進
- 研修案内を回覧し、本人希望または管理者依頼により参加
- 研修後は記録を提出し、職員全員で内容を確認・共有
- 利用者様の状態変化や注意点について話し合い、必要に応じてケアの統一を図る
- 事故報告や業務改善があれば、ミーティング等で振り返りと対応を実施
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
「利用者・家族・職員の安心を守る運営」を経営理念とし、制度理解と現場感覚の両立を重視したケア方針を掲げている。職員一人ひとりの働きぶりを記録・評価し、勤務形態や配置に反映することで、役割と責任を明確化。処遇改善加算の算定に必要な記録整理や制度研修を通じて、職員の制度理解と実務力の向上を支援している。
入職後は、先輩職員による日々の実地支援を通じて業務習得を支援しており、特定のOJT体制があるわけではないが、毎日の業務そのものが指導の場となっている。現場では声かけや申し送りを通じて、自然なかたちで新人を支える関係性が少しずつ築かれている。
また、情報共有の効率化と記録整備の質向上を目的に、クラウド型情報共有ツール「リンク」を導入。セキュリティ面にも配慮しつつ、職員間の連携や記録の標準化を進めている。制度対応と現場運営の両立を支える仕組みづくりを通じて、職員が安心して働ける環境づくりに継続的に取り組んでいる。介護経験や資格の有無にこだわらず、他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者など、幅広い人材を受け入れている。採用時には、資格よりも人柄や柔軟性を重視し、現場の温度感を守る姿勢を評価している。なかには、この施設が介護経験の始まりとなる職員もおり、未経験者が安心して一歩を踏み出せる環境づくりに努めている。
新人職員への支援は、日々の業務の中での声かけや申し送り、記録の共有を通じて行っており、形式的な研修に頼らず、実地の中で育成を進めている。人員に余裕があるわけではない中でも、記録様式の整備や情報共有ツールの活用など、仕組みで支える育成体制を整えている。
職員同士が試行錯誤しながら支え合い、少しずつ関係性を築いてきた経緯があるからこそ、今では安心して働ける雰囲気が育まれている。制度に頼るだけでなく、現場の声を反映した柔軟な対応を通じて、人材の定着と育成を図っている。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当事業所では、働きながら資格取得や専門研修に取り組む職員に対して、勤務調整などの支援を行っている。
実務者研修や介護福祉士試験に向けて学習に集中できるよう、シフトの調整や休暇のまとめ取りを柔軟に対応しているほか、遠方での試験受験時には試験日前後の勤務も配慮している。職員の意欲を尊重し、無理なく学びを継続できるよう支援することで、専門性の向上と定着につなげている。
今後も、職員のキャリア形成を支える環境づくりを継続し、質の高いケアの提供に結びつけていきたい。職員が制度を理解し、日々の業務に活かせるよう、定期的に研修を行っている。研修では、処遇改善加算の算定に必要な記録の整え方を中心に、管理者が現場の実情に合わせて説明している。記録の正確さや申し送りの質を高めることで、職員が安心して業務に取り組めるよう支援している。
研修の受講状況は記録し、日々の業務の中で確認している。これらの内容は人事考課にも反映され、勤務形態や配置の見直しにつながることで、職員の成長と処遇が連動する仕組みを整えている。
評価は一律ではなく、職員一人ひとりの特性や業務内容に応じて柔軟に行っている。役割を明確にすることで、モチベーションの向上にもつながっている。
キャリア段位制度については、希望や業務内容に応じて活用を検討しており、制度の理解促進やキャリア形成の支援として位置づけている。今後はこの制度を通じて、職員の専門性や役割意識を高め、安定した人材定着につなげていきたいと考えている。
少人数体制ではあるが、身体拘束・虐待防止委員会、事故防止・防災対策委員会、感染症対策委員会など、制度上重要な委員会活動を責任持って継続している。委員会運営に直結する外部研修の受講や、内部研修の実施を通じて、職員の意識向上と制度理解を図っている。研修内容は委員会内で共有し、現場の記録整備や対応力の向上に活かしている。
感染症対策については、これまで何度も対応を経験しており、その都度マニュアルを見直している。マニュアルは情報量が多すぎると混乱するため、現場での実効性を高めるために要点を整理し、コンパクトに再構成したものを活用している。職員への周知徹底を図るうえで有効な手段として位置づけている。
BCP(業務継続計画)については、マニュアルを作成し、研修を通じて周知を図っている。感染症対策を中心に、自然災害などへの備えとして訓練も実施しているが、実際の災害時には職員のとっさの判断や機転が大きな力となった経験もあり、今後も現場の柔軟な対応力を大切にしていきたいと考えている。
研修・評価・配置・委員会活動を連動させながら、制度と現場の両立を意識した職場づくりに取り組んでいる。制度としては未整備であるが、先輩職員が新人指導にあたり、業務の流れやケアの基本を丁寧に伝えている。また、相談ごとは管理者や介護リーダーが日常的に対応しており、職員が安心して働ける環境づくりに努めている。今後は、こうした支援体制を制度的にも整理し、育成や定着支援につながる仕組みとして整備していきたい。
管理者が職員一人ひとりの勤務状況や業務の進め方を日々記録・評価し、配置や役割に反映する過程で、自然なかたちで相談の機会を設けている。特別な面談だけでなく、「ちょっといいですか?」と声をかけられる日常の対話を大切にし、勤務時間や働き方の希望、Wワークの相談などにも柔軟に対応している。業務の見直しや加算算定の根拠整理を通じて、制度への理解と実務力の向上を支えているほか、行事準備や現場運営では職員の意見を積極的に取り入れ、キャリア形成につながる関わりを日常的に築いている。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
子育てや家族の介護など、職員それぞれの生活背景に応じて、勤務調整や休業取得に柔軟に対応している。急な体調不良や家庭都合による欠勤時も、冷静な配置調整と記録対応により、職員が安心して休める体制を整えている。日々の声かけや相談を通じて、無理なく働き続けられる環境づくりを意識している。事業所内託児施設は未整備だが、今後の検討課題として位置づけており、職員の両立支援に向けた取り組みを少しずつ進めている。
職員の体調や家庭の事情に応じて、勤務シフトの調整や短時間勤務への変更に柔軟に対応している。お子さんの成長に合わせて、無理のない範囲で勤務時間や勤務日数を段階的に増やすなど、相談に応じた働き方を支援している。生活環境に応じて、遅出勤務を中心とした勤務形態や、パート職員による夜勤対応なども取り入れ、多様な働き方を推進している。業務の進め方や勤務状況を記録・評価し、職員の希望に応じて非正規職員から正規職員への転換も支援。急な欠勤やNG日にも冷静に対応できる配置体制を整え、職員が安心して働き続けられる環境づくりを意識している。
有給休暇の取得を促進するため、毎月〆切日を設けて希望休・有休の予定を記入してもらい、取得状況を定期的に確認している。取得が難しい月もあるが、相談に応じて柔軟に勤務調整を行い、可能な月には積極的に取得できるよう支援している。職員はお子さんの成長段階や学校行事などを事前に共有してくれるため、調整がしやすく、年配職員も「今はあなたたちの番よ」と協力的な姿勢で支えている。身近な管理者による声かけも行い、職員が気兼ねなく休暇を申請できる雰囲気づくりを大切にしている。
業務の属人化を防ぐため、職種ごとの専門性を尊重しつつ、業務内容を明確に区分している。毎月〆切日を設け、全職員に希望休や有給休暇の予定を記入してもらうことで、計画的な取得を支援。希望を出す職員もいれば、直接相談に来る職員もおり、個別事情にも柔軟に対応している。厨房職員は厨房内でシフトを調整し、有給休暇をうまく取得できる体制を整備。情報共有と複数担当制により、業務配分の偏りを防ぎ、誰かが休んでも業務が滞らない環境づくりを推進している。
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
業務内容や勤務形態、体調・家庭事情などに関する相談には、管理者が個別に対応し、職員が安心して働ける環境づくりを推進している。心身の不調や業務負担には、ねぎらいの言葉やお菓子・飲み物の差し入れ、夕方の「もぐもぐタイム」など、福利厚生的な視点から気持ちに寄り添う工夫をしている。施設内禁煙の方針のもと、喫煙者には希望制で短時間の喫煙時間を設けるなど、個別事情にも配慮。健康診断の日には、業務負担を軽減できるよう勤務調整を行い、必要に応じて半休を活用することで、職員が心身を整える時間を確保できるよう配慮している。利用者様へのケアや対応に関する相談が多く、記録をもとに職員と一緒に考える時間を大切にしている。制度理解や加算算定に関する相談には、記録の整え方や算定要件の説明を通じて、職員の不安や疑問に丁寧に対応している。
職員の健康保持・増進を重要な経営課題のひとつと捉え、勤務形態に関わらず、すべての職員が安心して働き続けられる環境づくりに取り組んでいる。特に、短時間勤務者や非常勤職員に対しても、常勤職員と同様に健康診断の受診機会を確保しており、勤務時間の長短にかかわらず、平等な健康管理体制を整えている。
また、正社員については、母体である病院にて受診した場合、医療費補助を受けることができる制度を設けている。これにより、常勤職員が自身の健康状態を把握しやすくなり、早期の体調管理や医療的対応につながっている。
ストレスチェックについては、制度上の定期実施は行っていないが、都度職員からの相談に応じて個別対応を行っている。職場内での人間関係や業務負担に関する悩みなどについて、管理者が直接話を聞き、必要に応じて勤務調整や業務内容の見直しを行うなど、精神的な健康にも配慮した体制を構築している。
また、体調不良時には、勤務調整や業務内容の変更、休養の促進など柔軟な対応を行っており、職員一人ひとりの状況に応じた個別相談に応じている。特に、感染症流行期や季節の変わり目など、体調を崩しやすい時期には、早期の声かけや体調確認を徹底し、無理のない勤務体制を整えるよう努めている。これにより、職員が安心して体調を整えながら働ける環境を維持している。
さらに、職員の心身のリフレッシュを目的として、休憩室を整備している。1階には更衣室とは別に畳敷きの部屋を用意しており、落ち着いた空間で休憩が取れるようになっている。また、2階のフロアも休憩スペースとして使用可能にしており、職員が分散して休憩を確保できるよう配慮している。
また、職種によっては在宅ワークも認めており、業務内容や家庭状況に応じて柔軟な働き方ができるよう配慮している。これにより、職員が無理なく業務に取り組める体制を整え、継続的な就労支援にもつなげている。
このように、職員の健康管理を単なる制度対応にとどめることなく、日々の業務の中で自然に根付かせることを目指している。職員が心身ともに健やかであることは、利用者へのサービスの質にも直結するとの認識のもと、今後も継続的な改善と取り組みを進めていく。介護職員の身体的負担を軽減するための取り組みとして、日々の業務を通じた介護技術の修得支援を行っている。OJTの体制は十分に整っているとは言えないが、現場そのものが学びの場となっており、先輩職員が実地で声かけや動作の工夫を伝えながら、無理のない介助方法を共有している。
腰痛予防については、利用者様の状態に応じて、一人体制から二人体制への介助方法の変更を行うなど、状況に応じた柔軟な対応を心がけている。必要な場面ではすぐに支援に入れるよう、職員同士で声をかけ合いながら、負担の偏りが生じないよう配慮している。また、正しい姿勢や福祉用具の活用について確認する機会も設けており、体調不良時には勤務調整や休養の促進にも対応している。
過去には、外部の腰痛予防トレーナーを招いて、職員向けに学びの場を提供したこともある。実技を交えた研修を通じて、身体の使い方や予防意識を高める機会となり、現場での声かけや介助方法の見直しにもつながっている。
令和5年1月に管理者へ就任して以降、業務運営の見直しを進めており、記録や報告の方法についても現場の実態に合わせて少しずつ整えてきた。制度への理解を深めるために、関連する法令や通知などを確認しながら、職員配置や加算に関する情報を整理しているところである。行政への報告や職員対応に必要な知識についても、研修や実務を通じて少しずつ身につけている段階であり、制度の変更や運用の見直しにも、できる範囲で柔軟に対応できるよう心がけている。
現在は、雇用管理責任者講習を受講中であり、雇用管理に関する法令や実務知識を体系的に学んでいるところである。さらに、当施設には顧問の社会保険労務士が関与しており、制度運用や労務管理に関する相談をいつでも行える体制を整えている。こうした支援を受けながら、職員が安心して働ける環境づくりに、少しずつ取り組んでいる管理者と事故防止・防災委員会が中心となり、事故やトラブルへの対応に関する委員会活動を行っている。マニュアルや記録の整備についても、現場で使いやすく、迷わず対応できるよう少しずつ見直している。
事故の記録に関しては、介護ソフトによる実記録と、紙ベースによる振り返り記録の二つの方法で行っている。介護ソフトでは事故の記録を正確に残すことを重視し、紙ベースでは事故後の対応や今後の対策、職員間の情報共有(勉強会など)を見据えた記録を行っている。これらの記録を通じて、状況の把握と再発防止につなげている。
施設内のトラブルについては、何か異変や「おかしいな」と感じた時点で、すぐに報告してもらえるよう日頃から声かけを行っている。火災警報や電気系統の点検は法令に基づいて実施しており、今年は一斉停電による点検も行った。設備の故障時には、業者への連絡先を把握し、可能な範囲で職員自身が対応できるよう、業者からレクチャーを受けるなどの工夫もしている。
職員間のトラブルについては、管理者が即時に対応することを大切にしており、状況に応じて冷静に話を聞き、必要な調整を行っている。また、利用者様の苦情や衝突についても、職員からの報告を徹底し、すぐに対応できるよう心がけている。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
厚生労働省の「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善に向けた取り組みを進めている。ICT導入支援事業の補助金を活用し、介護ソフトの導入や記録業務の効率化を図ってきた。
現在は、管理者と職員で構成する生産性向上委員会を立ち上げており、日々の業務の中で感じる課題や工夫を持ち寄りながら、現場に合った改善策を検討している。外部研修の活用などはこれからの課題としており、できるところから少しずつ整えている段階である。どの職種でも、どんな場面でも積極的に意見が出せるような雰囲気づくりを大切にしている。もとにあるのは、利用者様の安心・安楽を守ることと、ケアにあたる職員の負担を同時に考えたいという思いである。
そのため、日々の業務の中で自然と職員間の意見交換が生まれており、小さな気づきも共有されるようになっている。例えば、食事時間の繰り上げや、猛暑時の職員の服装についての柔軟な対応など、現場の声をもとに改善が進められている。冷房が苦手な利用者様への配慮と、暑さの中で働く職員の負担軽減の両立を目指し、職員からの意見をもとに工夫を重ねている。
記録や情報共有には、タブレット端末やインカムを活用しており、現場での記録入力やリアルタイムの連携がしやすくなっている。以前は職員一人あたり1日に30分~40分かかっていた記録業務が、現在では時間的に半分程度で済むようになっており、業務負担の軽減につながっている。
ICT導入後には、職員へのアンケートも実施しており、記録時間の変化や使いやすさ、業務への影響などについて意見を集めている。こうした声をもとに、現場の課題を見える形にしていく取り組みを進めている。
現在は、生産性向上委員会を立ち上げており、記録の振り返りや勉強会などを通じて、業務の流れや時間の使い方の見直しにもつなげている。職員一人ひとりが「働かせていただいている」という謙虚な姿勢を大切にし、心を整えることを業務の出発点と捉えている。毎朝の朝礼では、法人理念を365日欠かさず復唱することで、職員の意識統一と心の安定を図り、真摯な姿勢で業務に臨む土台を築いている。こうした「躾」の意識が、職場の秩序や規範を自然と支え、5S活動の根幹となっている。
清掃や衛生管理においては、担当者を定めたうえでチェック表を活用し、日々の清掃・物品管理を職員間で協力して実施。感染症対策にも配慮しながら、清潔で安全な環境を維持している。物品の配置や記録様式については、テンプレート化を進めることで整理・整頓を推進し、情報共有の効率化と業務の標準化を図っている。
記録業務に関しては、以前は手書きによる記録時間の増加が課題となっていたが、介護ソフトの導入により記録の整理・整頓が進み、職員の負担軽減と業務効率の向上につながっている。また、急な欠勤時にも冷静に対応できる体制を整備しており、職員が安心して働ける職場づくりを重視している。
5S活動は単なるルールや形式的な取り組みにとどまらず、職員の心構えと日常業務が連動することで、職場の秩序・清潔・働きやすさの両立を実現している。今後も、理念に基づいた職場環境の整備を継続し、利用者・職員双方にとって安心できる施設運営を目指していく。以前の記録方法を見直し、制度に沿った業務手順や記録のスタイルを整えている。加算算定の根拠資料や職員配置に関する情報は、管理者が一元的にデータで管理しており、職種や勤務形態ごとに色分けや項目整理を行うことで、誰が見ても分かりやすく、記録・報告の負担軽減にもつながっている。
記録業務に関しては、手書きによる記録時間の増加が課題となっていたが、介護ソフトの導入により記録の整理・整頓が進み、業務効率の改善と職員の負担軽減を実現している。さらに、インカムを導入することで、リアルタイムな記録と情報共有が可能となり、現場の連携力向上にも寄与している。
情報共有の手段としては、介護ソフト内の掲示板機能やクラウド型ツール「リンク」を活用。LINEは情報漏洩リスクを考慮し使用を中止し、現在は「リンク」にて業務連絡のアップロードや、各委員会グループ運用を行い、活動の相談や進捗報告などに活用している。これにより、職員間の情報伝達が円滑になり、安心して業務に集中できる環境づくりを推進している。
業務手順については、紙ベースの資料も併用し、ファイリングや写真の活用など、視覚的に分かりやすい工夫を施している。これは、ICTに抵抗のある職員にも配慮した取り組みであり、誰もが安心して業務を遂行できるよう、柔軟な運用を心がけている。こうした記録様式や情報共有の工夫を通じて、職員が本来のケア業務に専念できる体制を整えている令和5年度の県のICT導入支援事業補助金を活用し、介護ソフトを導入。令和6年2月から本格的な活用を開始し、1年が経過した現在では、職員が担当ごとに課題の抽出と対応策の検討を重ねたことで、運用が着実に定着してきている。
導入当初は操作面や記録方法などに戸惑いもあり、職員の負担が大きかったが、現在ではシステムに慣れ、施設独自の運用方法を確立。メーカーへのカスタマイズ依頼も行い、オリジナリティのある活用を進めている。導入にあたっては、リモート研修や施設内勉強会を実施し、職員の理解促進にも努めた。
介護ソフトの導入と並行して、タブレット端末やスマートフォン、インカムも導入。リアルタイムな記録と情報共有が可能となり、業務の効率化と連携力の向上に寄与している。情報共有には、介護ソフト内の掲示板機能やクラウド型ツール「リンク」を活用し、業務連絡や委員会活動の進捗報告などを円滑に行っている。
現在は、管理者・介護リーダー・ケアマネージャー・事務員の4名がICT活用推進チームとして連携し、介護ソフトの運用・改善に取り組んでいる。こうした取り組みが実現できているのは、職員一人ひとりの努力と、導入を決断してくださったオーナーの支援によるものであり、今後も継続的な改善を重ねていく方針である。見守り支援の一環としてセンサーマットを導入し、利用者の動きに応じた通知を受け取ることで、転倒予防や夜間の見守り体制の強化に活用している。介護ロボットや移乗・排泄支援機器などは未導入であるが、現場の状況やニーズに応じた導入可能性を検討しており、今後の課題として位置づけている。
また、職員間の連絡調整の迅速化を目的として、インカムやクラウド型ツール「リンク」を導入。インカムによりリアルタイムな記録と情報共有が可能となり、緊急時や申し送り時の対応力が向上している。「リンク」では、業務連絡のアップロードや委員会ごとのグループ運用を行い、活動の相談や進捗報告などを円滑に行っている。
さらに、介護ソフト内の掲示板機能も併用し、職員間の情報共有を多層的に支える体制を構築。ICT機器の活用により、職員が安心して業務に集中できる環境づくりを推進している。導入当初は操作面での課題もあったが、研修や勉強会を通じて理解を深め、現在では施設独自の運用方法を確立。職員の努力とオーナーの支援により、ICT機器の活用が定着している。介護職員が利用者へのケアに集中できるよう、業務内容の整理と役割分担に取り組んでいる。シフト作成にあたっては、締め日までに次月の希望休や勤務希望を各職員に記入してもらい、休みやすい環境づくりに配慮している。年末年始・お盆・GWなどの長期休暇時期には、早めに勤務希望を確認し、家庭事情に応じた調整を行っている。
働き方にも柔軟に対応しており、早出中心・遅出中心などの希望に加え、小さなお子様の成長や親の介護など、個々の状況に応じた勤務調整を実施。職員が安心して働ける体制を整えている。
業務面では、専門職と介護職の役割を時間帯や状況に応じて調整し、必要に応じて連携・協力しながら業務を遂行している。特に、ケアマネージャーと看護師による服薬管理や記録業務など、集中を要する業務については、静かな空間を確保するなど、環境面にも配慮している。
間接業務(食事準備・片付け・清掃・ベッドメイク・ゴミ捨て等)については、外部委託は行っていないが、職員間で協力体制を築き、業務の偏りが生じないよう調整している。イレギュラー対応時には、利用者にもご協力いただきながら、安心・安全を最優先に対応している。当事業所は、医療法人桂会丹尾医院を母体とする単独運営の事業所であるが、職場環境の改善に向けて、事業所内での協働体制と法人との連携を活かした取り組みを行っている。
委員会活動は少人数で構成されているが、感染症対策、事故防止・防災、身体拘束・虐待防止、生産性向上など、複数のテーマに分かれて取り組んでいる。時間の工夫をしながら業務を分担し、メンバーが集まってそれぞれの視点を持ち寄り、無理のない形で計画を立て、できることから少しずつ実践している。制度の要件も意識しつつ、現場の声を大切にした運営を心がけている。
指針や計画の策定においては、管理者・介護リーダー・ケアマネージャー・事務員が連携し、制度と現場の実情を両立させた内容づくりを行っている。内容によっては、必ずオーナーと相談のうえで方針を決定しており、現場の状況や管理者の負担にも配慮した意思決定を心がけている。
物品購入は事務担当者が中心となり、管理者に確認のもと必要物品のリスト化・価格比較・在庫管理を行い、無駄のない購入体制を整えている。ICTインフラについては、介護ソフト・クラウド型ツール・インカムなどを導入し、職員間の連携強化と業務効率化を図っている。
人事管理や福利厚生については、法人内での共通システムは導入していないが、施設専門の労務士と連携し、制度面での助言を受けながら職員の働きやすさを支えている。また、オーナーともすぐに相談できる体制を構築しており、管理者の負担や現場の状況にも配慮した意思決定が可能となっている。
今後も、事業所内での協働体制をさらに強化し、法人との連携も活かしながら、職員が安心して働ける職場づくりを継続していく方針である。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
職員同士のコミュニケーションを大切にし、日々の申し送りや定例ミーティングを通じて、利用者の状態や職員の気づきを共有し、勤務環境やケア内容の改善につなげている。
職員からの提案をきっかけに、通所利用者で外出の機会が少ない方に対して「少し気分転換にドライブへ行ってもよいですか?」との声が上がり、管理者が「いいですね」と応じた。さらに「マクドナルドのドライブスルーに寄ってもいいですか?」という提案もあり、利用者は施設に戻ってからシェイクとアップルパイを楽しく召し上がった。こうした職員の気づきと柔軟な対応が、利用者の笑顔や満足感につながっている。
また、職員からの声をもとに、シフト調整や業務分担の見直しを行うこともあり、家庭事情や体調への配慮を反映した柔軟な勤務体制づくりを心がけている。業務の見直しについては、実際に運用してみてうまくいかない場合もあり、その際は元の方法に戻したり、再度意見交換を行いながら現場に合った形を模索している。
利用者への対応についても、現場の気づきを記録や申し送りに反映し、チーム全体で統一した支援ができるよう努めている。こうした日々のコミュニケーションが、職員の安心感や定着にもつながり、働きやすい職場づくりの一助となっている。コロナ禍の影響で中止していた感謝祭を、昨年は利用者様のみで再開し、今年は参加可能なご家族様をお招きして開催した。職員が一所懸命企画を練り、ランチバイキングとスイーツバイキングをすべて手作りで提供。さらに、手作りのゲームコーナーも設け、利用者様とご家族が触れ合う時間をつくった。笑いあり涙ありの感謝祭となり、会場には温かな空気が満ちていた。
また、職員のご子息がボランティア活動の一環として参加され、介護業界が人手不足や職業イメージの課題を抱える中で、若い世代が現場に関心を持ち、実際に足を運んでくださったことは、職員にとって大きな励みとなった。日々のケアへの意欲向上にもつながっていると感じている。
こうした交流は、日々の業務の中で職員が自分の役割を改めて認識するきっかけとなり、地域とのつながりを実感することで、ケアへの前向きな気持ちが育まれている。
これからも、地域の方々とのふれあいを大切にしながら、「この仕事をしていてよかった」と思えるような、あたたかな現場づくりを続けていきたい。利用者本位のケアの実践に向けて、介護保険制度や法人の理念を職員が定期的に学ぶ機会を設けている。
法人の理念については、雇い入れ時に必ず説明を行い、職員がその考え方を理解したうえで業務に臨めるようにしている。また、毎朝の朝礼では全員で理念を復唱することで、日々のケアの中でその意識を保ち続けられるよう工夫している。
さらに、月例の全体会議では、制度改正の内容やケアの方向性について共有し、現場での実践と照らし合わせながら理解を深めている。職員同士で「利用者にとって何が最善か」を考える時間を持つことで、制度的な視点と現場の温度感を両立させる姿勢が育まれている。
今後も、制度や理念をただ学ぶだけでなく、日々のケアに活かせるような学びの場づくりを継続し、職員が自信を持って利用者本位のケアに向き合える環境を整えていきたい。日々のケアの中で生まれる好事例や、利用者様・ご家族からいただいた感謝の言葉を、職員間で積極的に共有するようにしている。
たとえば、ご家族様から「ケアの技術が高い」とお褒めいただいたり、送迎時のあいさつや声かけに対して「気持ちが明るくなった」と喜ばれることがある。こうした何気ない日常のやりとりでも、「当たり前のことを丁寧に続けているだけなのに、喜んでいただけた」と職員が感じる場面は多く、それらを月例の全体会議などで共有することで、職員同士の励みとなっている。
また、好事例だけでなく、改善が必要な場面についても隠さず共有し、振り返りと対策を行うことで、ケアの質向上につなげている。良いことも課題も分かち合う風土が、チームとしての信頼を育み、利用者本位のケアの実践を支えている。
今後も、現場での声や経験を大切にしながら、職員が前向きにケアに向き合える環境づくりを続けていきたい。
併設されているサービス
サービス付き高齢者向け住宅「わがや」
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所では、20代:0人、30代:1人、40代:6人、50代:12人、60代~:3人と、主に中堅からベテラン層の職員が中心となって業務にあたっている。介護現場での経験が豊富な職員が多く、利用者様への対応においても安定感と信頼感があり、安心できるケアの提供につながっている。
この施設が介護の仕事のはじまりとなった職員もおり、未経験からスタートした職員が、現場での支え合いや丁寧な指導を受けながら成長してきた経緯もある。年齢や経験に応じて得意分野を活かし合いながら、若手職員の柔軟な発想とベテラン職員の安定した対応が融合することで、現場全体の温かさと安心感につながっている。
職員それぞれが、子育て中、両親の介護、ご自身の体力面など、異なる生活背景を抱えながら勤務しており、互いの状況を理解し合いながら働き方を模索している。シフト調整や業務分担においても、無理なく継続できるよう配慮し合う風土が根づいている。
そして何より、職員一人ひとりが「心寧の優しさ」を持ち、利用者様を大切に思う気持ちをもって日々のケアにあたっている。主治医や看護師と連携しながら、介護従事者は利用者様に寄り添い、「今、何を求めているのか」を丁寧にくみ取り、対応する姿勢が根づいている。
今後も、職員の思いや強みを活かしながら、支え合える職場づくりと、利用者様に安心していただけるケアの提供を継続していきたい。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
当事業所の利用者様は90歳を超える方が多く、平均年齢は高めではあるが、皆様とてもお元気で、日々の生活を明るく過ごされている。特にカラオケが大好きな方が多く、レクリエーションの時間には大きな声で歌われる姿が見られ、職員も一緒に楽しませていただいている。
利用者様から「一緒に歌いましょう」と職員が呼ばれることもあり、歌を通じて自然な交流が生まれている。そのような場面では、職員も笑顔で応じ、利用者様との距離がぐっと縮まる。歌うこと・話すこと・笑うことを大切にされている利用者様が多く、周囲との関わりを楽しむ姿勢が強く感じられる。
こうした日常の中で、利用者様同士の会話や笑顔が自然に生まれ、施設全体が温かい雰囲気に包まれている。今後も、利用者様の「好きなこと」「得意なこと」を大切にしながら、心身の活力を引き出すケアを継続していきたい。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
正社員→早出6:30-15:30 日勤9:00-18:00 遅出10:00-19:00 夜勤17:00-翌5:00
パート→日勤勤務のみや短時間勤務にも対応しています。要相談
休暇制度の内容および取得状況
◎年次有給休暇:勤続年数6か月より10日付与 ◎特別休暇制度あり(血族の死亡または姻族の死亡の場合) ◎産前・産後休業制度 ◎生理休暇 ◎育児休業制度(育児休業規定あり) ◎介護休業(介護休業規定あり)※正社員対応のみの制度もあります。
福利厚生の状況
健康診断、インフルエンザ予防接種等を全職員を対象に行っています。
離職率
(離職率):9.5%
(内訳):2024年9月1日〜2025年8月31日の離職者数が2人、2024年9月1日時点の在籍者数が21人
(計算式):9.5% = 2人 ÷ 21人 × 100
(算定基準日):2024年9月1日時点の在籍者数を基準
※退職者のうち1名は70歳を超えており、計画的な延長勤務ののち円満に退職された。もう1名は定年前の退職であったが、ご家庭の事情によるもので、惜しまれながらの退職となった。新たな職員の入職にあたり申し送り期間を設け、業務に支障はなかった。
ケアの詳細(具体的な接し方等)
入浴形態(一般浴、機械浴)
一般浴(個浴)
その他
事業所や周囲の外観
-

近隣には「養浩館」、「お泉水公園」、「郷土歴史博物館」などがあります。 -

心安らぐ和モダンの空間でゆったりと過ごしていただけます。 -

-