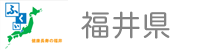2026年01月06日12:16 公表
リハビリデイサービス すきっぷ

サービスの内容に関する写真
-

当事業所では、8台の油圧式トレーニングマシンを使用し、各部位の筋力を効果的に鍛えています。ご利用者さま一人ひとりの筋力レベルや疼痛部位を考慮し、6段階の負荷を細かく調整することで、安全かつ最適なトレーニングを提供しています。これにより、筋力強化や可動域の拡大、骨格筋量の増加などを図り、日常生活動作の改善にもつなげています。
また、専門スタッフが丁寧にサポートすることで、初めての方でも安心して取り組んでいただけます。トレーニングは仲間と一緒に行うため、自然と笑顔や会話も生まれ、楽しみながら継続できるのも大きな魅力です。明るく清潔な環境の中で、体も心も元気に動かし、「いつまでも自分らしく暮らせる力」を育んでいただけるよう努めています。 -

当事業所の「筋トレ体操」では、ボールや棒、チューブなどの道具を活用し、楽しく体を動かしながら筋力の向上や維持を目指します。道具を用いることで運動の幅が広がり、無理なく続けられるのが特徴です。また、繰り返し行う動作がバランス感覚の向上や姿勢の安定にもつながり、転倒予防の効果も期待できます。
さらに、「脳トレ体操」では簡単な動作に頭を使う要素を加えることで、認知機能の低下を防ぎ、脳の活性化を図ります。体と心の両面を刺激することで、介護予防の効果を高め、日常生活の質の向上につなげています。
職員が丁寧にサポートしながら行うため、初めての方でも安心して参加できます。仲間と一緒に取り組むことで自然と笑顔が生まれ、交流の時間としても楽しんでいただけます。明るい雰囲気の中で「楽しく続けられる機能訓練」をご提供しています。 -

当事業所では、国家資格を有する柔道整復師が一人ひとりの身体の状態に合わせた施術を行っています。筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減するだけでなく、神経への圧迫を取り除くことでしびれや違和感の改善も期待できます。また、関節の柔軟性や可動域を広げることで、日常生活における動きがよりスムーズになり、転倒予防や姿勢改善にもつながります。
さらに、施術を通じて血液やリンパの流れを促進し、疲労の回復や冷えの改善にも効果的です。体が軽くなることで活動意欲が高まり、心身ともにリラックスした状態へ導きます。施術は利用者様との対話を大切にしながら丁寧に行いますので、安心してお受けいただけます。
「痛みを和らげたい」「動きをもっと楽にしたい」といったご希望に応えながら、健康で快適な生活のサポートをいたします。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
10/10人 -
最大受け入れ人数10人中、現在の受け入れ可能人数10人です。
(2025年09月16日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当事業所は、地域密着型通所介護として定員10名、午前と午後の1回短時間制で運営しており、食事や入浴サービスは行わず、機能訓練に特化したプログラムを提供している。主な対象者は要支援1・2および要介護1.2.3の方であり、自宅での生活を維持しながら機能向上を目指したいという利用者が多い。少人数制であることを活かし、利用者一人ひとりに合わせた個別的な支援を重視している点が特色である。
サービス内容の中心となるのは機能訓練である。マシントレーニング、リカンベントバイク、歩行訓練、電気療法、下肢への空気圧マッサージ機などを用い、身体機能の維持・改善を目指す。また、筋力トレーニング体操やストレッチを取り入れることで、日常生活動作の安定化に寄与している。プログラムは機能訓練指導員が通所介護計画書、個別機能訓練計画(要介護1以上)に基づき立案し、利用者の体調や生活状況を踏まえながら柔軟に調整している。
身体的な訓練に加えて、認知機能の維持・向上を目的とした脳トレ体操やゲームも実施している。計算問題や言語課題、カードやパズルを用いた取り組みなど、楽しみながら集中力を高められる工夫を取り入れている。これにより、単なる身体的リハビリにとどまらず、利用者の認知機能低下予防を目指している。
サービス提供時間が短いことから、メリハリのあるプログラム運営を心がけている。開始時には健康チェックを行い、体調に応じた無理のない計画を実施する。終了前にはおやつを提供し、利用者同士や職員との交流の時間を設けている。おやつの時間は単なる飲食の場ではなく、会話や笑顔が生まれることで心理的安定や仲間意識の醸成につながっている。
安全面についても重視しており、転倒防止のための声かけや環境整備、送迎時の確認体制を徹底している。感染症対策としては、手指消毒、換気、機器の清拭を定期的に実施し、利用者が安心して通える環境を整えている。また、職員は日々の記録を通じて利用者の変化を把握し、必要に応じて家族や関係機関と連携して支援を行っている。
当事業所のサービスは、単なる機能訓練の提供にとどまらず、「短時間で効率的に」「楽しく」「安心して」通えることを重視している。利用者は在宅生活を基本としながらも、定期的に専門的な訓練や交流を行うことで心身の活性化を図っている。今後も、利用者の声や外部評価の結果を取り入れながら、個別性をより重視したサービス提供を継続していきたい。
サービスの質の向上に向けた取組
当事業所では、地域密着型通所介護として「利用者が自宅での生活を継続しながら心身機能の維持・向上を図ること」を基本方針とし、サービスの質の向上に向けた様々な取り組みを行っている。特に、小規模かつ機能訓練特化型という特色を活かし、利用者一人ひとりの状態や生活背景を踏まえた個別的支援の充実を重視している。
まず、職員研修の充実を通じてサービスの質の向上を図っている。新任職員に対しては入職時研修を実施し、機能訓練補助や記録方法、感染症予防、事故防止など、業務に必要な基礎知識を習得できる体制を整えている。現任職員に対しては年間研修計画を策定し、感染症対策、虐待防止、認知症理解、制度改正など、実務に直結するテーマを中心に学習の機会を提供している。
次に、自己評価を定期的に実施し、その結果を改善につなげている。事業所として年1回自己評価を行い、サービス提供、記録、家族対応、職員研修などの観点から現状を確認している。
安全管理の面では、転倒防止や感染症対策を重点課題とし、チェックリストやマニュアルを活用した日常的な確認を徹底している。送迎時には確認を実施し、事業所内では機器や環境の安全点検を定期的に行っている。事故やヒヤリハットが発生した場合には速やかに記録・報告し、職員間で共有して再発防止に努めている。
さらに、サービスの質を高めるために「楽しみながら取り組める機能訓練」の工夫を行っている。脳トレゲームや体操など、利用者が前向きに参加できるようなプログラムを取り入れ、身体だけでなく精神面の活性化にもつなげている。利用者同士の交流や笑顔が自然に生まれることは、心身両面の健康維持に効果をもたらしている。
今後の課題としては、職員の専門性向上とICTの活用が挙げられる。外部研修の参加をさらに促進するとともに、電子記録システムの導入やデータ活用による効率化を進め、職員がより利用者に向き合える時間を確保することを目指している。
このように、当事業所は「研修」「評価」「安全管理」「プログラムの工夫」といった多方面から質の向上に取り組んでおり、今後も継続的な改善を重ねながら、利用者にとって安心で効果的なサービスを提供し続けていく。
- 取組に関係するホームページURL
-
-
リハビリデイサービスすきっぷ
https://aday-skip.com/skip.php
-
リハビリデイサービスすきっぷ
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
当事業所は「地域に根ざした温かいケアの提供」と「利用者一人ひとりの尊厳の保持」を経営理念の柱として掲げています。特に機能訓練特化型の地域密着型通所介護として、身体機能の維持・向上を目的としつつも、単なるリハビリにとどまらず、「その人らしい生活」を支えることを重視しています。そのために、ケア方針として「安全・安心」「尊重・共感」「継続的な成長」の三本柱を設定し、全従業員が共有できるよう研修を通じて繰り返し確認しています。
人材育成に関しては、「学び続ける職員が質の高いサービスを生む」という考え方を大切にしています。新任職員に対しては入職時研修を必ず行い、感染症防止、虐待防止、緊急時対応といった基礎知識の習得を図っています。また、現任職員に対しても年間研修計画に基づき、認知症ケア、身体拘束廃止、制度改正など多角的な学習機会を設けています。さらに研修後の振り返りや意見交換を重視し、「学んだことを現場でどう活かすか」を職員同士で共有する仕組みを取り入れています。
また、「働きやすさ」「やりがいの実感」という視点から、さまざまな取り組みを行っています。例えば、少人数の事業所である強みを活かし、日々のミーティングを通じて意見交換の場を設け、業務改善やケアの工夫を迅速に反映できるようにしています。
ケア方針を現場に浸透させるために当事業所では以下のような取り組みを行っています。
•マニュアル整備:感染症防止、認知症対応、非常災害対応などのマニュアルを作成し、全員が共通の手順で行動できる体制を確保。
•役割分担の明確化:送迎、機能訓練、レクリエーション、記録業務といった業務ごとに役割を整理した運営を徹底。
•チームケアの推進:リハビリ専門職や介護職員が連携し、利用者の目標達成をサポートする体制を強化。
また、利用者にとっての「安心感」や「信頼感」を高めるためには、まず職員自身が安心して働ける環境づくりが重要と考えています。
今後も法人全体としての経営理念を礎に、職員一人ひとりが安心して働き、誇りを持てる環境を整備し続けることを目標としています。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
当事業所では、地域密着型通所介護の特性上、利用者の送迎や移動介助、機能訓練補助など身体を使う業務が多く、職員の腰痛や疲労の蓄積が大きな課題となり得ます。また、小規模事業所ゆえに一人ひとりの役割が広く、業務上の心理的負担も軽視できません。こうした背景から、法人として「職員の健康を守ることが利用者への質の高いサービス提供につながる」という理念を掲げ、心身両面の健康管理に重点を置いた相談体制の整備と運用を行っています。
まず、身体的健康面では、腰痛予防を中心に取組みを強化しています。利用者介助時には「持ち上げない介助」「体に負担をかけにくい移動支援」の実践を徹底しています。特に送迎やマシントレーニングの補助など負担がかかりやすい場面では、職員同士が声を掛け合い、無理をせず協力して対応するよう意識づけています。
次に、心の健康管理として、メンタルヘルス面での相談体制を整備しています。小規模事業所では職員間の人間関係や業務上の悩みが個人に集中しやすく、早期に相談できる環境が重要です。そのため、管理者を中心に、業務負担、働き方、対人関係、家庭との両立、心身の不調など幅広いテーマで気軽に相談できる体制を構築しました。また、相談は秘密を守り、安心して声を上げられるよう配慮しています。
さらに、日常業務の中で相談や意見交換を自然に行えるようにするために、短時間のミーティングや振り返りを定期的に設定し、小さな不安や体調の変化に気づける場を大切にしています。特に腰痛や肩こりといった身体症状は本人が我慢しやすいため、早めに申告してもらうよう「無理せず相談」「早期対応」を合言葉にしています。
総合的に見て、当事業所が目指すのは「職員が安心して働き続けられる環境づくり」です。職員の健康が守られ、相談できる仕組みがあることで、サービスの安定提供につながります。今後も腰痛を含む身体面の予防と、メンタルヘルスを含めた心の支援の両立を重視し、法人全体で相談体制の充実を図ってまいります。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
当事業所では、厚生労働省が示す「介護サービス事業における生産性向上ガイドライン」を踏まえ、業務改善と働く環境の改善を両立させることを目標としています。その実現のために、法人内に「業務改善委員会」を設置し、継続的かつ組織的に生産性向上活動を進める体制を構築しています。
業務改善委員会は、管理者を委員長とし、介護職員、機能訓練指導員、生活指導員のメンバーで構成されています。少人数事業所である特性を活かし、職員一人ひとりの意見を反映しやすい仕組みを整えていることが特徴です。委員会は年1回の定例会議を基本とし、必要に応じて臨時会議を開催します。会議では、現場から寄せられた課題の整理、業務フローの見直しなどを行い、改善策を提案・決定しています。
これまでの取組として、送迎業務の効率化、記録業務の簡素化、利用者の機能訓練スケジュール調整方法の見直しなどを実施しました。例えば、送迎ルートの最適化を委員会で検討し、職員の負担軽減と利用者の待ち時間短縮を同時に実現しました。また、紙ベースの記録を整理し、入力フォーマットを統一することで、記録時間を短縮しながら情報共有の精度を向上させることができました。
さらに、委員会活動は業務改善にとどまらず、職員の意識改革や働きやすい職場環境づくりにもつながっています。議論の中で「小さな改善でも積み重ねれば大きな成果になる」という共通理解が醸成され、職員が自ら提案し行動する風土が育っています。このプロセスを通じて、職員が自らの業務を見直し、効率化やケアの質の向上に結びつける姿勢を持つようになりました。
当事業所は今後も業務改善委員会を中心とした取組を継続し、生産性向上を通じて職員の負担軽減とサービスの質の向上を両立させてまいります。当事業所では、生産性向上のための具体的な方策として、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を導入し、日常業務において継続的に実践しています。5Sは単なる環境整備にとどまらず、職員一人ひとりの意識改革を促し、業務効率の向上と利用者サービスの質の向上につながる重要な取組です。
まず「整理」では、日常業務で使用する機材や備品の必要・不要を見極め、使用頻度の低いものは保管場所を移動するか廃棄し、必要なもののみを手元に残すようにしています。これにより、探し物の時間を削減し、作業効率の向上が実現しています。
次に「整頓」では、利用頻度の高い備品を定位置に配置し、誰が使ってもすぐに取り出せるよう工夫しています。職員全員が共通認識を持って扱えるようにすることにより、業務の流れがスムーズになり、利用者様を待たせる時間も短縮されています。
「清掃」については、毎日の終業時に担当を決め、マシントレーニング機器やリカンベントバイク、マッサージ機などを清拭・点検する仕組みを取り入れています。これにより、清潔さを保つだけでなく、機器の不具合を早期に発見でき、事故防止にもつながっています。
さらに「清潔」は、整理・整頓・清掃を継続して行うことで自然と保たれます。利用者様やご家族にとっても「安心して利用できる施設」という信頼感につながっており、事業所の評価向上にも寄与しています。
最後に「躾」では、5Sのルールを守ることを全職員の基本姿勢として位置づけています。職員全員が共通の価値観を持ち、5Sを日常の行動習慣として根付かせることで、組織全体の一体感が強まっています。
これらの取組を通じて、事業所内の作業環境は大きく改善され、職員の業務負担が軽減されるだけでなく、利用者様に対するサービス提供の質も高まります。今後も5S活動を継続し、職員が働きやすく、利用者様が安心して過ごせる環境づくりを進めてまいります。当事業所では、生産性の向上と業務の効率化を目的として、介護ソフトを導入し、職員それぞれが所有するパソコンを活用して情報を共有しています。導入したソフトは日々のケア記録そのものには使用していませんが、利用者様の機能訓練計画や介護計画の入力、利用日管理、個人情報の整理といった業務に重点的に活用されています。これにより、業務の正確性や効率性が高まり、職員の事務負担を軽減する効果を上げています。
現在は介護ソフトに直接入力することで、データが一元的に管理され、必要な情報を迅速に検索・閲覧できるようになっています。これにより、計画の作成や更新作業の効率が上がり、利用者様一人ひとりに適したサービス提供の基盤が整いました。
特に、機能訓練特化型事業所としては、機能訓練計画の管理が非常に重要です。ソフトに計画を入力しておくことで、過去の履歴や進捗状況を簡単に確認でき、評価や見直しの際に有効に活用できます。また、介護計画との連携も可能であるため、全体的なサービス方針と日常の訓練方針を統一的に把握でき、職員間での認識のズレを防ぐことができます。
さらに、利用日の入力や個人情報の管理についても、利用状況の確認や請求事務との連携がスムーズになり、事務処理にかかる時間を削減できています。これにより、職員は利用者様への直接支援により多くの時間を割くことが可能となり、サービスの質向上にもつながっています。
また、全職員が共通のシステムにアクセスできるため、業務の透明性が高まり、誰が見ても同じ情報を確認できる体制が確立されています。情報共有の円滑化は、職員間のコミュニケーションの質を高め、結果としてチームケアの推進にも寄与しています。
今後も、介護ソフトの機能をさらに活用し、入力業務や情報管理の効率を高めることで、利用者様への質の高いサービス提供と職員の働きやすい環境づくりを両立させてまいります。当事業所では、介護職員が利用者様へのケアにより集中できる環境を整備するために、業務内容の明確化と役割分担の工夫に取り組んでいます。特に当所は定員10名、午前・午後に分けた1回短時間の機能訓練特化型デイサービスであり、食事や入浴のサービスは提供していませんが、おやつの提供や訓練機器の準備、清掃、ゴミ捨てなどの間接業務は日常的に発生します。これらを効率的に行うことで、限られた人員(職員4名)であっても、利用者様に対して安全かつ質の高いサービスを提供できる体制づくりを進めています。
当事業所では介護助手や外注による間接業務の分担は行っていないため、職員自身が責任をもって業務を遂行しています。そのため、業務の偏りや過重負担が生じないように、シフトや担当割を工夫し、各職員が自分の役割を理解して行動できるようにしています。例えば、日々の開始前ミーティングで確認し、全員が共通認識をもって業務を進められるようにしています。これにより、作業の重複や抜け漏れを防ぎ、限られた時間内で効率的に業務を進めることができます。
また、間接業務を単なる付随作業として扱うのではなく、利用者様の安全や快適さを守るための大切なケアの一部として位置づけています。例えば、訓練機器の準備や清掃は事故防止や感染症対策に直結し、環境を清潔に保つことは利用者様の満足度向上にもつながります。このように、間接業務の意味づけを職員間で共有することで、誰もが積極的に取り組む姿勢を持てるようにしています。
さらに、業務分担を工夫することで、利用者様との関わりを増やす時間を確保しています。例えば、おやつの準備を行う職員以外はその時間を機能訓練の見守りや声かけに専念するなど、状況に応じて役割を切り替えながら、効率的かつ柔軟に対応しています。このようにして、間接業務と直接ケアのバランスを調整し、全体のサービスの質を高めることを意識しています。
今後も、職員の意見交換を通じて業務の流れを見直し、役割分担のさらなる改善を進めていきます。小規模事業所だからこそ可能な柔軟な対応力を活かし、利用者様に寄り添った支援を行いながら、職員が働きやすくやりがいを持てる環境づくりを目指してまいります。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
当事業所では、介護職員一人ひとりがやりがいを持って働ける環境をつくるために、職場内のコミュニケーションを重視し、定期的なミーティングを実施しています。小規模事業所であるからこそ、日々の業務の中で気づいたことや感じた課題を迅速に共有し、改善に反映させていくことが可能です。こうした仕組みは、職員の声を大切にし、現場の主体性を尊重する文化を育てるとともに、ケアの質を高める取り組みにつながっています。
ミーティングでは、まず利用者様の状況や機能訓練の進捗、体調の変化などを共有することで、全員が共通理解を持ち、ケアの一貫性を保てるようにしています。特に機能訓練特化型デイサービスでは、日々の小さな変化を見逃さず、早期に対応することが求められるため、職員間の情報共有が非常に重要です。さらに、業務の進め方や環境整備に関する意見交換も行っています。
また、職員が気づいたことを自由に発言できる雰囲気づくりを意識しており、上下関係にとらわれず意見を交換できる環境を整えています。これが、職員一人ひとりが「自分の意見が事業所運営やケアの質に反映されている」と実感できるきっかけとなり、働きがいや自己成長の実感につながっています。特に小規模の強みとして、提案から実行までのスピードが速く、改善の成果を職員全員で共有できる点は大きな魅力です。
さらに、定期ミーティングだけでなく、日常的な声かけや短時間の打ち合わせも大切にしています。例えば、送迎前後や休憩時間に「今日は利用者様の歩行状態が少し不安定だった」などの小さな気づきを共有することが、事故防止やより良いケアの実現につながっています。この積み重ねが、安心して働ける職場環境を形作り、職員のモチベーション維持にも大きく寄与しています。
今後も、ミーティングを単なる情報伝達の場にとどめるのではなく、職員全員が参加しやすく、意見を反映しやすい場とすることで、現場の知恵や工夫を活かした改善を積極的に進めてまいります。そして、職員が互いに支え合い、成長を実感できる職場づくりを通して、利用者様へのサービスの質向上につなげていきます。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
当事業所では、介護保険の給付対象となるサービスのほかに、保険外(自費)でのご利用が必要となる場合があります。これらは利用者様にとって必要不可欠なものではなく、あくまで希望に基づきご利用いただくもの、または介護保険制度上カバーされない部分に限定して設定しています。
基本的にご利用料金の大部分は介護保険による給付対象ですが、おやつ代や日常生活における消耗品代(紙パンツ、個別に使用する衛生用品等)については実費をご負担いただいております。おやつ代は1回あたり100円とし、嚥下機能に配慮した内容を提供しております。消耗品については、ご家庭から持参いただくことも可能です。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所の従業員は、常勤・非常勤を含め計4名で構成されており、それぞれが異なる専門性や経験を活かしながら、利用者一人ひとりの心身機能の維持・向上に取り組んでいる。
介護職員は利用者の日常生活動作の支援だけでなく、マシントレーニングや歩行訓練などの機能訓練補助を積極的に行っており、安全に配慮しながら声かけや励ましを行うことで、利用者のモチベーション向上にも貢献している。また、利用者の健康管理やバイタルチェック、電気療法の実施を担い、医療的視点からの助言や対応に強みを発揮している。体調の変化をいち早く察知し、他職種との連携を図りながら迅速に対応する姿勢は、利用者や家族からの信頼を高めている。
機能訓練指導員は国家資格を取得した2人の柔道整復師が担い、個別機能訓練計画の作成や運動プログラムの立案を行い、リハビリテーションの専門的知見を活かして利用者に適切な運動を提供している。リカンベントバイクや筋トレ体操、脳トレ体操など多彩なメニューを導入し、利用者が「楽しみながら続けられる機能訓練」を実現している点が特色である。また、柔道整復師だからこそできる手技療法や電気療法、温熱療法等により、疼痛軽減や身体のケアも行っている。
従業員全員に共通しているのは、利用者やご家族との丁寧なコミュニケーションを大切にしていることである。送迎時の声かけや利用中の小さな気配り、またおやつの時間における交流を通して、利用者の安心感や居心地の良さを提供できている。加えて、脳トレやレクリエーションでは、職員それぞれの個性を活かしながら工夫を凝らし、利用者同士の交流を促進している。
今後は、従業員の専門性をさらに高めるために外部研修や資格取得の機会を積極的に取り入れ、より質の高いサービス提供につなげていく予定である。小規模であることを強みに、職員一人ひとりが多様な役割を担い、チームとして柔軟かつきめ細やかな対応ができる点が、当事業所の従業員の特色である。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
当事業所の利用者は定員10名と少人数制であり、地域に根ざしたサービスを求める方が多い。利用者の年齢層は概ね70歳代から90歳代にかけて広がっており、比較的自立度の高い方から軽度の介護が必要な方まで幅広く在籍している。介護度としては要支援1・2および要介護1・2の方が中心で、重度介護を必要とする方は少ない。
利用目的の大きな特徴として、「自宅での生活を継続するための機能訓練」を重視している点が挙げられる。特に、歩行の安定や下肢筋力の維持を目的に、マシントレーニングやリカンベントバイクを希望する方が多い。また、脳の活性化を目的とした脳トレやゲーム、体操に積極的に取り組む方も多く、身体だけでなく認知機能の維持・向上を意識して通所している傾向が見られる。
さらに、当事業所の特色として「入浴・食事の提供がなく、短時間(3時間)で集中した訓練を行う」ことから、長時間の滞在を望まず、効率的に訓練や交流を行いたいというニーズを持つ利用者が多い。送迎付きで気軽に通える利便性もあり、通所を生活リズムの一部として定着させている方が多い。
利用者同士の関係性については、少人数であることからお互いに顔なじみになりやすく、和やかな雰囲気の中で活動に参加している点が特徴である。脳トレゲームや体操の時間には自然と笑顔や会話が生まれ、利用者同士が励まし合う姿が見られる。また、おやつの時間は交流の場として機能し、利用者同士のつながりを深める貴重な機会となっている。
家族のニーズとしては、「できる限り在宅で生活を続けたい」という本人の希望を尊重しつつ、機能維持のための専門的支援を求める声が多い。リハビリや運動を重視しながらも、見守りや交流を通じて安心感を得られることに価値を感じている傾向がある。
全体的に、当事業所の利用者は「積極的に活動に取り組む姿勢」が強いことが特徴であり、自ら目標を持ち、それに向かって努力する方が多い。その一方で、加齢に伴う体力や認知機能の低下を不安に感じている方も多く、職員による励ましや適切なサポートが大きな支えとなっている。
今後は、利用者の多様なニーズに応じて個別性をさらに重視した支援を行い、利用者一人ひとりが「自分らしく生活を続けられる」よう取り組んでいくことが必要である。
ケアの詳細(具体的な接し方等)
利用者の一日の流れ
当事業所での1日は、心身の健康維持と生活の質の向上を目的に、計画的かつ楽しく過ごしていただけるよう工夫されています。
まず、ご自宅まで職員が送迎に伺い、安全に事業所までお越しいただきます。到着後はリラックスできる雰囲気の中で、血圧・脈拍・体温などのバイタルチェックを実施し、その日の体調を確認します。ご利用者様一人ひとりの状態を把握することで、安全で無理のないプログラム進行につなげています。
準備が整いましたら、全員での筋トレ・脳トレ体操をスタートします。ボールやチューブなどを用いた運動を行い、楽しみながら筋力向上や認知機能の維持を図ります。さらに、皆さんでゲームを行い、体と頭を同時に活性化させていきます。
その後は、全員でマシントレーニング(1種目8レップ×3セット)を一斉に実施します。油圧式マシンを使い、安全に負荷を調整しながら、各部位の筋肉をしっかりと鍛えます。ここまでは全員一緒に取り組み、一体感を感じながら楽しく運動に励みます。
続いては、各プログラムを順番に巡っていくサーキット形式に移ります。電気療法で筋肉の緊張をほぐしたり、柔道整復師による施術(マッサージ)で血流や関節可動域を改善したりします。また、空気圧による脚のマッサージ器「ドクターメドマー」を用いて下肢のむくみを解消し、血液循環を促します。
さらに、個別の目的に応じてマシントレーニングやリカンベントバイク(10~15分)で有酸素運動を行い、歩行訓練やストレッチで身体機能を整えます。ご利用者様は自分のペースで次々と進めていき、無理なく楽しみながら様々な訓練を体験していただけます。
運動後は、お茶の時間で一息つき、お菓子を食べながら和やかな雰囲気の中で団らんを楽しんでいただきます。おしゃべりや交流の場は心のリフレッシュにもつながり、利用者様同士のつながりを深める大切な時間となっています。
最後は職員が再び送迎を行い、安全にご自宅までお送りします。一日の活動を通じて、「体を動かす楽しさ」「仲間と過ごす喜び」を実感していただき、心身ともに充実した時間を過ごしていただけるよう支援しています。
送迎に関する情報(地区、曜日、個別対応(寝たきり等)の可否等)
当事業所では、ご利用者様が安心して通所いただけるよう、送迎サービスを提供しております。福井市街地を中心に設定しており、地域密着型サービスとして、身近な地域の皆様にご利用いただきやすい体制を整えています。対象となる具体的な地区については、ご利用開始前にご相談いただき、道路事情や所要時間を考慮したうえで柔軟に対応いたします。
送迎の曜日については、月曜日から金曜日までの週5日運行しております。(土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は休業)。利用者様の通所日程に合わせて時間を調整し、午前・午後それぞれの部で送迎を行っています。1回あたりの定員を踏まえ、効率的かつ安全に移動できるよう、事前にルートを計画し運行しています。
送迎対応にあたっては、安全第一を基本とし、乗車時の介助や降車時のサポートも丁寧に行います。玄関先まで職員が伺い、必要に応じて室内までお迎えに上がることも可能です。歩行が不安定な方には手を添えて付き添い、車への乗降も無理なく行っていただけるようサポートいたします。車内ではシートベルトの着用確認や体調の変化に注意を払い、安心して移動いただけるよう努めています。
また、当事業所は機能訓練特化型であるため、送迎対象者は基本的にご自身で座位保持が可能な方、車いすでの短距離移動が可能な方を想定しています。寝たきりの方や医療的ケアを常時必要とされる方の送迎は難しい場合がございますが、軽度の介助があれば通所可能な方についてはご相談のうえ、可能な範囲で対応させていただきます。
さらに、送迎に関する特別なご要望についても、事前にご相談いただければ可能な範囲で柔軟に対応いたします。ご利用者様とご家族様の生活スタイルに寄り添い、安心してご利用いただける送迎サービスを目指しています。
個別の機能訓練の詳細
当事業所では、利用者様一人ひとりの身体状況や生活背景、リハビリの目標に応じた個別機能訓練を実施しています。ご利用開始時には、柔道整復師などの専門職員が機能評価を行い、筋力・関節可動域・バランス能力・歩行能力・認知機能などを確認します。その結果をもとに個別機能訓練計画書を作成し、利用者様やご家族様と共有したうえで、安全かつ効果的な訓練を進めてまいります。
訓練の内容は大きく分けて、筋力強化訓練、関節可動域訓練、バランス訓練、歩行訓練、持久力向上訓練、ストレッチ、疼痛緩和のための補助療法などです。たとえば、油圧式トレーニングマシンを使用した下肢・上肢筋力強化では、負荷を6段階で調整し、無理なく継続できるプログラムを提供しています。リカンベントバイクによる有酸素運動では、10〜15分の運動で下肢筋力と心肺機能を高め、生活動作の持久力を養います。
また、歩行訓練では平行棒や歩行補助具を使用し、転倒予防や歩行の安定性を重視した訓練を行います。バランス訓練や立ち座り動作の反復練習を取り入れることで、日常生活に直結した機能回復を図ります。さらに、柔道整復師によるマッサージや電気療法、空気圧マッサージ機(ドクターメドマー)を組み合わせることで、疲労回復や循環促進、疼痛緩和を支援しています。
機能訓練においては「楽しさ」や「達成感」を大切にし、ボールやチューブを使った体操、脳トレを組み合わせたプログラムも導入しています。単なる身体機能の回復にとどまらず、認知機能の維持・向上や社会的交流の促進につながるよう工夫しています。
訓練はすべて個々の身体状況に応じて調整され、無理なく継続できるよう配慮しています。これにより、利用者様が「自分らしい生活を続けられること」を目標に、心身両面から支援していきます。