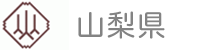2025年09月16日08:02 公表
訪問介護事業所ほの字
| 介護サービスの種類 |
訪問介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目25-14 IKビル205号
|
| 連絡先 |
Tel:055-288-8662/Fax:055-288-8663
|
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
38/38人 -
最大受け入れ人数38人中、現在の受け入れ可能人数38人です。
(2025年09月14日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当事業所では、身体介護(入浴・排泄・食事・服薬支援等)や生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理等)を中心に、利用者の状態や生活状況に応じた柔軟な支援を提供しています。現在は住居系施設への訪問を中心としてサービスを展開していますが、今後は体制を整備し、地域のご自宅への訪問介護にも積極的に取り組んでいく方針です。
サービス開始前には徹底的なアセスメント評価を行い、心身の状態・生活歴・生活環境を多角的に把握した上で、その方に最も適したケアプランを立案しています。これにより、単一的なサービスではなく、利用者一人ひとりに応じたオーダーメイドの支援を実現しています。
また、透析や在宅酸素など医療的ケアを必要とする方については訪問看護事業所と連携し、生活保護受給者や身寄りのない方については地域包括支援センターや行政と協力するなど、多職種・多機関連携による包括的な支援体制を整えています。定期的な職員ミーティングを通じて情報共有を徹底し、既存の介護事業所にありがちな問題を排除しながら、利用者にとって安心・安全で継続可能な在宅生活の実現を目指しています。
サービスの質の向上に向けた取組
当事業所では、利用者に対して常に質の高い介護サービスを提供できるよう、Mission・Vision・Value(MVV)の設定とその実行に向けた取組を進めています。単なるスローガンにとどめず、日常業務や職員研修の中で繰り返し確認・実践することで、組織全体に理念を浸透させています。
職員研修においては、GIFT理論を基盤とし、体軸特性に基づいた自己や他者の特性理解を深めることで、介護技術や対人スキルを高めることを重視しています。また、外部の研修事業者による各種研修を積極的に活用し、継続的に最新の知識や技術を学べる体制を整えています。
さらに、事業所内のミーティングでは、職員全員が参画意識を持てるよう工夫しており、相手に対して肯定的な評価を伝える「賞賛スキル」の向上にも取り組んでいます。加えて、平時からコミュニケーション技術を磨くことを目的に、ディベートやグループワークを積極的に導入し、意見交換を通じた理解の深化とチーム力の強化を図っています。
これらの取組みを通じて、当事業所は単に介護技術を提供するだけでなく、理念に基づき、人材が自律的に成長し続ける文化を持った組織づくりを推進しています。これが最終的に、利用者一人ひとりへの質の高いサービス提供につながると考えています。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
【経営理念・ケア方針】
現在、法人全体としてのMission・Vision・Value(MVV)については、策定過程にあり、法人内の全職員が参画する研修や意見交換を通じて、組織として共有できる理念体系を醸成している段階である。このプロセス自体を重視し、現場の声を反映させながら、利用者・家族・地域にとって真に有益な方向性を打ち出すことを目指している。
理念の具体化に向け、研修や会議の中で「利用者本位」「尊厳の保持」「地域との共生」といったキーワードを軸に討議を重ねている。これにより、単に経営層が定めた理念を一方的に示すのではなく、職員一人ひとりが主体的に関わることで、理念が現場に根付く仕組みを構築している。
【人材育成方針】
当法人は、人材を最も重要な資源と位置付け、継続的な研修と育成の仕組みに力を入れている。人材育成研修においては、各職員の特性や強みを把握し、それに応じた個別的アプローチを行うことを基本方針としている。
例えば、観察力に優れた職員にはアセスメント業務を、コミュニケーション能力の高い職員には利用者や家族対応を重点的に担ってもらうなど、役職に縛られない柔軟な役割分担を実現する。このような仕組みにより、全ての職員が自らの力を発揮できる環境を整え、働きがいのある職場づくりにつなげている。
【施策・仕組み】
〇研修制度の充実
新人導入研修、介護技術研修、医療知識研修、管理職研修などを体系的に整備し、段階に応じた学びの機会を提供する。さらに、法人全体研修におい ては理念や方針の共有を行い、職員間で共通の価値観を形成する。
キャリア形成支援
資格取得の費用補助や定期的なキャリア面談を通じて、長期的なキャリア形成を支援している。また、評価制度においては「成果」だけでなく「成長の過程」を重視し、挑戦を後押しする仕組みを導入している。
〇理念浸透と実践の仕組み
定例会議や委員会活動の中で理念や育成方針の進捗を確認し、日常業務へ反映する仕組みを設けている。現場で生じた意見や課題は速やかに法人全体にフィードバックされ、必要に応じて施策を改善している。これにより、理念の策定・共有・実践が循環する仕組みを継続的に運用している。-
当法人は、介護事業を安定的かつ継続的に運営するためには、多様な人材の確保と育成が不可欠であると認識している。そのため、経験者や有資格者のみに依存せず、他産業からの転職者や主婦層、中高年齢者、新卒者を含む幅広い層からの採用を積極的に行ってきた。
【採用実績】
2022~2023年には、製造業や販売業など他産業から転職した無資格者の採用実績がある。入職後は介護補助業務からスタートし、基礎を学びながら徐々に現場に慣れていく仕組みを整えた。その後、法人が費用を補助する形で介護職員初任者研修を受講し、資格取得後には実践的な介護業務に携わるという段階的キャリアパスを実現している。この制度により、介護業界未経験者でも安心して業務を開始し、成長できる環境を整えている。
また、当法人では**新卒高校生の採用を毎年継続的に行っており、無資格から介護の道に進む若年層の育成にも力を注いでいる。**学校との連携を通じて業界の魅力を発信するとともに、入職後はマンツーマンでの指導や先輩職員によるサポート体制を整備し、早期離職の防止と成長促進に努めている。
【資格取得支援制度】
無資格で入職した職員に対しては、資格取得のための費用補助や受講調整を法人が行っている。特に介護職員初任者研修、実務者研修など、キャリア形成に直結する資格取得を支援する体制を整え、**「無資格者⇒介護補助⇒資格取得⇒実践介護」**という明確なステップを設けている。この仕組みにより、入職時のハードルを下げると同時に、長期的な成長と定着を促進している。
【幅広い採用の方針】
当法人は今後も、介護人材不足という業界の実情を踏まえ、無資格者や他産業からの転職者を積極的に採用する方針を堅持していく。経験や資格の有無にとらわれず、「介護に携わりたい」「人の役に立ちたい」という意欲を重視し、多様な背景を持つ人材を受け入れることが、法人の持続可能な成長と地域への貢献につながると考えている。
さらに、主婦層や中高年齢者に対しても、柔軟な勤務形態や短時間勤務制度を活用することで参画を促進し、ライフスタイルに応じた働き方を支援している。これにより、ライフステージに応じた働き方を実現し、働きやすい職場環境の整備を進めている。
このように当法人では、無資格者や異業種からの転職者、新卒者など、経験や資格の有無を問わず幅広い人材を積極的に採用し、研修や資格取得支援を通じて専門職として育成している。今後もこの方針を継続・発展させ、地域社会に必要とされる人材を育み、質の高い介護サービスの提供を実現していく。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
【働きながら資格取得や専門研修を目指す者への支援体制について】
当法人は、職員が働きながら介護福祉士等の国家資格や、より専門性の高い介護技術を習得できるよう、費用面・学習面・環境面での包括的な支援体制を整備している。これにより、職員が自己のキャリア形成を図るとともに、組織全体として介護サービスの質を高めていくことを目的としている。
【資格取得支援】
介護福祉士資格を目指す職員に対しては、実務者研修の受講費用を全額法人負担としている。経済的負担を軽減することで受講意欲を高め、働きながらでも資格取得を無理なく目指すことができる。また勤務調整にも配慮し、学習と現場業務の両立を可能とする体制を整えている。
【専門研修への取り組み】
介護現場では、専門性とリーダーシップを備えた人材の育成が求められている。当法人では、ユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引研修、認知症ケア研修、サービス提供責任者研修などの**専門研修については、これまで参加受講歴がないが、法人として積極的に受講を促している。具体的には外部研修事業者と連携し、研修情報の提供、受講スケジュール調整、受講費用の法人負担などを通じて、職員が安心して挑戦できる環境を整えている。今後は中堅職員向けのマネジメント研修も含め、体系的に受講機会を拡充し、管理職・リーダー層の育成につなげていく。
【GIFT理論を取り入れた人材育成研修】
当法人の人材育成研修の中核には、GIFT理論を導入している。これは自己と相手の特性理解を基盤とし、対人スキル・マネジメントスキルを体系的に高めることを目的とするものである。継続研修を通じて、自らの強みや弱みを認識し、相手に応じた柔軟なコミュニケーションや指導を行える人材を育成している。この理論の活用により、単なる知識や技術習得にとどまらず、チーム全体の協働性やリーダーシップを強化する仕組みを構築している。
【外部事業者との連携と継続的アプローチ】
研修支援にあたっては、外部の研修事業者との継続的な協力関係を構築している。これにより、最新の介護技術や制度改正への対応を速やかに反映できる体制を整えている。法人内研修と外部研修を組み合わせることで、学習内容を現場に落とし込み、実効性の高い育成を実現している。
【管理職・リーダー層の擁立と育成メソッドの確立】
最終的には、これらの取り組みを通じて、専門性とマネジメント力を兼ね備えた管理職・リーダー層の擁立を目指している。資格取得支援、専門研修の促進、GIFT理論を基盤とする人材育成研修を一体的に運用することで、当法人独自の人材育成メソッドの確立を進めている。このメソッドは「学び → 実践 → 振り返り → 成長」というサイクルを促し、法人全体の持続的な成長とサービスの質向上に直結するものである。
このように当法人は、資格取得費用全額負担、外部研修事業者との連携、GIFT理論を活用した人材育成研修など多角的な施策を通じて、働きながら学び続けられる環境を整備している。今後も専門研修への参加を積極的に促し、組織全体の人材力強化に努めることで、利用者にとってより質の高い介護サービスを提供していく。当事業所では、職員が安心して働き続けられるよう、キャリアアップや働き方に関する定期的な相談の機会を確保しています。年1回以上、管理者や担当責任者が中心となり、職員一人ひとりと面談を実施しています。
面談では、日々の業務での悩みや負担の確認に加え、資格取得や研修受講の希望、将来的なキャリアビジョンなどを丁寧に聞き取り、個々の状況に応じた助言や支援策を提示しています。必要に応じて、勤務形態の調整や役割分担の見直しも行い、ワークライフバランスを考慮した働き方を支援しています。
また、キャリア面談を通じて得られた意見や課題は、法人全体の人材育成方針や職場環境改善の取組に反映させています。こうしたサイクルにより、職員が将来を見据えて前向きに働ける環境づくりを実現しています。
今後も定期的な相談体制を維持・強化し、職員一人ひとりが自らの成長を実感できる事業所運営を目指していきます。 - 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
当事業所では、職員が子育てや家族の介護等と仕事を両立できるよう、柔軟な働き方の制度整備に取り組んでいます。過去には短時間正社員制度を導入し、フルタイム勤務が難しい職員でも正規雇用として安定的に働ける仕組みを構築しました。現在も、育児や家庭の事情に応じて勤務時間を調整できる時短制度を導入しており、ライフステージに合わせた多様な働き方を実現しています。
これらの制度は、特に子育て世代や家族介護を担う職員にとって、仕事を継続する大きな支えとなっています。また、職員一人ひとりの事情に応じた勤務調整を行うことで、離職防止や人材定着にもつながっています。
現時点では事業所内託児施設の整備には至っていませんが、今後も地域資源の活用や法人内での体制検討を進め、子育てや介護を担う職員が安心して長く働ける環境づくりを強化していきます。当事業所では、職員一人ひとりの事情に配慮し、多様な働き方を選択できる環境整備を進めています。勤務シフトの作成にあたっては、子育てや家族介護、通院等の個別事情を丁寧に確認し、可能な限り柔軟に対応する体制を整えています。
雇用形態においては、過去に短時間正規職員制度を導入し、フルタイム勤務が難しい職員であっても正社員として安定的に働き続けられる仕組みを構築しました。また、非正規職員から正規職員への転換制度を運用し、これまでに複数の職員が正社員へ移行しています。その際には、国の助成金を活用することで、転換時の賃金アップや処遇改善にも取り組み、職員が安心してキャリアを築けるよう努めています。
こうした制度や取組により、職員はライフステージに応じた働き方を選びながら、長期的なキャリア形成を目指すことが可能となっています。今後も制度の継続的な見直しを行い、働きやすさとキャリアア当事業所では、職員が安心して働き続けられる環境づくりの一環として、有給休暇の取得を促進する取り組みを進めている。特に、現場上長からの積極的な呼びかけや声かけを通じて、職員が休暇を取りやすい雰囲気づくりに努めている。
実際の取得状況としては、付与された有休をほぼ使い切る職員もいれば、あまり取得していない職員もおり、個々の取得状況には差が見られる。これは、本人の意識や働き方のスタイルに加えて、その時々の人員配置や業務の繁閑にも左右される側面がある。当事業所としては、こうした状況を踏まえつつ、一律の取得目標を定めるのではなく、まずは上司からの働きかけを通じて「取得しやすい雰囲気」を醸成することを大切にしている。
また、有休の取得が特定の職員に偏ることなく、できる限り均等に機会を得られるよう、会議やミーティングの場でも随時状況を共有している。人員の充足状況によっては調整が必要となる場面もあるが、可能な範囲で柔軟に対応することで、休暇取得が「遠慮なく申し出られるもの」となるよう工夫している。
今後も、個々のライフスタイルや現場状況に応じた柔軟な対応を続けながら、職員が有給休暇を取得しやすい職場づくりを目指していく。当事業所では、有給休暇の取得を促進するために、業務の属人化や業務配分の偏りを解消する取組を進めている。その中で特に効果を発揮しているのが、訪問先である有料老人ホームとの間で導入している情報共有ツール「LINE WORKS」の活用である。
このツールを通じて、利用者の状況や現場の進捗がタイムリーに共有される仕組みを構築している。これにより、有給休暇の取得や急な欠勤が発生した場合であっても、現場職員や関係者が即座に状況を把握でき、スムーズな引き継ぎや業務調整が可能となっている。結果として、特定の担当者に依存することなく業務を回すことができ、休暇取得に伴う不安を軽減する体制が整っている。
また、LINE WORKSは法人全体の情報共有ツールとしても稼働しており、業務依頼や進捗管理などにタスク機能を積極的に活用している。タスクを個人ではなくチーム単位で共有する仕組みとすることで、業務が一人に集中することを防ぎ、属人化の解消につながっている。これにより、誰かが休んでも他のメンバーが補完できる体制を整え、計画的な有給休暇の取得を後押ししている。
以上のように、当事業所では訪問先施設との情報共有と法人内でのタスク管理をICTツールで一体的に運用し、属人化を防ぐ仕組みを整えている。これにより、有休取得を含む働きやすい職場環境づくりと、利用者に対するサービスの安定的な提供の両立を図っている。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
当事業所では、職員が安心して業務に従事できるよう、日常的な相談や健康面でのサポートを受けやすい体制づくりを重視している。
日常の業務に関しては、管理者が利用者モニタリング等で訪問先へ出向いた際に、職員から業務上の相談や意見を受ける機会が常態化している。これにより、形式的な窓口を設けなくても、自然な風土として相談が行われる環境が構築されている。現場で感じた悩みや課題をその場で管理者に伝えることができるため、対応が迅速であり、職員にとっても相談しやすい雰囲気が根付いている。
さらに、令和7年7月よりクリニックがグループ法人として加わったことにより、健康面のサポート体制も拡充している。具体的には、予防接種や体調不良時の診察・処方を優先的に受けられるほか、疼痛時のペイン外来受診やブロック注射といった専門的な診療もスムーズに利用できる体制を整えている。これにより、職員が日常業務で抱える身体的な不調についても安心して相談でき、早期対応や適切な治療につなげることが可能となっている。
以上のように、当事業所では業務相談の機会を日常業務に組み込み、加えてグループ内医療機関との連携により健康面の支援体制を整えることで、職員が働きやすく安心できる環境を構築している。今後もこうした取り組みを継続し、相談しやすい風土づくりと健康管理の両面から職員を支援していく。事業所では、職員が心身ともに健康で安心して働ける環境を整備することを重要な取り組みのひとつと位置づけ、健康診断や休憩環境の整備などの健康管理対策を実施している。
訪問系サービスを主軸としながらも、当事業所の訪問先は介護施設であることから、現場で働く職員が適切に休憩を取れるよう、介護施設内の休憩室整備に特に力を入れている。利用者へのケアに集中するためには、職員自身の休養が不可欠であるとの考えから、清潔かつ落ち着いて過ごせる休憩環境を確保するよう努めている。
また、健康診断については常勤者のみならず、過去には勤務実績を踏まえて短時間勤務の職員にも受診の機会を付与した実績がある。これは、勤務時間の長短にかかわらず、全ての職員の健康保持が重要であるという法人方針に基づいたものである。短時間勤務労働者に対しても健康診断を提供することで、健康状態を適切に把握し、必要に応じて早期の対応が可能となる体制を整えている。
以上のように、当事業所では訪問先介護施設における休憩室の整備や、短時間勤務者を含めた健康診断の機会付与を通じて、職員が健康を維持しながら長く働ける環境を整えている。今後も継続的に健康管理対策を進め、利用者への安定したサービス提供と職員の働きやすさの両立を図っていく。当事業所では、介護職員の身体的負担を軽減し、長期的に安心して働き続けられる職場環境を整えることを目的として、介護技術や腰痛対策に関する研修体制を整備している。
具体的な取組として、法人全体の方針として「体軸理論(GIFT理論)」を取り入れ、骨格特性に応じた介助方法を学ぶ研修を導入している。この研修は外部の専門研修事業者によって実施しており、少なくとも年1回は必ず開催するようにしている。職員が自身の体の使い方を理解したうえで利用者への介助にあたることで、腰痛などの身体的負担を予防し、安全で効率的なケアの提供につながっている。
現在は、管理職および現場リーダー層を中心に研修を重点的に受講させ、現場全体へ浸透させるための土壌づくりを進めている。まず中核となる層が理論と技術を習得し、実際の業務の中で具体的に指導や助言ができる体制を築くことで、段階的に職員全体への波及効果を高めることを狙いとしている。
また、当該研修を担当している外部研修事業者は、他の法人内研修も担っているため、その際にも骨格特性や身体の使い方に触れてもらうよう依頼している。これにより、年1回の専門研修にとどまらず、日常的な学びや他研修の場を通じても意識付けを行い、少しずつ全体の意識に浸透していく工夫をしている。
これらの取組を通じて、介護職員が「無理をせず、合理的に体を守りながら介助を行う」という姿勢を自然に持てるようにすることを目指している。結果として、職員の腰痛や身体的負担を予防するだけでなく、介助そのものの質や安全性の向上にもつながっている。
以上のように、当事業所では体軸理論を基盤とした研修を継続的に取り入れ、まずは管理職・リーダー層から現場全体へ浸透させる形で、介護職員の身体的負担を軽減する仕組みづくりを進めている。今後も外部研修事業者との連携を強化しながら、全職員が安心して働ける環境づくりを推進していく。当事業所では、事故やトラブル発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を整えることを重要な課題と捉え、対応マニュアルの整備および組織的な仕組みの構築を行っている。
まず、事故・トラブル対応に関するマニュアルについてはすでに作成済であり、全職員に周知している。マニュアルでは、発生時の初動対応や関係部署・上長への報告体制など、基本的な流れを明確に定めており、職員が迷わずに行動できる指針となっている。
また、日々の業務におけるインシデントやアクシデントについては、「インシデント・アクシデント報告対策立案書」を活用して記録・分析を行っている。発生事象を「レベル0~レベル3a」「レベル3b~レベル5」と段階的に区分し、事象の重大性に応じて対応や再発防止策を検討する仕組みを整えている。軽微なものは現場で改善を図り、重大なケースについては法人全体で検討する体制とすることで、リスクマネジメントを段階的かつ体系的に行っている。
さらに、法的リスクに備えるため、法人として顧問弁護士を擁立しており、必要に応じて専門的な助言や対応を仰げる体制を整備している。あわせて、損害保険にも加入しており、万が一の事態にも迅速に補償や対応ができる仕組みを構築している。これにより、利用者や家族に対しても安心していただける体制となっている。
報告体制については、まず現場職員が上長へ報告し、次に法人へと情報が上がる流れを標準化している。これにより、現場での初動対応と並行して法人全体での状況把握と対策が可能となり、迅速な意思決定につながっている。
以上のように、当事業所では事故・トラブル対応のマニュアル作成、インシデント・アクシデントの段階的管理、顧問弁護士や損害保険によるリスク備え、そして報告の標準化を通じて、事故発生時にも一貫した対応が可能となる体制を整えている。これらの取組により、職員が安心して業務に取り組める環境を整備するとともに、利用者と家族に対しても安全と信頼を提供できるよう努めている。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
当事業所では、厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動を計画的かつ継続的に推進する体制を構築している。まず基本の枠組みとして、事業所全体での定例ミーティングを位置づけ、管理職と現場職員が双方向に意見を出し合うことで業務導線の改善に関する協議を行っている。単なる情報伝達に留まらず、現場の具体的な課題を直接管理職へ伝え、また管理職からも業務改善の方向性を示すことで、実効性のある改善策を共同で策定できる体制を確立している。
さらに、協議で決定した改善内容については、ミーティング直後から1か月間を実施期間とし、全職員が日常業務において試行する。その後、1か月後の事業所全体ミーティングにおいて実施結果を再評価し、効果や課題を明確にしたうえで再度修正を加えるというサイクルを基本としている。この「協議 → 実施 → 評価 → 再協議」の流れを組織的に定着させることで、改善活動を単発的な取り組みに終わらせず、継続的な成長につなげている。
平時の業務においては、管理職が担うリテール書類作成や定型業務に対して生成AIを積極的に導入している。これにより、資料作成や文書整備にかかる時間を削減し、管理職が現場職員のサポートや組織運営の戦略的業務に注力できる体制を整えている。生成AIの活用は、業務効率化だけでなく、内容の均質化やエラー防止にも寄与しており、結果として現場全体の負担軽減や品質向上に資している。
また、外部研修事業者の関与も積極的に取り入れている。定期的な研修はもちろんのこと、必要に応じて外部専門家を招き、現場の状況を直接確認してもらったうえで、第三者の視点からの介入や助言を受ける機会を設けている。この取り組みにより、内部では気づきにくい課題を浮き彫りにし、改善策の幅を広げることができている。外部の知見を組織に取り込むことで、事業所独自の発展にとどまらず、介護業界全体の標準に照らした持続的な改善を志向している。
以上のように、当事業所は管理職と現場の協働による改善協議、計画的な実施・評価のサイクル、生成AIをはじめとしたICTの活用、さらに外部研修事業者からの助言を組み合わせることで、厚生労働省の「生産性向上ガイドライン」に沿った実効性の高い業務改善活動を展開している。これらの取り組みは、職員一人ひとりの業務負担を軽減するとともに、サービス品質の向上につながり、ひいては利用者とその家族に対する安心と満足度の向上を実現している。今後も継続的な改善の文化を根付かせ、持続可能な介護サービスの提供に努めていく。当事業所では、厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、「現場の課題の見える化」を重要な経営課題として位置づけ、日常的かつ中長期的な視点から取組を進めている。
まず、平時の取組としては、事業所全体の定例ミーティングを活用し、現場職員からの課題の表出、管理職やサービス提供責任者を交えた協議、実行、修正という一連のプロセスを継続的に運用している。この場では、日常業務で生じた小さな気づきや非効率な業務の流れについても積極的に取り上げ、実行可能な改善策を速やかに試行し、次回のミーティングで効果検証を行うというサイクルを重視している。この「表出 → 協議 → 実行 → 修正」の仕組みにより、現場レベルの課題が放置されず、改善につながる実効性の高い活動として根付いている。
一方で、中・長期的な視点では、業務全体の時間配分や効率性をより俯瞰的に把握する取組を行っている。具体的には、サービス提供責任者を中心に、現場職員の大枠の業務ごとの所要時間をExcelへ落とし込み、各業務にどの程度の時間が割かれているかを暫定的に表出している。これにより、日々の業務感覚に基づく主観的な把握だけでなく、データに基づいた課題抽出が可能となり、業務の優先順位付けや効率化の方向性を明確にできるようになった。時間の可視化を通じて、どの業務に過度の負担が集中しているのか、どの工程を見直すことで全体の効率を高められるのかといった具体的な議論が可能となっている。
さらに、この中・長期的な取組においては、特に管理者やサービス提供責任者の業務効率化とスリム化を重点課題としている。管理職層は日常的に多岐にわたる業務を担っており、その業務が現場の円滑な運営に直結している一方で、過度な負担や煩雑な事務作業が業務改善の妨げとなるケースも少なくない。そのため、業務の棚卸しを行い、優先順位をつけて整理することで、本来注力すべき業務とそうでない業務を明確にし、業務分担の見直しやシステムの導入による効率化を進めている。Excelを活用した時間分析は、その議論の基盤資料となり、数値に裏付けられた改善施策を検討する助けとなっている。
これらの活動を通じて、当事業所では「短期的な改善」と「中長期的な効率化」の両面から現場の課題を見える化し、持続的な改善体制を整えている。短期的には、全体ミーティングで現場課題をタイムリーに表出し、迅速に実行・修正を繰り返すことで、利用者サービスの質と職員の働きやすさを確保している。中長期的には、業務時間のデータ化と効率化の検討を通じて、将来的な人材確保や働き方改革にもつながる基盤を築いている。
このように、日常業務に即した課題改善とデータに基づく構造的な業務見直しを組み合わせることで、現場の課題を継続的に見える化し、改善に結びつける仕組みを確立している。今後も、業務の効率化と質の高いサービス提供の両立を目指し、職員全体で取り組みを深化させていく。当事業所では、厚生労働省が推進する「生産性向上ガイドライン」の趣旨を踏まえ、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を職場環境整備の基本方針として取り入れている。その実践にあたり、当事業所の業務特性である「住居系介護への訪問サービス」という現場の特性を重視し、利用者の生活環境に直結する形で5Sを実行していることが大きな特徴である。
まず、訪問介護における5S活動の中心は「訪問先住居の環境整備」である。職員は、利用者の居住環境がそのまま生活の質や安全性に直結することを十分に認識し、日々の業務において整理・整頓・清掃を意識的に行っている。特に「清掃」に関しては、事前に決められた作業のみをこなすのではなく、日常の中で気づいた「些細な清掃」を大切にしている。例えば、落ちているゴミを拾う、汚れをその場で拭き取る、見て見ぬふりをしないといった行動を職員共通の倫理観として位置づけており、この基本姿勢を事業所の標準的な行動規範とすることで、職員全体に浸透させている。
また、整理・整頓の実践においては、雑多になりがちな書類や物品を見直し、利用者周囲の環境を整えることを重視している。介護の現場では、必要な書類や物品が散乱していると、探す時間が増えたり、誤用や紛失といったリスクが生じやすい。そのため、業務効率を高めるだけでなく、誤薬や転倒といったリスクを未然に防ぐ目的からも、書類・物品の整理整頓は重要な取組となっている。職員一人ひとりが「必要なものを必要な場所に戻す」「不用なものは放置せず処分する」といった行動を徹底することで、利用者にとって快適で安全な居住環境が保たれると同時に、職員にとっても効率的に業務を遂行できる環境が形成されている。
さらに「清潔」と「躾」に関しては、5Sの基本を日常業務の中で習慣化し、組織全体の文化として根付かせることに重点を置いている。清潔を維持するための衛生意識は感染症予防にも直結し、利用者の安全確保に資する。一方、躾は単なる規律遵守ではなく、「見て見ぬふりをしない」「小さな改善を積み重ねる」という姿勢を育むことを意味している。当事業所では、この考え方を職員教育の基本方針に組み込み、新人からベテランまで共通の倫理観を持って業務に従事できるよう取り組んでいる。
以上のように、当事業所における5S活動は、単なる職場整理や清掃活動にとどまらず、訪問先住居という介護特有の現場に即した形で実践されている。日常業務の中で「些細な清掃」を重視する姿勢や、書類・物品整理による業務効率化とリスク低減、そして5Sの基本を職員の行動規範として定着させる取組を通じて、利用者に安心・安全で快適なサービスを提供できる体制を築いている。当事業所では、厚生労働省が推奨する「生産性向上ガイドライン」に基づき、情報共有の円滑化と職員の作業負担軽減を目的とした業務手順書や記録・報告様式の整備に積極的に取り組んでいる。
まず、日常業務の中で発生する各種書類について、システム化されているもの以外の書類に関しては、独自に様式を見直し、改善や簡素化を進めている。これにより、記入に要する時間を短縮し、記録そのものの精度と職員の負担軽減を両立させている。従来は複数の様式に重複して記載を求められることもあったが、様式の統合やチェック欄の簡略化により、無駄を削減しつつ必要な情報を確実に残せるよう工夫している。
また、業務に応じて必要とされる書式をあらためて検討し、現場で使いやすい形に整備している。職員が迷わず使用できるシンプルな様式を整えることで、記録業務が円滑に行える体制を構築し、記録を「負担」ではなく「支援」として機能させている。その結果、職員が本来注力すべき利用者へのケアに集中できる環境づくりを進めている。
さらに、訪問先が居宅だけでなく介護施設に及ぶケースもあるため、外部施設との情報連携にも力を入れている。特に、訪問先介護施設との間では情報共有ツールを導入し、口頭や紙ベースに頼らず、必要な情報を即時に共有できる体制を整備している。これにより、記録や報告のやり取りが迅速化し、双方の認識齟齬によるトラブルを防ぐとともに、利用者に対して一貫したケアを提供することが可能となっている。
これらの取組を通じて、当事業所では「業務手順書の作成や様式の工夫」が単なる文書整備にとどまらず、現場の負担を軽減し、情報の正確性・即時性を高める仕組みとして機能している。今後も継続的に様式改善やツールの活用を進め、利用者本位のサービス提供を支える基盤として発展させていく。当事業所では、業務効率の向上と職員間の円滑な情報共有を目的に、介護ソフトおよび情報端末の導入を積極的に進めている。
まず、介護ソフトとして『ほのぼの』を導入し、記録から情報共有、さらには請求業務までを一体的に管理できる体制を整えている。もし紙媒体で記録を行っていた場合には、そこから請求システムへ転記する手間が発生し、二重入力やミスのリスクが高まるところである。しかし『ほのぼの』を活用することで、記録データが自動的に請求業務へ反映され、そうした負担やリスクを回避できている。これにより、事務作業の効率化だけでなく、職員の負担軽減やサービス提供の質向上にも直結している。
さらに、現場での業務効率を高めるため、タブレット端末を複数台配置している。職員は訪問現場でリアルタイムに記録を入力できるため、事務所へ戻ってから改めて入力する必要がなくなり、直行直帰の環境を実現している。これにより、情報の即時性が高まり、利用者の状況を正確に記録・共有できるだけでなく、現場滞在時間の有効活用やサービス提供後の迅速なフィードバックが可能となっている。タブレットの導入は、単なる機器の活用にとどまらず、働き方改革にも資する効果を生み出している。
また、当事業所では訪問先介護施設との情報連携にも注力している。専用の情報共有ツールを活用し、訪問時以外でも利用者の状況をタイムリーに把握できる体制を構築している。これにより、訪問直前に最新の健康状態や生活状況を確認したり、訪問後に行ったケア内容を即時に共有することが可能となり、双方の認識齟齬を防ぎ、一貫したサービス提供を実現している。施設職員との間での情報共有が円滑になったことで、利用者を取り巻く多職種連携の質も高まり、より安心・安全なサービス提供につながっている。
以上のように、当事業所は『ほのぼの』の導入、タブレット端末の現場配置、外部施設との情報共有ツールの活用を通じて、介護ソフトと情報端末の導入を効果的に進めている。これらの取り組みは、単なるシステム導入にとどまらず、業務負担の軽減、記録の正確性向上、直行直帰による柔軟な働き方の実現、そして利用者本位のサービス提供体制の強化という成果を生んでいる。今後も引き続きICT活用を進め、より効率的かつ高品質な介護サービスの実現を目指していく。当事業所では、厚生労働省が示す「生産性向上ガイドライン」の方針を踏まえ、職員間の連絡調整や外部施設との情報共有を円滑に行うため、ICT機器の活用を積極的に進めている。その中核として導入しているのが、ビジネスチャットツール「LINE WORKS」である。
LINE WORKSの導入により、従来は電話や紙ベースの伝達に依存していた各種連絡が、即時かつ簡便に行えるようになった。シフト調整や業務連絡といった日常的な調整はもちろん、急な利用者対応や訪問スケジュールの変更も、タイムリーに共有できる体制を整備している。これにより、職員間の情報伝達の齟齬を防ぎ、業務遂行のスピードと正確性を高めている。
また、LINE WORKSは訪問先介護施設との連携においても有効に活用している。訪問時以外でも利用者の最新状況を施設側から受け取り、必要に応じて当事業所からも情報を共有することで、利用者の状態をタイムリーに把握できる体制を構築している。これにより、訪問時に限らず一貫した支援が可能となり、多職種連携の質も向上している。
さらに、LINE WORKSは会社全体の情報共有ツールとしても運用している。予定の周知や各種連絡事項の伝達、規則やマニュアルの共有、会議の議事録の配信など、多様な場面で活用している。職員は端末からいつでも必要な情報にアクセスでき、情報の属人化を防ぐとともに、組織全体での情報格差を解消している。これにより、全員が同じ情報を共有したうえで業務に取り組める体制を整えている。
加えて、BCP(事業継続計画)の観点からも、LINE WORKSを初動対応ツールとして位置づけている。災害発生時には、スタッフの安否確認や初期対応に関する指示伝達の手段として活用する計画を盛り込んでおり、緊急時にも迅速に全職員へ情報が行き渡る体制を確立している。これにより、平時の業務効率化だけでなく、有事における安全確保や事業継続にも資するツールとして運用している。
以上のように、当事業所では職員間の連絡調整や外部施設との情報共有を円滑化するためにビジネスチャットツールを積極的に活用している。LINE WORKSを中心とした運用は、業務負担の軽減、情報伝達の迅速化、緊急時対応力の強化といった多面的な効果をもたらしており、利用者に対するサービスの質向上と職員の働きやすさの両立を実現している。今後もICT機器のさらなる活用を進め、介護現場の効率化と安全性の向上を目指していく。当事業所では、介護職員がケアに専念できる環境を整えることを目的に、業務内容の明確化と役割分担を重視した体制を整備している。
具体的には、毎年年度初めに無資格者の採用を計画的に行い、また年度途中においても無資格者からの応募があった場合は積極的に採用している。これにより、現場における人材層を厚くし、多様な人材が役割に応じて働ける環境を確保している。採用した無資格者については、入職後に初任者研修の取得を推進し、資格取得後はOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)期間を経て介護補助者として活用している。この流れを標準化することで、介護職員の専門性を必要とするケア業務と補助的な業務とが適切に切り分けられ、業務の効率化が図られている。
この仕組みにより、介護職員は本来注力すべきケア業務に集中できるようになり、利用者に対するサービスの質の向上にもつながっている。一方で、介護補助者は補助的な役割を担いながら現場での経験を積み、段階的にスキルアップを図ることができる。結果として、職員全体の負担軽減と人材育成の両立を実現している。
また、このような補助者の活用は、介護職員の負担軽減の一助となるだけでなく、長期的には職員の定着や離職防止にも寄与している。役割を明確に分担することで、現場全体の業務の流れが整理され、介護チームとしての一体感や働きやすさが高まっている。
以上のように、当事業所では無資格者の計画的な採用と育成を通じて介護補助者を活用し、負担を軽減する体制を構築している。今後も役割分担やシフト体制の見直しを継続的に行い、介護職員が利用者ケアに集中できる職場環境を整備していく。当事業所では、法人内の系列事業所との協働化を積極的に推進し、職場環境の改善と業務効率の向上を図っている。
まず、各種委員会活動については、ツール(Zoom)を積極的に活用し、系列事業所である「ほの字船津」と合同開催を行っている。これにより、双方の事業所で抱える課題や改善策を共有し、解決方法を共同で探る場としている。単独の事業所内で完結させるのではなく、法人全体の知見や経験を活かした協働の形をとることで、課題への対応力や改善の幅を広げている。さらに、各種指針や計画の策定においても同様に協議を行い、方向性を共有しながら一貫性のある運営を実現している。
次に、事務処理部門の効率化については、時代の流れを踏まえ、ほとんどの事務処理を外注化している。事業所から業務オーダーを出し、外部から成果物を受け取る仕組みを確立することで、内部の負担を大幅に削減し、職員が利用者サービスに集中できる体制を整えている。このように、外部資源を効果的に活用することで、事務処理の正確性・効率性を維持しつつ、現場へのリソース配分を最適化している。
さらに、人事・労務領域においても協働化を推進している。職員データベースをはじめとする情報はすべてシステムで一元管理しており、事業所から管理職、そして現場職員までが一気通貫で情報を共有できる体制を構築している。この仕組みにより、人材管理や勤怠管理、労務手続きなどが標準化され、属人的な業務処理から脱却できている。情報がシステム上で可視化されていることで、管理職が迅速かつ適切に判断でき、職員一人ひとりの働きやすさにもつながっている。
以上のように、当事業所では委員会の共同開催、指針・計画の共同策定、事務処理の外注化、そして人事・労務システムの一元管理といった協働化を通じて、職場環境の改善と業務効率化を実現している。今後も法人内の連携を深めるとともに、ICTのさらなる活用や外部リソースの効果的な導入を進め、持続可能で質の高い介護サービスを提供できる環境整備に努めていく。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
当事業所では、職員一人ひとりの気づきを大切にし、勤務環境やケア内容の改善につなげるために、月1回の事業所全体ミーティングを実施しています。
ミーティングでは、利用者の個別ケースを題材とした事例検討や情報共有を行い、各職員が自身の考えを発信できる場を設けています。これにより、ケアの質の向上だけでなく、職員同士が相互に学び合う風土を醸成しています。
また、介護に直接関わるテーマにとどまらず、介護から離れた題材を用いたグループワークやディベートも取り入れ、柔軟な発想やコミュニケーション力の向上を図っています。さらに、隣のスタッフへ日常の出来事をきっかけに感謝の言葉を伝えるなど、お互いを認め合う文化を育む仕組みもミーティング内で実践しています。
これらの取組みにより、職員が主体的に意見を出し合い、日常の気づきを積極的に共有することで、働きやすい職場環境の形成と利用者本位のケアの実現を推進しています。当事業所では、介護保険制度や法人の理念を職員全員が正しく理解し、利用者本位のケアを実践するための学びの機会を定期的に設けています。その一環として、外部研修事業者を招き、映画「ロストケア」を題材とした倫理研修を実施しました。
この研修では、介護現場で起こり得る倫理的な課題やジレンマを具体的に取り上げ、スタッフ一人ひとりが「介護とは何か」「利用者本位とは何か」を改めて考える機会となりました。特に研修の中で問題提起がなされ、日常の支援場面における価値観の揺らぎや判断の難しさについて活発な意見交換が行われました。
こうした学びを通じて、職員は理念を単なる言葉として捉えるのではなく、自らのケア行動に照らし合わせて実践的に考える力を養っています。今後も定期的に外部研修や内部ディスカッションを重ね、利用者一人ひとりの尊厳を守るケアの実現に向けた体制を強化していきます。当事業所では、日々の支援の中で生まれるケアの好事例や利用者・ご家族から寄せられた謝意について、全職員で共有する機会を定期的に設けています。具体的には、毎月1回の事業所ミーティングにおいて、各職員が実際の事例や利用者からの感謝の言葉を紹介し合い、良い実践を全体の学びとして活用しています。
また、外部研修事業者による研修の中では、第三者から見た当事業所の社会的役割や意義について賞賛を受ける機会があり、職員の意識高揚やモチベーション向上につながっています。加えて、MVV(Mission・Vision・Value)研修においては、自事業所の取組や在り方を振り返り、理念に基づいた実践について考察する機会を持ち、好事例や感謝の声を理念と結びつけて再確認しています。
こうした継続的な取組により、職員一人ひとりが自らの実践を振り返り、他者からの評価や感謝を実感することで、組織全体としての成長とサービスの質向上を実現しています。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所では、20代から60代まで幅広い年齢層の職員が在籍し、経験年数も多様です。その特性を活かしながら、組織全体として自立的かつ自走できる成熟したチームを目指しています。既存の介護事業所にありがちな雰囲気や慣習に縛られず、常に新しい発想で事業所づくりを進めている点が特徴です。定期的なミーティングでは全員が参画し、意見を出し合う風土を大切にしています。また、派閥や固定的な人間関係といった介護業界で起こりやすい問題を徹底的に排除し、誰もが安心して働き、力を発揮できる環境を整えています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
当事業所の利用者は、平均介護度が3.5~3.8と比較的高く、日常生活において多様な支援を必要とされる方が中心です。生活保護を受給されている方や、身寄りのない方も多く利用されており、社会的に支援が必要な状況にある方々に対しても、安心して暮らせる環境づくりを重視しています。
また、透析治療を受けている方や在宅酸素療法を利用されている方もいらっしゃるため、訪問看護事業所と連携しながら、医療ニーズにも対応可能な支援体制を整えています。このように、医療的ケアや生活支援を複合的に必要とする利用者の方々に寄り添い、継続的な在宅生活を支えることを特色としています。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
当事業所の勤務時間は以下の通りです。利用者への切れ目のないサービス提供と、職員の多様な働き方に対応できるよう、日勤・夜勤・短時間勤務の勤務形態を設けています。
■ 基本勤務
日勤(早番):6:30~15:30
日勤(通常):8:30~17:30
夜勤 :17:00~翌9:00
■ 短時間勤務
9:00~16:30
9:00~17:00
8:30~12:00(入浴介助優先)
13:00~17:30
また、入社後においても、職員一人ひとりの生活事情や家庭の背景等を踏まえ、管理者との協議により勤務時間の調整を柔軟に行っている。これにより、育児や介護、通院などの個別事情を抱える職員であっても、無理なく勤務を継続できる環境を整えている。こうした取組は、長期的な就業継続を支えるとともに、多様な人材が安心して働き続けられる職場づくりにつながっている。
当事業所では、勤務シフトの柔軟な運用と環境整備を通じて、職員が安心して働きながら、利用者に対して質の高い介護サービスを安定的に提供できる体制を整えている。
賃金体系
当事業所では、職員が安心して働き続けられるよう、公平性と透明性を重視した賃金体系を整備している。賃金は以下の項目を基本構成としており、職員の経験・能力・勤務形態に応じて適切に支給している。
俸給
基礎となる給与部分であり、職種や勤務形態に応じて設定している。
職務能力給
職員の役割や業務遂行能力に応じて支給し、個々のスキルや責任に応じた評価を反映している。
資格・調整手当
介護福祉士などの専門資格を有する職員には資格手当を支給しており、また業務の特性や配置等に応じた調整手当を設けている。
夜勤手当
夜間勤務に従事する職員に対しては、労務負担を考慮し、所定の夜勤手当を支給している。
変動処遇改善加算
毎月の事業所介護報酬に応じて算定される処遇改善加算を原資とし、職員へ還元している。事業所の成果を職員に適切に反映させる仕組みとして位置づけている。
業務調整連絡手当
事業所ミーティングに出席し、業務調整や情報共有に携わる職員に対して支給している。これは、円滑な事業運営に必要な調整業務を評価し、組織全体の質の向上を支える目的で設けている。
通勤手当
通勤にかかる費用の一部を補助する目的で支給しており、上限は10,000円としている。
その他手当
リファラル採用手当:既存職員が紹介した人材が採用に至った場合、紹介者・採用者の双方へ年2回に分け支給している。
賞与
原則として毎年7月に支給を行い、事業所の半期の売上および経営状況を踏まえて決定している。
過去6年間の実績としては、年2回の支給を継続している。
昇給
原則として毎年7月に実施し、勤務状況や能力等を考慮して決定している。
過去6年間の実績として、年1回の昇給を行っている。