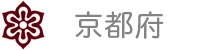2025年02月03日09:57 公表
医療法人 松寿会 共和病院 訪問リハビリテーション
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
8/65人 -
最大受け入れ人数65人中、現在の受け入れ可能人数8人です。
(2025年01月21日時点)
サービスの内容に関する自由記述
医療法人松寿会共和病院では、病気や怪我・加齢などにより、心身に何らかの障がいを持たれた方やそのご家族が住み慣れた地域において、継続してより良い在宅生活をおくる事が出来るよう理学・作業・言語療法士による訪問リハビリテーションを行っております。
訪問リハビリテーションは、医師の指示に基づいて、心身機能や生活環境を評価し、目標を設定して、日常生活動作能力の改善や心身機能の維持および向上・住環境の整備や介助動作の指導などを実施しております。
☆訪問リハビリテーションのサービス内容☆
1)生活機能障害の評価…お身体の状態を確認し、状態に合ったリハビリを実施するとともに説明を行ないます。
評価や生活動作の助言・提案のみを行なう期間設定利用(1ヶ月程度)も行なっています。
2)身体機能の訓練…関節の動きを良くする運動や筋力を強化する訓練を行ないます。
3)基本動作の訓練…寝返りや起き上がり・床からの立ち上がりの練習や屋内・外での歩行練習を行ないます。
4)日常生活動作の訓練…トイレやお風呂・着替えといった生活動作を安全に自分で行なえるよう練習を行ないます。
5)生活環境の調整…ご利用者様にあった住環境の調整(配置換えや住宅改修の提案)や福祉用具の選定などを行ないます。
6)言語機能の訓練…失語症など高次脳機能障害や、構音障害に対して能力に応じた言語訓練を行います。
7)嚥下機能障害の訓練…様々な疾患による飲み込みの問題に対して、口腔運動等の基礎訓練から、食事摂取、介助方法の説明等状態
に応じた嚥下訓練を行います。
8)ご家族様への介助方法の助言…腰痛を予防する介助方法やご本人様に能力を活かした動作方法などをお伝えします。
9)その他…趣味活動の継続(獲得)や社会的活動を継続するための練習を行ないます。
サービスの質の向上に向けた取組
-
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
-
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
-
-
-
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
-
-
-
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
-
-
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
-
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
理学療法士3名
利用者様・家族様のお困り事やご意向に沿ってリハビリを行います。
また身体機能・動作面の評価・アプローチのみならず、住宅改修や
福祉用具の導入など生活環境を含めた検討・ご提案も致しております。
移動手段はバイク・自転車などにてフットワーク軽く地域を巡回しております。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
利用者の年代としては50歳代~90歳代までの方となっています。そのうち70代・80代が半数以上を占めて
います。男女比としては男性約4に対して女性は約6となっています。さらに対象疾患としては運動器疾患・脳血管
疾患をはじめ・心疾患・廃用症候群など、多岐にわたっています。