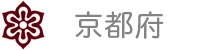2025年10月20日13:22 公表
訪問介護 空
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
0/0人 -
最大受け入れ人数0人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
(2025年09月17日時点)
サービスの内容に関する自由記述
-
サービスの質の向上に向けた取組
資格取得や研修への参加など、自己研鑽に意欲的な姿勢を持つスタッフが多く、成長意欲と専門性の向上を事業所全体で支え合っています。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
地域に根差した質の高いケアを提供しています。その実現には、人材の確保と育成が不可欠であると考え、法人全体として明確なケア方針と人材育成方針を策定しています。特に「働く職員自身が安心し、成長できる環境であること」を重視し、入職後の研修体系の整備、キャリアパスの明確化、評価制度やインセンティブ制度の導入など、やりがいを持って働ける仕組みを構築しています。また、チームでの支援体制を重視し、個人任せにしないフォローアップ体制を整えることで、経験やスキルに不安がある方でも安心して現場に入ることができるようにしています。
地域内の複数事業所と連携し、採用活動の情報共有や合同説明会の実施、職員の人事ローテーションの仕組みづくりを進めています。これにより、特定の事業所だけでなく法人全体として安定的な人材確保を目指すとともに、職員が複数の現場を経験することで幅広い視点やスキルを習得できる体制を整えています。さらに、研修についても法人横断的に実施することで、同じ法人内であっても事業所ごとに偏りが出ないように配慮し、共通したケアの質を維持・向上させています。外部講師を招いた勉強会や、資格取得に向けた支援制度も導入し、キャリア形成を法人全体で支援しています。
当法人では、他産業からの転職者や主婦層、中高年齢者など、経験や資格の有無にかかわらず広く採用の門戸を開いています。実際に、全く介護業界未経験で入職した職員が、研修やOJTを通じて着実に成長し、資格を取得してサービス提供責任者や相談支援専門員へとキャリアアップした事例もあります。家庭と両立したいパート勤務の方や、定年後に地域貢献として働くことを選んだ中高年層の方など、多様な人材が活躍しています。こうした幅広い採用を可能にしているのは、法人内に「初任者研修から実務者研修、介護福祉士取得」までのステップを支援する仕組みがあるからです。誰もが安心して新たな一歩を踏み出せるよう、制度面と教育面の両輪でサポートし、結果として離職率の低下と職員定着率の向上につながっています。
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当法人では、介護職員一人ひとりが「働きながら学び、成長できる職場環境」を整えることを重視しています。そのため、介護福祉士取得を目指す職員には、実務者研修の受講費用の助成や勤務調整による学習時間の確保など、制度面・運用面での支援を行っています。また、専門性の高い介護技術を習得するために必要な研修(喀痰吸引等研修、実務者研修、介護福祉士など)についても、受講費用補助やシフト調整によって積極的な受講を後押ししています。
さらに、中堅職員に対してはマネジメント研修を通じ、チームリーダーとして必要な人材育成力・業務管理力・組織運営力を養成しています。これにより、単なる現場スキルの向上にとどまらず、事業所全体のマネジメント力強化へとつなげています。法人全体で「学び続ける文化」を醸成することで、キャリアアップへの意欲が自然と高まり、職員の定着率向上にも寄与しています。当法人では、研修受講の実績や職員の成長が正しく評価される仕組みを整えています。具体的には、定期的な人事考課において、日常業務の成果や利用者対応の質に加え、「研修受講歴」「資格取得状況」を重要な評価項目としています。
面談では、日常業務に関する振り返りや改善点の確認に加え、将来的に目指す資格取得や役職キャリアについて具体的に相談できる体制を整えています。また、子育てや介護などの家庭事情に応じた勤務形態の見直しや、ワークライフバランスを踏まえた働き方の調整も行っており、個人のライフステージに寄り添った柔軟な対応が可能です。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
育児については、産前産後休業・育児休業の取得を積極的に推奨しており、復職に向けた職場復帰面談や短時間勤務制度を通じて、スムーズに職場へ戻れる仕組みを整えています。特に、復職直後のシフトについては、保育園や学校行事への参加を考慮し、柔軟な勤務調整を可能としています。また、男性職員の育児休業取得についても法人全体で推進し、育児に対する意識改革を進めています。
家族の介護についても、介護休暇・介護休業の取得や時短勤務制度を活用できるよう制度を整備しており、突然の介護ニーズにも対応できるよう管理者や上司が相談窓口となっています。これにより、家庭の事情と仕事の両立を支援し、離職防止につなげています。職員一人ひとりの生活状況やライフステージに合わせて、安心して働き続けられるような勤務制度を整えています。特に「子育て」「介護」「学業」「ダブルワーク」など、個々の事情に配慮した柔軟なシフト調整を行い、長時間勤務が難しい職員でも無理なく働ける体制を構築しています。
その一環として、短時間正規職員制度を導入しており、1日あたりの勤務時間や週あたりの勤務日数を調整しながらも、正規職員としての処遇を受けられる仕組みを用意しています。これにより、フルタイム勤務が困難な時期でもキャリアを中断せず、安定した雇用形態で働き続けられるよう支援しています。職員が心身ともに健康で働き続けられることが、利用者への安定したサービス提供につながると考え、有給休暇の計画的な取得促進に力を入れています。
また、有給の残日数が常に分かるように給与明細に記載しています。日々の支援内容や利用者の状況を記録・システムで共有し、担当者以外でもスムーズに対応できるよう情報共有体制を整備しています。加えて、複数担当制を導入することで、一人の職員に業務が集中せず、誰かが休暇を取っても他の職員が代わりに対応できる仕組みを構築しています。
また、業務の偏りを防ぐために、シフト作成時には事務員が各職員の担当件数や勤務状況を確認し、公平な業務配分を心がけています。これにより、一部の職員に負担が集中して休暇が取りにくくなることを防ぎ、全員が安心して休暇を取得できる体制を実現しています。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
職員が安心して働けるよう、業務上の悩みや福利厚生制度の利用、メンタルヘルスに関する相談に対応する窓口を設置しています。管理者や専門担当者が相談対応を行い、必要に応じて外部機関とも連携しながら、早期解決と職員の安心につなげています。
全職員を対象に定期健康診断やストレスチェックを実施し、短時間勤務者も受診できる体制を整えています。また、職員が心身をリフレッシュできるよう、休憩室を設置し、健康維持と職場環境の改善に取り組んでいます。
介護技術の習得支援や腰痛予防研修を実施しています。
利用者の安全と職員の安心を守るため、事故・トラブル発生時の対応マニュアルを整備しています。職員に周知徹底するとともに、定期的に見直しや研修を行い、迅速かつ適切に対応できる体制を構築しています。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
日常業務の中で生じている課題を抽出・整理しています。抽出された課題は会議等で共有し、構造化して改善の優先順位を明確化することで、対応策を組織的に検討・実施しています。これにより、属人的な対応を防ぎ、効率的かつ質の高いサービス提供を可能にしています。
物品や備品を必要なものと不要なものに区分し、配置や保管場所を明確化することで、業務効率を高めています。また、日常的な清掃・点検を徹底し、常に清潔で安全な環境を維持しています。
業務手順書を整備し、誰でも同じ手順で作業できる体制を構築しています。これにより業務の標準化を進め、属人化を防止しています。
また、記録・報告様式についても現場の声を反映し、分かりやすく簡便な形式に工夫することで、記録業務にかかる時間を削減し、職員の負担軽減を図っています。これにより、情報共有の精度が高まり、利用者支援により多くの時間を充てられる環境が整っています。業務の効率化と情報共有の質向上を目的に、介護ソフトを導入しています。記録や情報共有に加え、請求業務への転記が不要なシステムを活用することで、職員の事務作業負担を大幅に軽減しています。
シフト編成の段階で業務量の偏りが生じないよう調整を行い、必要に応じて役割の見直しを実施することで、効率的かつ公平な体制を構築しています。これにより、介護職員が利用者に向き合う時間を十分に確保でき、サービスの質向上と職員の働きやすさの両立を実現しています。
虐待防止委員会・感染症委員会など各種委員会の共同設置や、身体拘束適正化指針・虐待防止計画・BCPなどの各種指針・計画を共同で策定し、標準化と効率化を図っています。
また、物品の共同購入によるコスト削減や、事務処理部門の集約によって、現場職員がケアに専念できる体制を整えています。さらに、ICTインフラを共同で整備し、人事管理システムや福利厚生制度の共通化を進めることで、法人全体として統一された管理体制を実現しています。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
現場内のコミュニケーションを活性化し、職員一人ひとりの気づきを業務改善に反映しています。現場での小さな課題や工夫を共有することで、勤務環境の改善やケア内容の質向上につなげています。
また、管理者やサービス提供責任者が進行役となり、職員が意見を出しやすい雰囲気づくりを心がけています。これにより、情報共有の精度が高まり、利用者支援に関する新しい視点や改善策が生まれやすくなっています。定期的な学習機会を設けています。具体的には、定例会議や研修の場を活用し、介護保険制度の改正点や事業所のケア方針を確認・討議する機会を設け、全職員が共通の理解を持って業務にあたれるよう努めています。
併設されているサービス
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・相談支援
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所のスタッフは、明るく親しみやすい人柄と、利用者一人ひとりに寄り添う温かいコミュニケーション力を強みとしています。日々の支援では、安心感を持っていただけるよう丁寧かつ誠実な対応を心がけ、利用者やご家族から厚い信頼をいただいています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
-
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
正社員:8時間勤務とし、希望勤務時間に沿ってシフト調整を実施。
賃金体系
売上に準じたインセンティブ制度を導入
休暇制度の内容および取得状況
年次有給休暇整備、勤続年数に応じて付与日数の増加。