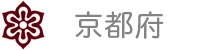2025年10月20日13:22 公表
久世ホーム訪問介護事業所 夜間対応型訪問介護
サービスの内容に関する写真
-

久世訪問介護事業所は京都市久世特別養護老人ホーム内にあります。施設にはデイサービスやショートステイも併設されており、訪問介護と併用されている方もたくさんおられますので、利用者様とお会いすることもしばしばあります。 -

勤務開始前は職員からの引継ぎ情報を確認してから、施設を出発をします。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
1/22人 -
最大受け入れ人数22人中、現在の受け入れ可能人数1人です。
(2022年12月27日時点)
サービスの内容に関する自由記述
訪問介護員等(ホームヘルパー)が、18時~翌朝8時までの夜間帯にご自宅を訪問します。食事やトイレの介助・オムツ交換、服薬確認等の「身体介護」のほか、もしもの時には24時間・年中無休の「緊急通報システム」により、ご自宅に駆けつけます。昼間だけでなく、夜間においても、安心してご自宅でお過ごしいただけるよう、サポートいたします。
また、久世ホーム訪問介護事業所では、訪問介護、定期巡回随時対応型訪問介護も併設されており、利用者様の状態に合わせてサービスを選んでいただけます。
サービスの質の向上に向けた取組
夜間対応型訪問介護は、緊急時に訪問するということになります。そのため、ご利用がない場合は、1ヶ月間訪問する事はありません。利用者様の状態を把握できるよう、私たちは毎月利用者様のお宅に訪問して、体調などを伺っております。また、その情報を他の職員にも共有し、どの職員が訪問しても対応できるように努めております。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
-
併設されているサービス
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防支援
介護老人福祉施設
保険外の利用料等に関する自由記述
利用料金:30分 1250円
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
20代〜50代の職員で構成されています。各職員のやる気と能力に応じ業務をお任せします。久世訪問介護事業所は、特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援事業所も併設されているため、各サービスで経験を積んだ職員が主になっております。比較的若い職員で構成されているため、とても活気があります。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
平均要介護度は3.5です。歩行に不安があり、転倒の危険がある方や、高血圧などの既往歴があり、急変される危険性のある方がたくさんご利用されています。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
早出:7:00~16:00
日勤:9:00~18:00
遅出:12:00~21:00
夜勤:21:00~7:00
賃金体系
定期昇給
入職1年後から最大8年間、毎年昇給があります。
※昇給額:3,472円〜(初年度でボーナスUP分を含み、年収で56,246円UP)
昇級試験
昇級試験に合格すると、昇給額が増えるほか、定期昇給の年数が延長になります。
(合格率は約70%)
退職金制度(確定給付企業年金)
給与の額に応じて、毎月一定の金額を控除し、それに法人からの拠出を加えた額(控除額とほぼ同額)を毎月積み立て、退職時にそれを給付いたします。
(例)給与からの控除4,000円+法人からの拠出4,000円=合計8,000円を毎月積み立て
休暇制度の内容および取得状況
産休・育休制度
産前6週間、産後8週間の産前産後休暇制度(産休)、原則、子どもが満1歳に達する日(最大1歳半を超えた後に初めて到来する4月末まで延長可能)までの間に取得することができる育児休業制度(育休)を就業規則に定めています。
この他、出産時には祝金の支給もあります。
その他介護休暇、年次有給休暇、特別休暇、生理休暇もございます。
福利厚生の状況
<キャリアアップ支援>
キャリアアップ制度
各職員の能力を伸ばすため、キャリアに応じた研修・制度を設けています。
資格補助
《介護福祉士の場合》※合格者のみ
•介護技術講習会費用のうち35,000円を施設が負担します。
•実技試験の登録免許税、登録手数料の補助あり。
•介護福祉士実務者研修の登録免許税、登録手数料の補助あり。
※介護技術講習会への出席は公休扱いとします。
《介護支援専門員の場合》※合格者のみ
•実務研修費用と受験料は施設が全額負担します。
(研修費、受験料、登録手数料、交通費)
•実務研修出席については、研修(出勤)扱いとし、交通費を支給。
•その後の更新研修も同じく、研修(出勤)扱いとし、交通費を支給。
•主任介護支援専門員取得の費用(研修費、登録手数料、交通費)は施設が全額負担します。
《社会福祉士・精神保健福祉士・管理栄養士》※合格者のみ
•登録免許税、登録手数料を補助します。
《書籍購入の補助》※合格者のみ
•各資格取得にかかる書籍を購入した場合、1資格につき3,000円までの補助があります
<女性のための福利厚生>
短時間勤務
3歳に満たない子どもを養育する職員は、所定労働時間を6時間とする「短時間勤務」を希望することができます。※勤務時間帯は、施設や部署によって異なります。
業務負担軽減
本人の希望により、夜勤の免除や入浴介助の免除など、一時的に身体的負担を軽減する業務形態にすることも可能です。