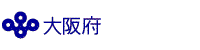2025年11月05日18:26 公表
医療法人全心会 寝屋川ひかり病院
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
7/30人 -
最大受け入れ人数30人中、現在の受け入れ可能人数7人です。
(2025年10月10日時点)
サービスの内容に関する自由記述
退院後の在宅生活に関して、自宅環境で評価を行い生活にあったリハビリテーションをご提案します。身体のことに関する心身機能へのアプローチだけでなく、ご本人への動作指導やご家族様への介助指導も実施しております。自宅内でのリハビリだけでなく周辺環境を利用して屋外での歩行や運動なども行い、充実した生活につながるように支援させて頂きます。また安心して生活を送れるようにケアマネージャーや関係スタッフと連携しながら福祉用具の提案や介護サービスの調整などの相談にも対応します。加えて、リハビリテーション実施の際にはバイタルサインの確認や体調の確認も行い、何か問題があれば主治医やケアマネージャーに報告し、問題の早期発見に努めています。
サービスの質の向上に向けた取組
定期的に職員間で情報共有を行い、利用者様の状態変化や支援方針について確認しています。
院内外の研修への参加を通じて、在宅リハビリテーションに必要な知識・技術の向上を図り、得られた内容は職員間で共有しています。
また、主治医・訪問看護・ケアマネジャーなど多職種との連携を重視し、利用者様が安心して在宅生活を続けられるよう質の高いリハビリテーションの提供に努めています。
- 取組に関係するホームページURL
-
-
寝屋川ひかり病院 リハビリテーション科
https://neyagawahikarireha.wixsite.com/website-2
-
寝屋川ひかり病院 リハビリテーション科
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
HMG全体の理念として「ひかり輝く心身であれ」「患者様の立場に立って考えよ」「責任を持って行動せよ」を掲げています。
リハビリテーション科の理念は「生活に安心を提供する」であり、利用者様が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援しています。
職員教育としてはOJTや院内研修、クリニカルラダー制度を活用し、段階的な人材育成を推進しています。
また、ISOや病院機能評価の仕組みを通じて、PDCAサイクルによる継続的な改善と、マニュアル整備・標準化の推進を行い、サービスの質向上を図っています。法人内の各施設(病院・通所・訪問部門)で連携を図り、リハビリテーション科の責任者会議を定期的に開催しています。
会議では各事業所の課題や方針を共有し、採用や教育体制の方向性を統一しています。
新入職者研修や経験年数別研修(1〜2年目、3〜4年目、5〜6年目)は法人全体で合同実施しており、各事業所間での人材交流や知識共有を通じて職員の育成を進めています。
必要に応じて人事ローテーションも行い、幅広い分野での経験が積める体制を整えています。寝屋川市内の小・中学校からの職場体験学習を受け入れ、児童・生徒に医療・リハビリテーションの仕事を知ってもらう機会を設けています。
また、地域包括支援センターと連携し、地域住民を対象とした体操教室や体力測定会に職員がボランティアとして参加するなど、地域に開かれた活動を継続しています。
これらの取り組みを通じて、地域における医療・介護専門職への理解促進と、職員のモチベーション向上につなげています。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
職員のスキルアップを支援するため、介護福祉士などの資格取得に向けた研修受講時には、病院からの補助制度を設けています。
また、認知症ケア、喀痰吸引、サービス提供責任者研修、マネジメント研修など、より専門性の高い分野の研修についても受講を推奨し、研修支援制度により費用の一部を助成しています。
職員が働きながら学び続けられる環境づくりを通じて、専門職としての資質向上とサービスの質の維持・向上を図っています。職員の成長を段階的に支援するため、クリニカルラダー制度を導入しています。
研修の受講状況やラダーレベルの到達度を評価に反映し、個々の成長が人事考課にもつながる仕組みとしています。
また、上位者との面談を通じてキャリア形成や今後の課題を確認し、専門職として継続的に能力を高められるよう支援しています。新入職員や若手職員に対して、上位者との定期的な面談を通じて業務上の悩みや不安を共有し、個別にサポートを行っています。
経験豊富なスタッフが日常業務の中で相談に応じ、職場に早くなじめるよう支援しています。
こうした取り組みにより、職員の定着促進と安心して働ける環境づくりを進めています。職員のキャリア形成や働き方に関する相談の機会を確保するため、定期的に上位者との面談を実施しています。
面談では、業務の課題や今後の目標、スキルアップに向けた取り組みなどを共有し、個々の成長に応じた支援を行っています。
これにより、職員が将来を見据えて安心して働き続けられる環境づくりを進めています。 - 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
育児休業など、家庭と仕事の両立を支援するための制度を整えています。
職員が安心して休暇を取得できるよう、業務調整や職場内でのフォロー体制を整備しており、育児休業の取得実績もあります。
託児施設は設けていませんが、職員がライフステージに応じて柔軟に働ける環境づくりを進めています。職員が安心して有給休暇を取得できるよう、計画的な休暇取得を推奨し、上司からの声かけや勤務調整を行っています。
有給休暇の取得率は90%以上と高く、連休の取得も事前に相談のうえで柔軟に対応しています。
夏季休暇や誕生日休暇などの特別休暇制度もあり、職員同士でフォローし合いながら、休みやすい職場環境づくりを進めています。職員が安心して休暇を取得できるよう、日々の申し送りや情報共有を徹底し、業務の属人化を防いでいます。
休みの予定はカレンダーで全員が共有し、他の職員が代行できる体制を整えています。
また、リハ助手業務についても理学療法士がフォローできるようにしており、職種間で協力しながら業務負担の偏りを軽減しています。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
職員が安心して働けるよう、業務上の相談や健康面の悩みを共有できる体制を整えています。
福利厚生として、職員は当院での受診を自己負担なく行うことができ、心身の不調にも早期に対応できる環境を整備しています。
また、産業医の助言を受けながら職場環境の改善に努め、メンタルヘルスを含む相談体制の充実を図っています。職員の健康管理を重視し、常勤・非常勤を問わず全職員を対象に年1回の健康診断を実施しています。
また、ストレスチェックも定期的に行い、心身の不調の早期発見と対応に努めています。
職員が安心して休憩・リフレッシュできるよう、休憩スペースも整備し、働きやすい職場環境づくりを推進しています。職員の身体的負担を軽減するため、正しい介護動作や移乗介助などに関する研修を院内で実施しています。
腰痛を含む身体の不調がある場合は、院内で受診できる体制を整えており、早期対応を行っています。
また、管理者は法人推奨の研修を受講し、職員の安全確保や働きやすい職場づくりに関する知識の向上に努めています。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
-
職員からの意見や改善提案を「気付きメモ」として提出できる仕組みを設け、業務上の課題を随時共有しています。
月1回の科内会議や定期面談を通じて課題の把握と解決策の検討を行い、職場環境や業務改善につなげています。
また、職員の稼働率や残業時間を定期的に把握し、負担が偏らないよう調整するなど、働きやすい職場づくりを進めています。職場の整理・整頓・清掃を日常的に行い、常に清潔で安全な環境を維持するよう努めています。
備品やリハビリ機器、記録物の配置を統一し、誰でも分かりやすく取り扱えるよう工夫しています。
また、業務マニュアルや掲示物の整備を通じて、働きやすく事故の起こりにくい職場環境づくりを推進しています。各業務の標準化を図るため、業務マニュアルを整備し、手順の統一と情報共有を徹底しています。
記録や報告については、電子カルテや「コンダクト」シリーズなどのシステムを活用し、入力作業の効率化とミス防止に努めています。
また、エクセル等を用いて管理業務の自動化を進めることで、職員の作業負担を軽減し、リハビリ提供時間の確保につなげています。「コンダクト フラワーシリーズ」や電子カルテを導入し、利用者情報やリハビリ記録、請求業務を一元管理しています。
記録内容の転記作業を減らすことで事務負担を軽減し、職員間での情報共有や報告の効率化を図っています。
また、必要に応じてタブレット端末等を活用し、訪問先でも情報確認が可能な体制を整えています。法人全体で医療安全委員会や院内感染対策委員会などの各種委員会を設置し、情報共有と安全管理の徹底を図っています。
また、指針や計画の策定は法人内で統一し、マニュアルや方針を共通化することで業務の標準化を進めています。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
定期的に科内会議を開催し、利用者支援に関する情報共有や業務上の課題について話し合う場を設けています。
また、個人面談を通じて職員一人ひとりの意見や気づきを把握し、勤務環境の改善やケアの質向上につなげています。
職員間のコミュニケーションを重視し、意見を出し合いやすい風通しの良い職場づくりを心がけています。地域包括支援センターと連携し、地域住民を対象とした体操教室や体力測定会に参加・協力しています。
また、寝屋川市内の小・中学校からの職場体験学習を受け入れ、児童・生徒に医療やリハビリテーションの仕事を知ってもらう機会を設けています。
こうした地域との交流を通じて、地域包括ケアの一員としての意識向上と職員のモチベーション向上につなげています。職員が日々の業務の中で感じた良い出来事や感謝の言葉などを「ハッピーメモ」として記録・共有する仕組みを設けています。
利用者様やご家族から寄せられた感謝の言葉やアンケートでの意見も職員間で共有し、ケアの励みや改善の参考としています。
こうした取り組みを通じて、職員のモチベーション向上と、より質の高いリハビリテーションサービスの提供を目指しています。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
リハビリテーション科スタッフは理学療法士13名、リハ助手3名の計16名で構成されています。20代から50代まで幅広い年齢層の職員が在籍し、明るく相談しやすい雰囲気の中で連携・情報共有を重視したチーム体制をとっています。
運動器の認定理学療法士4名、3学会合同呼吸療法認定士1名、LSVT BIG認定セラピスト1名など、専門資格を有する職員も多く、各分野での専門性を活かした支援を行っています。
登録理学療法士・認定理学療法士の取得を目指すスタッフも多く、院内研修や勉強会を通じて人材育成と専門職としてのスキル向上に取り組んでいます。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
要支援から要介護まで幅広い利用者様にご利用いただいています。年齢層は70〜90代が中心で、脳血管疾患、整形外科疾患、神経難病、廃用症候群など、在宅生活での身体機能維持や動作能力の向上を目的とされる方が多くを占めています。
日常生活動作(ADL)の維持・向上を図るため、実際の生活環境に即した動作練習や福祉用具の選定・環境調整などを行っています。
利用者様・ご家族・主治医・ケアマネジャー・訪問看護との連携を重視し、安全で安心できる在宅生活の継続支援に取り組んでいます。