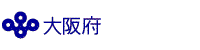2025年12月08日15:36 公表
介護老人保健施設よどの里
サービスの内容に関する写真
-

よどの里の外観です 市バスバス停からすぐです -

阪神電車姫島駅から徒歩7分です
空き人数
-
空き数/定員
2/100人 -
定員100人中、現在の空き数2人です。
(2025年10月25日時点)
サービスの内容に関する自由記述
入所さまの個別の介護計画を重視し、その方にあったケアプランを提供しています。
認知症の深い方でも適切な介護が行えるよう専門の療養棟(認知症専門棟)をもうけています。
サービスの質の向上に向けた取組
施設内委員会を重視して取り組んでいます。家族同士の交流を目的とした「やすらぎ会」や、認知症の市民公開講座(新型コロナウイルス感染症拡大以降、開催を中止しています)に取り組んでいます。施設内では感染対策委員会、褥そう防止委員会、栄養委員会などに全職員が活発に取り組んでいます。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
全職員に対して職員に対しての法人の理念、民医連の方針の学習を行っています。法人で毎年度学習テーマが決められ、複数回にわたり新人、中堅、ベテラン、職責者に対してそれぞれの難易度に合わせた学習会が実施されています。
必要に応じて事業所間の人事異動交流を行っています。法定研修を始め法人内研修、民医連としての定期的な研修制度の構築を行いキャリアパスに明記しています。
法人としてアシスタントワーカーを採用し、事業所への配置を行っています。職員募集の際は未経験、無資格者の採用検討を行い、要請があれば認知症介護基礎研修の受講を支援します。
インターンシップの受け入れや法人的に医療・介護の職業体験を主催し、多くの中高生が参加し好評でした。また、区民まつりや町会の夏祭りには積極的に参加し、地域住民に対しても施設の魅力を発信しています。
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
職員の資格取得、研修受講を積極的に推奨し、研修費の補助や貸与制度等を就業規則に明記し、キャリアアップしやすい環境を整えています。
就業規則に職種ごとの給与体系を記載しています。
メンター制度を導入し、定期的な面談等育成を支援する体制を整えています。
管理者による面談を年1回は必ず行い、キャリアアップに関する意向の確認や、体力的な面、精神的な面での悩みなどを聞き取り対応しています。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
介護休暇、育児休業制度等就業規則に明記しています
希望や必要に応じて勤務調整を行っています。今年度が時間有給制度が始まりました。パート職員に対する正規職員への採用試験を必要に応じて実施しています
基本的に希望に沿って有給休暇を与えています。法的に定められた最低5日間は大きく超える有給消化率となっています。
各勤務の業務を定めており、業務が俗人化して有給取得状況に偏りが出ないように配慮している
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
法人的に共済会を組織しており、医療費の助成や癒しの企画、文化行事や娯楽にかかる料金の補助(上限金額あり)等の福利厚生を充実させている。また、法人的にカウンセラーと契約しており、希望する職員がカウンセリングを受けられるように毎月複数回カウンセリング実施日を定めている。担当窓口に管理者が申し込むが、管理者にカウンセリングを受けることを知られたくない職員は自分で申し込むこともできるように連絡先をわかりやすい場所に掲示するとともに、各職員トイレの個室にも掲示している。また、法人でサポートチームを組織しており、匿名でラインで相談できる仕組みがある。産業医・保健師面談も必要に応じて実施している。
健康診断は全職員対象。ストレスチェックは週20時間以上の勤務者に実施している。
希望者には腰痛予防ベルトを支給しています。また、ノーリフティングの研修会等には積極的に職員を参加させています。また、管理者は管理者研修にて労務管理を学びます。
事業所における事故・拘束・虐待防止委員会での学習、労働安全衛生委員会における心理的安全性やクレーム対応に関する学習など実施。また、法人的にも介護安全委員会が設置されており、各事業所た他施設の事例を共有、学習している。マニュアルの整備も法人として実施している。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
業務改善委員会を立ち上げ、業務の見直しや新たなシステムの導入、効率的な利用など定期的に検討している
職員の時間外労働時間の精査を行い、原因の確定と改善に取り組んでいる。
職責者会議で5S活動を毎回議題にあげ、促進している。整理整頓のルールについてマニュアル化しているところである。
業務ごとのマニュアルの整備を行っている。作りっぱなしではなく定期的に見直し改定を行い、PDCAが回る仕組みの構築に取り組んでいる
介護ソフトほのぼのネクスト、ほのぼのケアパレットを導入しており、タブレットやスマートフォン等も使用している
見守りカメラ、赤外線センサーなどを使用し入所者の異変にいち早く気づけるように工夫している。特殊浴槽、リフト浴、マイクロバブル発生装置など使用し、利用者、職員共に入浴時の負担を軽減できるように工夫している
アシスタントワーカーを採用しており、タスクシフトを進めている
介護事業所で共通の委員会は法人的に委員会を設置し、法定学習会などは一括で実施できるように工夫している
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
職場会議を毎月各職場で開催しており、発生した課題や気づきに対してその都度話し合いを行っている。各職場の連絡ツールとしてラインを用いているが、職場ライン規定を作成し、個人が傷つくような書き込みは行わないなどルールを決めている。また行動指針に職員同士の相互理解を挙げており、常に相手から学ぶ姿勢を大事にしている。
区内の中学校から職業体験を毎年受け入れている。今年度は介護職体験だけではなく、老健に勤めるすべての職種について学んでもらえるようにプログラムを作成しているところである。また、地域の幼稚園から年複数回利用者との交流の機会を持っている。また、地域の子供たちに楽しんでもらうためのお祭り等も企画している。地域の健康福祉の増進に寄与するために出張学習会やフードバンクを開催するなど地域貢献を意識した活動を行っている。
我々の医療介護活動はすべて民医連綱領を実践するためにあるということを日頃から意識している。また施設の理念を今年度作成し直した。行動指針として利用者家族との共同の営みとしてのケアを掲げており、理念と行動指針はカードにして諸君が名札フォルダーに入れ常に意識できるように工夫している。
職員向けの新聞を発行しており、そこに好事例について掲載している
併設されているサービス
通所リハビリを併設しています。詳細は介護サービス情報公表でごらんください。
保険外の利用料等に関する自由記述
よどの里は1988年の開設時から「無料低額介護老人保健事業」の指定を受けています。経済的な理由で「介護サービスが受けられない」というようなことがないよう、利用者の介護を受ける権利=人権を守ります。
※無料低額介護老人保健事業とは老人保健施設の利用にあたり、経済的理由で費用の支払いが困難な方が、必要な介護サービスを受ける機会が制限されないように費用の減免を行う制度です。非課税世帯の方や、特別な事情により、支払いが困難な方などが対象となります。また申請には必要書類の提出と審査があります。よどの里では、申請をされる際には支援相談員がお話を伺い、公的な制度や社会資源の活用なども合わせてお手伝いいたします。詳細や申請方法については、ご遠慮なくご相談ください。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
教育研修を重視し、仕事のやりがいやモチベーションを高めています。そのため離職者はかなり少ないです。法人の在宅サービスの基幹職員として転出する事例も多数あります。新人教育を重視し、事例発表会や各種研究会の参加が活発です。また中堅職員においても研修を定期的に行っています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
入所者さまの多くは、近隣区に住んでおられる方です。そのため高齢であっても、障がいがあっても、住み慣れた地域で暮らしたいとの要望があります。この要望に応えるため施設入所、短期入所、通所リハビリ、訪問リハビリの提供を通じて在宅生活が継続できるよう取り組んでいます。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
9:00~17:00の日勤のほか、夜勤16:30~9:30、時差出勤があり、交代で勤務しています
賃金体系
法人規程で定められています。定期昇給・賞与・退職金あり。
休暇制度の内容および取得状況
有休は、概ね取得できています。
福利厚生の状況
非常勤も常時週20時間以上勤務の場合は健康保険加入。
離職率
法人内異動あり。離職率3%
その他
法人として「科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と権利の確立をめざします」という目標を掲げています