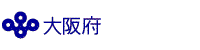2025年11月20日10:39 公表
ハートフルサンク
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
3/30人 -
最大受け入れ人数30人中、現在の受け入れ可能人数3人です。
(2025年09月30日時点)
サービスの内容に関する自由記述
・ワンストップサービスの実現
1.ケアプラン作成(居宅介護支援)
2.訪問介護
3.訪問看護
4.通所介護(堺市、和泉市をカバー)
5.福祉用具レンタル、販売
6.移動支援(介護タクシー等)
7.ニーズ・コーディネイション(後見、家具移動、庭手入れ、旅行付き添い等関係専門者と連携した保険外のサービス範囲の拡充)
サービスの質の向上に向けた取組
・高度事業 所資格の取得(高度資格人材配置基準などの充足)
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせた「混合介護」の提供によるニーズ対応力の進化
・SNS活用による利用者家族さまへのフィードバックや相談支援の拡充・強化
・外部専門講師などを招聘してのデイサービス内容のレベルアップ(認知防止など)
・総合事業に向けた自治会イベントやボランティアへの参加など地域密着活動の強化
- 取組に関係するホームページURL
-
-
株式会社ハートフルサンク
https://heartfulthank.com/
-
株式会社ハートフルサンク
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
ハートフルサンク居宅介護支援部門では、「ご利用者・ご家族の安心した在宅生活の継続」を理念に掲げ、ケアマネジャー一人ひとりが主体的に支援に関わる体制を整えています。
その実現のために、法人内で統一したケア方針と人材育成方針を定め、主任ケアマネを中心とした相談・助言体制を常時構築しています。さらにICTの積極活用(音声入力・AIによる記録補助等)により業務効率を高め、ケアマネジャーが利用者支援に集中できる仕組みを整備しています。
また、新人や経験の浅いケアマネジャーに対してはOJTと定期面談を組み合わせ、専門性の向上と定着を図っています。法人全体で「働き続けやすさ」と「成長の実感」を両立させることを重視し、採用後の離職防止にもつなげています。地域の事業所間での連携を重視し、法人内の訪問介護・訪問看護・福祉用具部門等と協働した採用活動を推進しています。合同説明会や施設見学の場を設けることで、幅広い人材に法人全体の魅力を伝える取組みを実施しています。
また、法人内ローテーション制度を設け、ケアマネジャーが他部署(訪問介護やデイサービスなど)の業務を一定期間経験できる仕組みを整備しました。これにより幅広い視点を持ったケアマネジャーの育成を実現しています。
研修については、法人内外の研修会に積極的に参加できる体制を整えるとともに、法人独自に「事例検討会」や「返戻対応共有会議」を実施し、スキルの底上げと情報共有を図っています。こうした共同体制により、採用から育成・定着までを一貫して支援する仕組みを構築しています。当法人では、多様な人材が活躍できるよう、介護業界未経験者や他産業からの転職者、子育て中・子育て後の主婦層、中高年齢者まで幅広く採用を行っています。採用にあたっては「人柄」と「利用者に寄り添う姿勢」を重視し、資格や経験の有無に関わらず応募いただける体制を整えています。
また、入職後は法人内の研修制度やOJT、主任ケアマネによる個別フォロー体制を活用し、無理なくスキルを習得できる仕組みを整備しています。これにより、異業種からの転職者も安心して定着・成長できる実績を重ねており、実際に現在も未経験からスタートしたケアマネジャーが第一線で活躍しています。地域とのつながりを重視し、中高生や専門学校生の職業体験の受け入れを積極的に実施しています。体験では、ケアマネジャーの業務内容や利用者支援の現場を知っていただくことで、介護業界の理解促進と将来の人材確保につなげています。
さらに、地域包括支援センターや自治会と連携し、地域行事や健康相談会、災害時対応訓練などへ積極的に参加・協力することで、法人としての社会的役割を発信しています。最近では、社内研修や返戻会議の取り組みを外部にも紹介し、ケアマネ業務のやりがいや専門性を広く地域に伝える活動を進めています。
こうした取組みにより、地域の方々にとって「身近で安心できる介護専門職」というイメージを醸成し、介護職の魅力度向上に寄与しています。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当法人では、職員のスキルアップを法人全体の成長と位置づけ、資格取得や専門研修の受講を積極的に支援しています。具体的には、介護福祉士実務者研修やユニットリーダー研修、認知症ケア研修、サービス提供責任者研修などの受講費用補助や勤務調整を行い、学びやすい環境を整えています。居宅介護支援部門においても、ケアマネジャーとしての実務能力向上に直結する外部研修やファーストステップ研修への参加を推奨し、法人内での事例検討会や返戻対応会議を通じて実践的なスキル習得を促しています。
研修受講は単なる知識習得にとどまらず、キャリア形成や人事評価に直結させています。法人内で定めたキャリア段位制度に基づき、各職員の成長段階を可視化し、研修参加実績や実務での活用度合いを人事考課に反映する仕組みを整備しています。これにより、研修を受けた職員が現場で学びを発揮しやすくなると同時に、昇格や処遇改善につながるモチベーションアップを実現しています。ケアマネジャーにおいても、主任ケアマネ取得や更新研修をキャリア評価とリンクさせ、専門職としての継続的成長を支援しています。
新規入職者や経験の浅いケアマネジャーに対しては、先輩職員がエルダー・メンターとして仕事面・メンタル面の双方をサポートする制度を導入しています。OJTだけでなく、定期的な振り返りや面談を通じて、不安や課題を共有しやすい環境を整備し、離職防止と早期戦力化につなげています。また、法人内での横のつながりを意識し、部署を越えた相談窓口を確保することで、孤立しやすいケアマネジャーの業務も安心して継続できる体制を整えています。
当法人では、ケアマネジャーを含む全職員に対して、上位者や管理者による定期的なキャリア面談を実施しています。面談では、個々の職員のキャリア形成や資格取得の計画、働き方の希望を確認し、具体的な支援策を共に検討しています。特にケアマネジャーについては、主任ケアマネ取得に向けたステップや、法人内での管理職候補としての育成計画を丁寧にサポートしています。こうした仕組みにより、職員が将来像を描きやすく、安心して長く働き続けられる環境を整えています。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
子育てや家族の介護と仕事の両立を支援するため、柔軟な休暇制度を整備し、家庭の事情に応じた働き方を尊重しています。育児休業や介護休暇の取得推進はもちろん、復職後も段階的に業務量を調整しながら安心して業務に復帰できる仕組みを整えています。また、法人全体として、子育て世代の職員同士が情報共有や相談を行える体制を設けており、互いに支え合う文化が根付いています。
当法人では、職員一人ひとりのライフステージに応じた働き方を実現するため、短時間正規職員制度を導入しています。これにより、子育てや介護、自己研鑽などの事情に応じた柔軟な勤務が可能となり、正規職員としての安定性と働きやすさを両立しています。さらに、非正規職員から正規職員への転換制度を整備し、本人の希望や勤務実績を尊重しながらキャリアアップを支援しています。こうした取り組みにより、長期的な定着とモチベーションの向上につながっています。
当法人では、有給休暇を「取りやすい・取りづらい」ではなく「当然の権利」として取得できる雰囲気づくりを大切にしています。毎年の取得目標を設定し、管理者が定期的に進捗を確認するとともに、身近な上司から積極的な声掛けを行っています。特にケアマネジャーは業務調整が難しい傾向がありますが、法人全体でバックアップ体制を構築し、1週間以上の連続休暇を含めて計画的に取得できるよう配慮しています。これにより、心身のリフレッシュを図り、長期的に安心して働き続けられる環境を整えています。
有給休暇の取得を阻害する要因の一つである「業務の属人化」を防ぐため、法人内での情報共有体制を徹底しています。記録のICT化や音声入力の活用、また複数担当制を導入することで、誰かが休んでも業務が滞らない仕組みを整備しました。これにより、業務の偏りを解消し、有給休暇を計画的かつ安心して取得できる環境を構築しています。
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
職員のメンタルヘルスや家庭の事情に寄り添うため、相談窓口を複数設置し、いつでも気軽に相談できる体制を整えています。管理者や主任ケアマネだけでなく、人財開発グループとも連携し、福利厚生制度や業務調整に関する相談も可能としています。これにより、心身の健康を維持しながら長期的に働き続けられる仕組みを構築しています。
当法人では、正規・非正規を問わず全職員が年1回の定期健康診断を受診できる体制を整えています。また、ストレスチェックを実施し、必要に応じて産業医や専門機関との連携を図ることで、早期対応に努めています。居宅介護支援部門では、在宅勤務や直行直帰が多い働き方の特性を踏まえ、オンライン相談窓口を設けるなど、メンタルヘルスケアにも注力しています。さらに、事業所内には休憩室を整備し、心身をリフレッシュできる環境を整えています。
法人全体として「職員の健康を守る介護技術習得」を重視しており、腰痛予防研修や福祉用具の正しい使用方法を学ぶ研修を定期的に実施しています。居宅介護支援部門のケアマネジャーも、現場職員の介助方法や最新の福祉用具の情報を学ぶことで、利用者支援の際に的確なアドバイスができる体制を整えています。さらに、管理者に対しては労務管理や雇用改善に関する研修を実施し、現場の負担を軽減できるよう組織全体で取り組んでいます。
職員が安心して業務に従事できるよう、事故・トラブル発生時の対応マニュアルを整備し、全職員が共有・理解できる体制を構築しています。居宅介護支援部門においても、利用者宅での緊急対応や情報共有の流れを明文化し、シミュレーション研修を行うことで即応力を高めています。また、インシデント事例を法人内で共有し、再発防止策を全体に展開する仕組みを構築しています。これにより、万一の際も迅速かつ適切な対応が可能となり、利用者と職員双方の安心につなげています。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
当法人では、厚生労働省が示す「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務効率化と質の向上を両立させる取組みを行っています。具体的には、委員会やプロジェクトチームを立ち上げ、ICT活用による記録業務の効率化、返戻対応の標準化、会議資料のデジタル化などを推進しています。また、外部研修や他法人との合同研修会に積極的に参加し、最新の事例やノウハウを取り入れることで、現場に即した業務改善を継続的に実施しています。
居宅介護支援部門では、日常的に発生する課題を「抽出→共有→改善」に落とし込む仕組みを整えています。業務時間調査や業務フローの可視化を行い、課題の構造化を進めることで、負担の偏りや無駄な作業を特定し、改善策を導入しています。特にケアマネジャー業務については、音声入力やAIを活用した記録補助を導入し、時間削減と質の確保を同時に実現しています。こうした仕組みにより、課題を「個人の悩み」で終わらせず、組織全体の改善につなげています。
法人全体で5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動を推進し、職場環境の整備を行っています。居宅介護支援部門でも、書類や記録の電子化と保管ルールの徹底を進め、誰もが必要な情報をすぐに取り出せる環境を整えています。また、定期的な職場点検や掃除当番表を活用し、清潔で安全な事務所環境を維持しています。こうした小さな積み重ねが、効率的で快適な職場づくりにつながり、結果として職員のモチベーション向上とサービスの質の向上を実現しています。
当法人では、業務の標準化と効率化を目的に、詳細な業務手順書を作成し、全職員に周知しています。さらに記録様式や報告フォーマットを工夫し、誰でも同じ品質で業務が遂行できる体制を整えています。これにより、属人化を防ぎ、休暇取得時や急な不在時でも円滑に業務が引き継げる仕組みを構築しています。
記録や情報共有、請求業務の効率化を図るため、介護ソフトを導入し、業務転記の手間を削減しています。また、全ケアマネジャーに Surface Pro 11やタブレット端末を貸与し、外出先や訪問先からもスムーズに記録入力や情報確認ができる環境を整備しています。さらに、ポケットWi-Fiを貸与することで、場所にとらわれない働き方を可能とし、即時性の高い情報共有を実現しています。
職員間の迅速な連携を図るため、法人内ではチャットツールを活用し、リアルタイムな情報共有を推進しています。さらに、「プラウドノート」を導入し、利用者情報の整理や研修での学びを蓄積・活用できる仕組みを整備しました。近年は生成AIを業務に取り入れ、音声データからの議事録作成や支援経過記録の効率化、サービス計画書の文案補助などに活用しています。これにより、職員の事務作業負担を大幅に軽減し、利用者支援にかけられる時間を増やすことにつなげています。
当法人では、業務改善と効率化を目的に各種委員会を設置し、法人横断的な課題解決を進めています。物品の共同購入や共通フォーマットの整備などにより、事務処理部門の集約化を図るとともに、ICTインフラや人事管理システム、福利厚生システムを法人全体で共通化しました。特に居宅介護支援部門では、こうした基盤を活かして業務の効率化を進め、利用者支援に集中できる環境を整えています。協働による体制づくりを通じて、職員の負担軽減と質の高いケアの両立を実現しています。
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
定期的に管理者会議や部門別ミーティングを行い、職員間の情報共有と相互理解を深めています。居宅介護支援部門では、ケース会議や返戻会議を通じて、利用者支援に関する課題を全員で検討し、知識やノウハウを共有しています。これにより、個々のケアマネジャーが抱える悩みを早期に解消し、働きやすい勤務環境の整備とケアの質向上につなげています。また、オンラインツールを活用した打ち合わせも導入し、リモート勤務者を含めた円滑なコミュニケーションを実現しています。
地域包括ケアの一員として、地域住民や学校との交流活動を積極的に実施しています。小学生の福祉教育への協力、地域行事への参加、住民向けの介護相談会などを通じて、介護の魅力や専門職としての役割を発信しています。職員にとっても地域住民からの感謝の声に触れる機会となり、やりがいの向上につながっています。こうした活動を継続することで、地域に根差した法人としての信頼を深め、職員のモチベーション維持・向上を図っています。
当法人では「利用者本位のケア」を理念に掲げ、全職員がその考えを共有できるよう定期的な学習機会を設けています。具体的には、介護保険制度の最新情報や法改正の内容を学ぶ勉強会を実施するとともに、法人のケア方針や人材育成方針についても研修や会議を通じて繰り返し周知しています。居宅介護支援部門では、ケース検討や事例発表を通じて「利用者の意思決定を尊重した支援とは何か」を職員全員で考え、日々のケアマネジメントに反映しています。
法人全体で、利用者やご家族から寄せられた感謝の言葉やケアの好事例を職員間で共有する仕組みを整えています。定例会議や社内チャットを通じて「うまくいった支援」や「感謝の声」を共有し、成功体験を職員全体のモチベーション向上につなげています。特に居宅介護支援部門では、利用者本位のケアが具体的にどう成果につながったかを事例として発表し合い、他の職員の参考や学びにしています。これにより、やりがいを実感できると同時に、法人全体として質の高いケアの継続に取り組んでいます。
併設されているサービス
介護でお悩みを抱えるご家族へのご相談を強化しています。専門コーディネイターが訪問し、多数の事例からベストソリューションを親身になって提供します。
・仕事と介護の両立
・仕事や家族の休養の確保(レスパイトニーズ)
・同居開始の検討
・認知症の兆候、重度化
保険外の利用料等に関する自由記述
保険外サービスについては専門コーディネイターを配置し、利用者様の様々なニーズにカスタマイズしてベストソリューションを提供します。
1.生活(家事援助(掃除など)、生活援助(調理など)、スポット援助(見守り、庭掃除、芝刈り)
2.お楽しみ(外出、旅行、家族イベントの同行、アレンジ等)
3.人生(成年後見支援、資産管理や処分、年金・贈与・相続等のコンサルティング支援を専門家と連携して支援)
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
・全員が地元出身。地域密着のカルチャーを体で体現、推進ができる。
・会社理念「自分の住み慣れた家で生活を快適に行う」介護、看護支援に共感したメンバーが集結している。
・ハートフルな利用者さま、家族さま支援を徹底的に行う。すなわちハートフル=「相手の気持ちに立ち誠実に心を込めた」サービス提供を全員が理解している。
・困難な事案に敢えてチャレンジすることも「ハートフル」の精神として近年、他所に先駆け率先して挑戦を推進している。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
・高齢者さま:軽度から重度の利用者の幅が広い。換言すれば、全ての利用者ニーズに応える用意がある(70歳~98歳、要支援1,2~要介護1,2,3,4,5)。
・障がい者さま:軽度から重度など利用者の年齢や支援ニーズの幅が広い(学生~高齢者、身体・精神障がい)。
・弊社のハートフル支援を一度受けると他所に移るといったケースが著しく低い(既存利用者の満足度が高い)。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
・勤務時間8:30~17:30
・月曜日~金曜日(土曜日) 祝日休
・8/13-15 、 1/1-3 休日
・訴求したい特徴:
残業なし(ICT活用による生産性徹底)、法定有給休暇全日取得促進、フレックス制度
賃金体系
基本給 昇給制度 各種役職手当 年二回賞与 月間社長賞 インセンティブ制度など各種表彰制度あり
休暇制度の内容および取得状況
年次有給休暇取得制度あり。
法定有給休暇全日取得促進目標に向かい体制強化中。
福利厚生の状況
健康保険 雇用保険 厚生年金 交通費支給 定期健康診断 出産手当支給あり シャワー室完備 資格取得支援(ヘルパー2級 介護福祉士取得にむけた実務者研修 主任介護支援専門員)
離職率
社員離職ゼロ、利用者家族介護離職ゼロが当社の目標です
(離職率):0%
(内訳)一年間の離職者数が0人、一年前の在籍者数が8人
(計算式):0%=0人÷10人×100