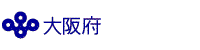2025年11月20日10:41 公表
はーとらんど居宅介護支援事業所
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
10/155人 -
最大受け入れ人数155人中、現在の受け入れ可能人数10人です。
(2025年10月15日時点)
サービスの内容に関する自由記述
ケアマネジャーが自宅を訪問して本人や家族様の困り事をお聞きし、在宅生活が安心して送れる様に相談・検討を行ないます。
本人、家族様の意向を尊重し、支援に必要なサービス事業所を複数紹介するとともに各事業所との連携を図り、サービス計画を作成してサービスの利用をしていただきます。
地域で困っている方がおられた場合は、地域包括支援センターと連携を行ない、住み慣れた地域で誰もが安心して生活が送れるよう働きかけていきます。
サービスの質の向上に向けた取組
様々な研修会の参加や事業所内の研修を行い、スキルアップに努めています。公正中立な立場でサービス事業所の提案を行い、本人や家族が望む生活が実現できるように支援しています。
- 取組に関係するホームページURL
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
法人の経営理念、運営方針、各部門の運営方針を掲示し、朝礼時、唱和にて周知を図っています。
人材育成面では 「部門目標管理、個人業務目標管理、部門・個人別教育計画、個人業績評価」制度を関連付けて資質の向上を図っています。「新卒者だけでなく、20代~70代までの職員を幅広く募集している。その方の能力が発揮できる現場を提案し、職員が自身の生活や家庭と、仕事のバランスがとれるよう配慮している。
未経験の方にも初任者研修を含め、OJTを中心にエルダー制度を導入し、スキルや経験に応じた業務指導を行い、職場全体でフォローアップしている。
法人全体では65歳の定年以上で雇用している方は17名になり、より経験豊富な職員が、お互いにノウハウを教え学びあい幅広い感性を身に着けられるようにしている。法人として、職場体験やボランティアの受け入れは随時行っている。大阪府の職場体験事業に登録し、介護だけでなく事務や営繕などに触れて、業務のイメージがしやすく工夫している。
地域活動として、子ども食堂の運営や認知症カフェを月1回開催し、地域の方が集える場の環境づくりを行っている。また、在宅介護支援センターを担っており、区の高齢者関係者会議に出席、地域包括ケア推進に向けた地域課題の検証やその解決のために、地域包括支援センターや民生委員など第一線で地域福祉に取り組む団体と協議し、認知症の方への見守り事業展開などを行っている」 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
職員は事業所に必須の資格にとどまらず、より専門性の高い知識習得とその活躍の場を目指して
日々研修や自己研鑽に励んでいる。
資格取得支援制度として「はーとらんど資格取得等スキルアップ支援規程」等があり、資格取得の受験費用の半額負担や、研修費を最高額20万円まで支給します。研修の受講は、個人研修計画に基づき、今年度習得すべき研修、資格の更新などを定めている。
キャリアは、初任者から始まり初級、上級と一般職を経て、管理職、経営職と上位に挑戦できる機会を準備している。上位職は、事業所の経営目標や事業計画の策定承認も担っている。
人事考課は一次段階で個人業績評価シートを作成し、自身が設定した年間目標である業務目標管理シートに査定を行う。それを以て、主任・管理者が面談を通じて二次査定を行い、最終、経営者査定を行う。キャリアアップ等に関する定期的な相談機会として、年に一度、上位者による「個人業務目標管理シート」人事評価制度に基づく個人面談を実施し、資質の向上をはかっています。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
育児・介護休業等に関する規則に定めるように、育児休業、介護休業を取得する職員を職場全体で支える仕組みを構築している。育児休業取得者は昨年度1名あり、女性だけでなく男性の育休も
取得しやすい職場環境を整備している。柔軟な勤務態勢を可能にするために、次月の勤務表作成前に、各自の希望を確認し、正式勤務表を作成している。また正規職員への転換については「パート就業規則」に正職員等への転換を規定している。
有給休暇取得促進のために、半日有給制度を設けている。また有休が取得しやすいように複数担当制とし、利用者が困らないように、他の職員で対応できるようにしている。
基本勤務表に前もって有給申請を行った日に有給取得を認めている。個人や家庭の事情で有休日が急に変更になっても柔軟に対応できるように、担当利用者以外の情報も共有して休んでも支障が無いように取り組んでいる
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
月1回理事長の個人面談日を設定。だれでもいつでも相談できるよう、時間をとっている。
メンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施。個人のプライバシーに配慮したウェブ検査を導入することで、自身のメンタルヘルスを把握できるとともに、産業医に相談したり治療できる環境を整備している。職員の健康管理体制として、健康診断、インフルエンザ等の予防接種に産業医等が来訪し、全員が受診している。またストレスチェック実施規程があり、2年に1回実施。昼食時の休憩場所として多目的ルームを開放している。
法人全体で、事故感染症などの対応マニュアルを整備している。特に全体に関わることや職員が守るべき安全マニュアルについては、安全衛生委員会を通じて作成している。
感染症対策など基本的な考えや指針が変更になった場合は都度情報提供し、各事業所で制定したマニュアルが効果的に活用できるように確認、指導をしている。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
生産性向上のための最も身近にできる取り組みとして5Sを推進している。整理整頓は毎月整理整頓の日を決めて、事業所内での共通の物品管理や使いやすい工夫を見直す機会を作っている。
職場環境と情報面での5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の更なる実践に取り組んでいる。各種マニュアルの作成や既存の様式変更など随時見直しを実施している。
平成30年度からICTを導入し、タブレット端末、スマホ端末を活用している。更なる情報の共有化とペーパーレス化に取り組んでいる。
委員会として安全衛生委員会、美化マナー委員会、広報委員会、子ども食堂ふれあいカフェ委員会を設置。各事業所から数名ずつ参加し年間の活動目標を定め、委員会を開催。全体内部研修で法定研修の企画や開催、研修後のフォローアップまでを行っている。
物品の購入は、消耗品に関しては、事業所で個別に発注する物と、全体でまとめて購入する物などわけている。
福利厚生は一覧表にまとめ、職務に応じて利用できるように情報提供を行い随時活用している。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
毎週実施しているミーティングで、業務改善について全職員で話し合っている。
地域包括ケアの一員としてのモチベーションを上げるために、堺市認知症カフェや子ども食堂を開催し、また地域のおしゃべり喫茶やサロンにも出かけ地域密着型の福祉を目指しています。
毎月2回運営方針と理念の唱和するとともに、事業所内に掲示している。
利用者や家族からのお礼の手紙を朝礼で紹介している。
併設されているサービス
ケアハウス・通所介護・訪問介護・在宅介護支援センターが併設されていて各部署との連携を強化し利用者様に多方面からのサービスを行っている。
保険外の利用料等に関する自由記述
保険外サービスについては、ご本人の要望や、専門的立場から必要性がある場合に応じてケアプランに反映させています。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
介護保険制度がスタートした時から本事業を開始し、現在は4名のケアマネジャーが在籍、そのうち主任介護支援専門員2名で活動しています。
色々な経験を積んだスタッフがチームとなり、利用者や家族の気持ちに寄り添った支援ができるように努めています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
介護保険を利用しながら住み慣れた自宅で過ごすことを希望されている利用者が多いです。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
勤務時間は8時30分~17時30分(内、休憩1時間)です。年間休日が122日と多くあります。
祝祭日も営業しております。(12月31日~1月2日はお休みを頂戴しております)
賃金体系
平成27年10月に賃金体系を新しく改定しました。
資格手当も創設し、キャリアアップに繋がるように考慮しています。
休暇制度の内容および取得状況
法定の有給休暇は勿論、結婚や忌引の特別休暇、育児休業、介護休業があります。
有給休暇は就業開始月から取得できるように就業規則を設定しています。
年間休日は122日をとれるようになっています。半日の有給休暇取得可能です。
福利厚生の状況
大阪民間社会福祉事業者共済会および堺市中小企業勤労者福祉サービスセンターに加入しています。
はーとらんど資格取得等スキルアップ支援規程を制定し、資格取得やスキルアップ支援を行っています。
離職率
(法人全体の離職率):10%
(内訳)1年間の離職者数が 5人 1年前の在籍者が50人
(計算式)10.0% = 5人÷50人×100
2025/4/1現在