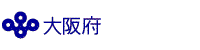2025年11月05日17:56 公表
グループホームアイケア服部
| 介護サービスの種類 |
認知症対応型共同生活介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町1丁目11番6号
|
| 連絡先 |
Tel:06-6867-0077/Fax:06-6867-0073
|
空き人数
-
空き数/定員
0/18人 -
定員18人中、現在の空き数0人です。
(2025年10月16日時点)
サービスの内容に関する自由記述
当事業所では、家庭的な雰囲気の中で利用者一人ひとりの生活リズムや希望を尊重し、安心して暮らしていただけるよう支援しています。食事・入浴・排泄などの日常生活援助に加え、個別性を大切にした介護サービスを提供しています。認知症ケアに重点を置き、専門研修を受けた職員が中心となって声かけや関わり方を工夫し、穏やかに過ごせるよう配慮しています。レクリエーションや季節行事、地域との交流を取り入れることで生活の楽しみを持っていただき、心身の活性化につなげています。また、医療機関や地域包括支援センターとの連携を密にし、健康管理や緊急時の対応にも備えています。
サービスの質の向上に向けた取組
当事業所では、利用者一人ひとりが安心して生活できるよう、サービスの質の向上に向けた取り組みを継続的に行っています。定期的に職員会議や委員会を開催し、事故防止、不適切ケア防止、感染症対策などについて情報共有と改善を図っています。また、介護技術や認知症ケアに関する研修を計画的に実施し、職員の知識・技術の向上に努めています。利用者やご家族からのご意見は意見箱や窓口で受け付け、速やかに対応するとともに、再発防止やサービス改善につなげています。さらに、ヒヤリハットや事故報告の記録を分析し、原因を検討した上で改善策を取り入れることで、安全で質の高いケアの提供を目指しています。。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
当事業所は「愛あるケアでゆとりとくつろぎの毎日を」を運営理念とし、利用者様の基本的人権を尊重し、その人らしい暮らしを支えること、安心できる家庭的な生活の提供、生き甲斐を持った生活の実現を基本方針としています。そのために、認知症ケアを重視した個別支援や行事・レクリエーションによる生活の潤いづくりを行い、職員には定期的な研修や資格取得支援を実施し人材育成を図っています。また、虐待防止・身体拘束適正化・感染対策等の委員会活動や事故・ヒヤリハットの分析、意見箱を通じた利用者・家族の声の反映などを仕組みとして取り入れ、サービスの質の向上と安心できる環境づくりに努めています。
当事業所では、介護経験や資格の有無にかかわらず、他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者など幅広い層の採用を行っています。経験者・有資格者だけにこだわらず、入職後の研修やOJTを通じて知識と技術を身につけられる仕組みを整えており、実際に異業種からの転職者や子育てを終えた主婦層の方々が活躍しています。こうした多様な人材の受け入れにより、チームに多様な視点が加わり、利用者一人ひとりに寄り添ったサービス提供につながっています。
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当事業所では、より専門性の高い介護技術を習得しようとする職員にはユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、認知症ケア研修の受講を推奨・支援しています。また、中堅職員に対してはマネジメント研修の受講を支援し、将来的なリーダー人材の育成に取り組んでいます。
-
当事業所では、職員のキャリアアップや働き方に関する相談機会を確保するため、上位者や担当者による面談を定期的に実施しています。年1回以上のキャリア面談を通じて、本人の希望や課題を把握し、研修受講や勤務体制の調整などに反映しています。また、日常業務の中でも管理者やリーダーが相談に応じやすい環境を整え、職員一人ひとりが安心して働き続けられる体制づくりに努めています。
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりのために具体的な取得目標を定め、取得状況を定期的に確認するとともに、身近な上司が積極的に声かけを行い、職員が安心して休暇を取得できる環境づくりに努めています。
当事業所では、有給休暇の取得を促進するため、情報共有や複数担当制を導入し、業務の属人化や配分の偏りを解消することで、誰もが休暇を取りやすい環境づくりに努めています。
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
当事業所では、業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等に関する職員相談窓口を設け、相談体制を充実させることで、職員が安心して働ける環境づくりに努めています。
当事業所では、介護職員の身体的負担を軽減するために介護技術の修得支援を行うとともに、職員に対する腰痛対策研修や、安全で働きやすい職場環境の整備に努めています。
当事業所では、事故やトラブルが発生した際に迅速かつ適切に対応できるよう、対応マニュアルを整備し、全職員に周知しています。転倒・転落・誤薬・誤嚥・利用者間のトラブルなど想定される事例ごとに対応手順を定め、発生時には利用者の安全確保を最優先に、速やかに医療機関や家族への連絡を行うとともに、事故報告書を作成し記録を残しています。
また、発生した事例については管理者を中心に原因分析を行い、再発防止策を検討・共有する仕組みを整えています。ヒヤリハット事例も含めて定期的に振り返りを実施し、重大事故の未然防止につなげています。さらに、職員研修においてマニュアルに基づく対応や事例検討を行い、全職員が統一した対応を取れるよう体制の維持・改善に努めています。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
現場の課題を明確化するため、課題の抽出や構造化を行い、業務時間の調査などを通じて業務の状況を把握し、改善につなげています。
職員が報告しやすい環境を整えるため、ヒヤリハットの記載方法を簡略化し、誰もが短時間で記録できる仕組みとすることで、情報の蓄積と共有を促進し、事故防止やサービス改善につなげています。
介護記録の効率化と情報共有の円滑化を図るため、記録・情報共有・請求業務において転記を不要とする介護ソフトを導入しています。また、タブレット端末を活用し、現場での記録入力や情報確認を可能とすることで、業務の効率化と職員の負担軽減を実現しています。
当事業所では、職場環境の改善を目的として、協働化による効率化と質の向上に取り組んでいます。具体的には、虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会・感染症対策委員会等の各種委員会を法人内で共同設置し、指針や計画についても共同で策定しています。また、物品の共同購入を行うことでコスト削減を図るとともに、ICTインフラの共同整備、人事管理システムや福利厚生制度の共通化を進めています。これらの取り組みにより、職員の事務負担軽減と働きやすい職場環境づくりを推進しています。
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
当事業所では、定期的なミーティングを実施し、職場内のコミュニケーションを円滑にすることで、介護職員一人ひとりの気づきや意見を共有する体制を整えています。ミーティングでは、日々の業務で得られた利用者への対応に関する工夫や課題、事故やヒヤリハット事例の振り返り、勤務環境に関する改善提案などを取り上げています。
出された意見は記録に残し、改善点については実際のケアや業務体制に反映し、その効果を次回のミーティングで検証する仕組みとしています。また、職員が安心して発言できる雰囲気づくりを心がけ、上下関係にとらわれず意見交換ができるよう配慮しています。
このように、職員同士の気づきを積極的に活かし、勤務環境やケアの質を継続的に改善することで、利用者にとってより安心で快適な生活環境を提供できるよう努めています。当事業所では現在、地域住民や関係者との関わりとしては運営推進会議の開催が中心となっていますが、今後は地域包括ケアの一員としての役割を果たすため、児童・生徒や地域住民との交流の機会を積極的に実施できるよう、関係機関との調整を進めてまいります
当事業所では、介護保険制度の理念や法人の運営理念を踏まえた「利用者本位のケア方針」を常に意識した支援を行うため、定期的に学ぶ機会を設けています。具体的には、全体研修や職員会議において制度改正や法人理念を取り上げ、事例検討を通じて理解を深めています。これにより、職員一人ひとりがケアの基本姿勢を再確認し、日常業務の中で利用者様の尊厳を尊重した支援が実践できるよう取り組んでいます。
職員のモチベーション向上とサービスの質の向上を図るため、ケアの好事例や利用者・ご家族からいただいた謝意の言葉などを職員間で共有する機会を設けています。定例ミーティングや研修の場で事例を紹介し合うことで、良い実践を全体で学び、日々の業務に活かすとともに、職員がやりがいを感じながら働ける環境づくりに努めています。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所には、長年にわたり介護に携わってきた経験豊富な職員が多く在籍しており、培ってきた知識と技術を日々のケアに活かしています。若い職員は少ないものの、その分ベテラン職員による落ち着いた対応や安定したケアが、当事業所の大きな強みとなっています。また、すべての職員が介護福祉士、初任者研修、実務者研修、認知症介護基礎研修、認知症ケア専門士、介護支援専門員など、いずれかの資格を有しており、専門性の高い支援を提供しています。さらに、外国籍の職員を含め、多様な背景を持つスタッフが互いに協力し合いながら、利用者一人ひとりに寄り添った温かいサービスを実践しています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
当事業所の利用者は、主に認知症の診断を受けた高齢の方々であり、それぞれの生活歴や価値観を大切にしながら日々を過ごされています。サラリーマン、商売、子育てなど多様な人生経験を持つ方が多く、会話や交流の中でその豊かな経験が活かされています。施設での生活においては、共同生活の中で互いに声をかけ合い、助け合いながら穏やかに過ごされる方が多いことが特色です。また、季節行事やレクリエーションを楽しみにされる方が多く、歌や体操、家事活動などにも積極的に参加されています。全体として、家庭的で落ち着いた雰囲気の中、個々の力を発揮しながら生活されているのが特徴です。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
当事業所の勤務時間は、原則として 1日8時間・週40時間以内 としており、シフト制で運営しています。基本の勤務帯は以下の通りです。
早出:8:00~17:00
日勤:8:30~17:30
遅出:10:00~19:00
夜勤:16:30~翌9:30
ケアの詳細(具体的な接し方等)
行事等のイベントの計画、記録
当事業所では、利用者様に四季を感じていただき、生活に楽しみや潤いを持っていただけるよう、年間行事計画を策定し、誕生日会や季節の行事(花見、夏祭り、敬老会、クリスマス会など)を実施しています。行事は事前に職員間で準備や役割分担を行い、安全面や感染症対策にも配慮しています。実施後は写真や記録を残し、職員会議や運営推進会議において振り返りを行い、次回の計画に活かしています。また、記録はご家族や地域への情報提供にも活用し、施設の透明性と信頼性を高めています。
利用者の一日の流れ
6:00~7:00 起床・整容
職員が声かけや見守りを行いながら、洗面・着替えなどを行います。
8:30~9:30 朝食
食事の配膳・介助を行い、服薬確認もあわせて実施します。
9:30~11:30 午前の活動
バイタル測定、体操、散歩、入浴、個別リハビリ、趣味活動などを行います。
12:00~13:00 昼食
バランスの取れた食事を提供し、服薬管理や口腔ケアも実施します。
13:30~15:00 午後の活動・レクリエーション
ゲーム、制作活動、音楽、地域交流などを通じて心身の活性化を図ります。
15:00~15:30 おやつ
会話を楽しみながらお茶やお菓子をいただきます。
16:00~17:00 体操や自由時間
体操や読書、テレビなどで過ごされます。
17:00~18:00 夕食
家庭的な雰囲気の中で食事をとり、服薬確認や口腔ケアも行います。
18:00~21:00 くつろぎ・就寝準備
テレビ鑑賞、会話など自由に過ごした後、整容や排泄介助を行い就寝準備をします。
21:00以降 就寝
消灯後も職員が巡回・見守りを行い、夜間の安全を確保します。
入浴形態(一般浴、機械浴)
機械浴