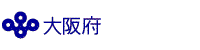2025年11月05日17:32 公表
ケアプランセンターラプラージュ
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
4/160人 -
最大受け入れ人数160人中、現在の受け入れ可能人数4人です。
(2025年09月22日時点)
サービスの内容に関する自由記述
利用者様の残存する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、
ご本人やご家族の話に耳を傾けながら、丁寧で迅速な対応を心掛けております。
サービスの質の向上に向けた取組
サービスの質の向上に向けた取組として、職員同士が日々、情報や知識を積極的に交換し合いながら、より良い支援につながるよう連携して業務に取り組んでいます。
また、医療介護連携に関する研修等にも積極的に参加し、医療関係者との連携強化や、円滑な情報共有体制の構築を図っています。認知症や虐待などの困難事例に対しては、地域包括支援センターと連携し、適切かつ迅速な対応ができるよう努めています。さらに、法人内で実施される研修や、他法人と連携して開催される事例検討会等にも継続的に参加し、専門職としての知識・技術の向上に取り組んでいます。こうした取組を通じて、質の高いケアマネジメントの提供と、利用者一人ひとりに寄り添った支援の実現を目指しています。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
在宅勤務制度を導入し、職員が育児・介護等と仕事を両立できる柔軟な働き方を推進しています。
有給休暇を時間単位で取得できる制度を導入し、職員が家庭や私用に合わせて、必要な時間だけ柔軟に休暇を取得できる環境を整えています。
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
在宅勤務体制に加え、事務所には1人1台のデスク・パソコンを整備。スマートフォンも職員に1台ずつ貸与し、ICT環境を充実させています。
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
当事業所では、毎月1回の「相互点検」を実施しています。これは、法令遵守の意識を高めるとともに、ケアマネジャー同士が学び合える仕組みとして取り組んでいるものです。各ケアマネジャーが1名の利用者を選び、その方のアセスメント・ケアプラン・サービス担当者会議録等の一連の書類について、お互いに確認・点検し合う形で行っています。第三者の視点が入ることにより、自身では気づきにくい点の見直しが可能となり、記載内容の精度や言い回しの工夫など、他のケアマネジャーの良い点を学ぶ機会となっています。これにより、業務の質の向上やスキルアップにもつながっており、スタッフ同士が切磋琢磨できる環境づくりにつながっています。また、当事業所では在宅勤務を導入しているため、全員が常に同じ場所で業務を行うことが難しい状況にあります。そうした中でも、週に1回は必ず全員が集まり、顔を合わせてミーティングを行う機会を設けています。この時間を活用し、気軽な相談や情報共有を行うことで、業務の連携を強化しています。定期的に対面でコミュニケーションを取ることで、在宅勤務下でもチームとしての一体感を維持することにつながっています。
併設されているサービス
・特養 : 特別養護老人ホーム ラプラージュ(施設入所・ショートステイ)
・デイサービス: 老人デイサービスセンターいちご
・訪問介護 : ヘルパーステーションラプラージュ
保険外の利用料等に関する自由記述
なし。
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所には4名の女性ケアマネジャーが在籍しており、そのうち3名は主任介護支援専門員の資格を有しています。在宅勤務を取り入れている中でも、より良い支援の実現に向けて職員が連携して取り組んでおり、グループLINEなどを活用して必要に応じて情報共有を行っています。また、週に一度の対面ミーティングを実施しており、日頃から気軽に相談し合える雰囲気があります。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
利用者層としては、65~74歳が16人、75~84歳が66人、85~94歳が88人、95歳以上が12人と、75歳以上の方が大半を占めており、高年齢層のご利用者が多いのが特徴です。
また、独居や高齢者のみの世帯や生活保護受給者など、多様な生活環境にある方が多く、医療的ケアや生活支援などさまざまなニーズが見られます。
ターミナル期にあるご利用者もおり、在宅で最期まで過ごすことを希望されるケースも一定数存在します。