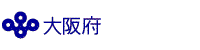2025年11月05日17:15 公表
レコードブック弥刀
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
15/15人 -
最大受け入れ人数15人中、現在の受け入れ可能人数15人です。
(2025年09月28日時点)
サービスの内容に関する自由記述
機能訓練を中心とした3時間のリハビリ型デイサービスです。 利用者さまの「身体機能」や「健康」の維持・回復・改善を目的に、ご自身の能力を最大限に引き出す運動プログラムを提案・実践を行い、健康的な生活を長く続けていただくためのお手伝いをする施設です。
サービスの質の向上に向けた取組
当事業所では、利用者様一人ひとりの生活の質(QOL)の維持・向上を目指し、AI技術を活用した歩行解析システムを導入しております。これにより、歩行時の姿勢・バランス・左右差・重心移動などを可視化し、専門スタッフが分析を行った上で、個別の運動メニューを提案しています。提案内容は、既往歴・現病歴・現在の身体状態を踏まえ、無理なく継続できる運動を中心に構成されており、ご自宅でも取り組めるよう配慮しています。
また、運動プログラムの質的向上を図るため、社内にて定期的なトレーニング研究会を開催し、最新の介護予防運動やリハビリ技術の情報共有を行っています。特に、体幹・下肢筋力・バランス能力の強化を目的とした椅子に座って行う全身運動を中心に、科学的根拠に基づいたメニューの開発・改善に努めています。
さらに、ケアマネジャー様、福祉用具のご担当者様、医療関係者の皆様と連携し、“福祉のワンチーム”として支援体制を構築。利用者様の生活環境やご希望を尊重しながら、安心して通所いただけるよう、スタッフ一同心を込めてサポートしております。
今後も、ICTやAIの活用を通じて、より精度の高い評価と提案を行い、介護サービスの質の向上に努めてまいります。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
当事業所では、「すべての人が、自分らしく、安心して暮らせる社会の実現」を理念に掲げ、利用者様の尊厳を守りながら、心身の健康と生活の質(QOL)の向上を目指した支援を行っています。特に、科学的根拠に基づく介護予防の実践に力を入れており、AI技術を活用した歩行解析システムを導入。歩行時の姿勢・重心移動・左右差などを可視化し、専門スタッフが分析を行った上で、個別の運動メニューを提案しています。
運動メニューは、既往歴・現病歴・現在の身体状態を踏まえ、無理なく継続できる内容で構成されており、ご自宅でも取り組めるよう配慮しています。椅子に座って行う全身運動を中心に、体幹・下肢筋力・バランス能力の強化を目的としたプログラムを提供。前半は上半身、後半は下半身に分けて構成し、各パートの最後には有酸素運動として足踏みを取り入れています。
また、サービスの質向上を目的に、社内で定期的なトレーニング研究会を開催。最新の介護予防運動やリハビリ技術の情報共有を行い、スタッフの専門性向上とケアの質の均一化を図っています。新人研修やOJT制度も整備し、段階的なスキル習得を支援。職員評価制度も導入し、専門性・協働性・利用者満足度などを指標に、成長を促しています。
さらに、ケアマネジャー様、福祉用具のご担当者様、医療関係者の皆様と連携し、“福祉のワンチーム”として支援体制を構築。利用者様の生活環境やご希望を尊重しながら、安心して通所いただけるよう、スタッフ一同心を込めてサポートしています。今後もICTやAIの活用を通じて、より精度の高い評価と提案を行い、介護サービスの質の向上に努めてまいります。当事業所では、介護人材の多様性を尊重し、経験や資格の有無にこだわらない幅広い採用を積極的に行っています。実際に、採用年齢は18歳から65歳までと幅広く、若年層から中高年齢者まで、それぞれのライフステージに応じた働き方を支援しています。
採用対象は、介護業界未経験者や無資格者はもちろん、他産業からの転職者、子育てを終えた主婦層、定年後も社会参加を希望するシニア層など多岐にわたります。これにより、職場には多様な価値観や経験が集まり、利用者様への支援にも幅と深みが生まれています。
未経験者には、入職時から段階的に学べるOJT制度や、介護技術・接遇・認知症ケアなどを学べる社内研修を整備。資格取得を目指す職員には、外部研修の紹介や費用補助制度も活用し、キャリアアップを支援しています。
また、年齢や経験に応じた業務分担や勤務形態の柔軟化にも取り組んでおり、短時間勤務や曜日固定勤務など、家庭や健康状態に配慮した働き方が可能です。これにより、離職率の低下と職員の定着につながっています。
今後も、「人柄・意欲・協調性」を重視した採用を継続し、介護業界の裾野を広げるとともに、誰もが安心して働ける職場づくりを推進してまいります。 - 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
当事業所では、職員のキャリア形成と専門性向上を支援するため、働きながら資格取得を目指す職員に対して、積極的な研修受講支援を行っています。実際に、職員の原和也は、業務と並行して社会福祉主事任用資格の通信講座や認知症ケア講座を受講し、資格取得に至りました。こうした取り組みは、職員の意欲を尊重し、学びの機会を保障することで、サービスの質向上にもつながっています。
介護福祉士取得を目指す職員には、実務者研修の受講支援を行っており、勤務調整や費用補助などを通じて、学習と業務の両立を支援しています。また、より専門性の高い介護技術を習得したい職員には、ユニットリーダー研修やファーストステップ研修、喀痰吸引研修、認知症ケア研修などの外部研修への参加を推奨し、必要に応じて受講費用の一部を事業所が負担しています。
さらに、レコードブック本部によるトレーナー研修、相談員研修、管理者研修など、多種多様な社内研修制度も活用しており、職員の役割やキャリアに応じた学びの場を提供しています。これらの研修は、運動指導・接遇・マネジメント・法令遵守など幅広い内容を含み、実践的かつ継続的なスキルアップを支援しています。
中堅職員に対しては、マネジメント研修の受講を促進し、チーム運営や後輩指導、業務改善などの能力向上を図っています。これにより、現場のリーダー層が育ち、職場全体の安定と成長につながっています。
今後も、職員一人ひとりの成長を支える制度づくりを進め、介護の専門職として誇りを持って働ける環境を整備してまいります。当事業所では、職員の成長とサービスの質向上を両立させるため、研修受講とキャリア段位制度、人事考課を連動させた仕組みを構築しています。職員の職位は、業務遂行能力・研修受講歴・評価項目の達成度・推薦などを総合的に判断し、段階的に昇格する制度となっています。
基本となる「キャリアパス表(トレーナー)」では、等級ごとに求められる業務内容・職責・必要な研修・能力が明確に定義されており、職員は自身のキャリア目標に向けて、段階的にスキルを習得していきます。例えば、A1級職員に昇格するためには、OJT・OFFJT・認知症基礎研修・法人内研修への積極的参加が求められ、さらに介護技術・接遇・記録作成・送迎方法・コミュニケーション力などの能力習得が条件となります。
評価は、所属長(S2・S1・SS級)によるチェック項目に基づく評価と、施設長による総合判断によって行われ、昇給・昇格に反映されます。また、主任・課長・部長の推薦も昇格の重要な要素となっており、現場での信頼と実績が重視される仕組みです。
研修については、法人内外の研修を積極的に活用しており、認知症ケア・喀痰吸引・サービス提供責任者研修・ユニットリーダー研修・マネジメント研修など、職位や役割に応じた内容を提供しています。特に中堅職員には、マネジメント力や部下育成力を高める研修を推奨し、組織運営の中核を担う人材の育成に力を入れています。
また、研修修了者には資格手当の支給や、評価項目での加点があり、学びが直接的に処遇改善につながる仕組みとなっています。実際に、原和也職員は社会福祉主事任用資格や認知症ケア講座を修了し、職位向上と業務の幅の拡大を実現しています。
今後も、職員の意欲と能力を正当に評価し、研修とキャリア形成が連動する制度を継続・発展させてまいります。当事業所では、職員一人ひとりのキャリア形成と働き方の最適化を支援するため、定期的な相談機会の確保に努めています。社員教育・業務顧問として今泉様を迎え、月に1回Zoomによるオンライン会議を実施。この場では、業務改善・人材育成・職場環境の整備などについて意見交換を行い、職員の声を反映した運営を推進しています。
さらに、年2回のキャリア面談を実施しており、職員が自身の業務状況や今後のキャリア、働き方に関する希望を上位者と直接話し合える機会を設けています。面談では、キャリアパス表をもとに、現在の職位や評価、今後の目標、必要な研修やスキルについて確認し、個別の成長支援計画を立案しています。
これらの取り組みにより、職員は自身の成長を実感しながら働くことができ、モチベーションの向上と定着率の改善につながっています。今後も、相談機会の充実とフィードバック体制の強化を図り、職員が安心して長く働ける職場づくりを進めてまいります。 - 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
当事業所では、職員のライフスタイルや家庭事情、健康状態などを考慮し、柔軟な勤務体制の整備に取り組んでいます。特に、パート介護職員や看護師に対しては、勤務開始・終了時間や休日を本人の都合に合わせて調整しており、育児・介護・通院などの事情にも配慮した働き方が可能です。
また、短時間勤務を希望する職員に対しては、短時間正規職員制度の導入を進めており、安定した雇用と処遇の確保を図っています。これにより、フルタイム勤務が難しい職員でも、正規職員としてのキャリア形成が可能となり、職場への定着と意欲向上につながっています。
さらに、非正規職員から正規職員への転換制度も整備しており、一定の勤務実績や評価、本人の希望に基づいて、正規登用の機会を提供しています。登用にあたっては、キャリアパス表や人事考課制度を活用し、業務遂行能力・研修受講歴・職場での貢献度などを総合的に判断しています。
これらの制度は、職員の多様な働き方を支援し、長期的な雇用の安定とサービスの質向上を両立させるための重要な取り組みです。今後も、職員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを進めてまいります。当事業所では、職員が心身ともに健康に働き続けられるよう、有給休暇の取得を促進するための環境整備と意識づくりに取り組んでいます。特に、パート看護師に対しては、祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの長期休暇も本人の希望に応じて自由に取得できる体制を整えており、家庭やプライベートとの両立を支援しています。
介護士(トレーナー)についても、交代制での有給取得を促進しており、業務に支障が出ないよう調整しながら、計画的な休暇取得を推奨しています。上司や管理者からも積極的に声かけを行い、取得しやすい雰囲気づくりに努めています。
また、今後は「年に1回以上の連続休暇(1週間以上)取得」や「付与された有給休暇のうち50%以上の取得」など、具体的な取得目標を設定し、取得状況を定期的に確認する仕組みの導入を検討しています。これにより、職員が安心して休暇を取得できる職場文化の醸成を目指します。
有給休暇の取得は、職員のリフレッシュやモチベーション向上に直結する重要な要素であり、今後も制度面・意識面の両面から継続的な改善を図ってまいります。当事業所では、有給休暇の取得促進を図るため、業務の属人化を防ぎ、業務配分の偏りを解消する取り組みを行っています。「この人しかできない仕事」を作らないという方針のもと、業務内容を共有し、複数担当制を導入。職員同士が互いの業務を理解し、カバーし合える体制を整えることで、安心して休暇を取得できる環境づくりを進めています。
また、職員のライフスタイルや家庭事情に応じた柔軟な勤務体制も整備しています。パート介護職員や看護師に対しては、勤務開始・終了時間や休日を本人の都合に合わせて調整しており、育児・介護・通院などの事情にも配慮した働き方が可能です。祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの長期休暇も、本人の希望に応じて自由に取得できる体制を整えています。
さらに、短時間正規職員制度の導入や、非正規職員から正規職員への転換制度も整備しており、フルタイム勤務が難しい職員でも安定した雇用とキャリア形成が可能です。登用にあたっては、キャリアパス表や人事考課制度を活用し、業務遂行能力・研修受講歴・職場での貢献度などを総合的に判断しています。
子育てや家族の介護と仕事の両立を目指す職員に対しては、休業制度の活用を推奨し、勤務調整や復職支援などを通じて、継続的な就労を支援しています。現時点では事業所内託児施設の整備はありませんが、今後のニーズに応じて検討してまいります。
これらの制度と取り組みにより、職員が安心して働き続けられる環境を整え、サービスの質向上と職場の安定化を両立させています。今後も、職員一人ひとりの事情に寄り添った制度整備を進めてまいります。 - 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
当事業所では、職員の健康維持と働きやすい職場環境の整備を目的に、健康管理対策を積極的に実施しています。パート従業員を含むすべての職員に対して、定期的な健康診断の受診機会を提供しており、雇用形態に関わらず健康状態の把握と早期対応を図っています。
また、心身の健康を支えるため、ストレスチェックの実施も検討しており、職員が安心して相談できる体制づくりを進めています。職場内でのコミュニケーションや業務負担の偏りにも配慮し、メンタルヘルスの維持にも力を入れています。
休憩環境については、狭いながらも専用の休憩室を設置しており、職員が業務の合間にリフレッシュできるスペースを確保しています。今後は、より快適な休憩環境の整備も視野に入れ、職員の声を反映した改善を進めてまいります。
これらの取り組みは、職員の健康と働きがいの両立を支えるものであり、今後も継続的な見直しと充実を図ってまいります。当事業所では、利用者様の安全と職員の安心を確保するため、事故・トラブルへの対応マニュアルを整備し、日常業務におけるリスク管理体制の強化に努めています。マニュアルには、転倒・体調急変・送迎時のトラブル・感染症対応・災害時の行動指針など、幅広い事例に対応できる内容を網羅しており、職員が迅速かつ適切に対応できるよう構成されています。
新規採用時や定期的な社内研修において、マニュアルの内容を共有し、実際の場面を想定したロールプレイやケーススタディを通じて、対応力の向上を図っています。また、事故発生時には、記録・報告・再発防止策の検討までを一連の流れとして実施し、組織としての学びと改善につなげています。
今後も、現場の声や事例を反映しながら、マニュアルの内容を随時見直し、より実効性の高い体制づくりを進めてまいります。 - 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
当事業所では、厚生労働省が示す「生産性向上ガイドライン」に基づき、介護サービスの質の向上と職場環境の改善を目的とした業務改善活動の体制構築に取り組んでいます。具体的には、レコードブック本部との連携のもと、業務の標準化・効率化・ICT活用の推進を図り、現場の負担軽減とサービスの質向上を両立させる取り組みを進めています。
業務改善にあたっては、職員の意見を反映したプロジェクトチームの立ち上げや、定期的なミーティング・情報共有の場の設置を通じて、現場の課題を可視化し、改善策を検討・実施しています。また、外部の研修会や勉強会にも積極的に参加し、他事業所の事例や最新の介護技術・運営手法を学び、実践に活かしています。
改善活動の一環として、AI歩行解析システムの導入や、個別トレーニング提案の仕組みの整備など、科学的根拠に基づいた支援体制の構築にも取り組んでおり、職員の専門性向上と業務の効率化を同時に実現しています。
今後も、ガイドラインに沿った継続的な業務改善を推進し、利用者様・職員双方にとってより良い環境づくりを目指してまいります。当事業所では、サービスの質向上と職員の働きやすさを両立させるため、現場の課題の見える化に取り組んでいます。日々の業務の中で感じる「できないこと」「うまくいかないこと」を積極的に議題として取り上げ、なぜそれが起こるのか、どうすれば改善できるのかを職員同士で話し合う機会を定期的に設けています。
課題の抽出にあたっては、職員の声を尊重し、現場での気づきや困りごとを共有する文化を育てています。抽出された課題は、構造化して整理し、業務の流れや役割分担との関連性を分析することで、根本的な原因の把握と改善策の立案につなげています。
また、業務の効率性や負担感を客観的に把握するため、業務時間の調査や記録の見直しも行っており、業務の偏りや属人化の防止にも取り組んでいます。これらの情報は、業務改善活動や人員配置の見直し、研修内容の検討などにも活用されています。当事業所では、職場環境の整備と業務効率の向上を目的に、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を日常業務の中で実践しています。特に、「ゴミを跨がない!日頃より整理整頓・清掃の徹底」という言葉を社訓として掲げ、職員一人ひとりが意識を持って取り組む文化を育てています。
整理・整頓では、業務に必要な物品の配置や保管方法を見直し、無駄な動きや探し物の時間を削減。清掃・清潔では、共有スペースや備品の衛生管理を徹底し、感染症対策にもつながる環境づくりを行っています。躾の面では、職員同士が互いに声をかけ合い、ルールやマナーを守る風土を醸成しています。
これらの取り組みは、利用者様にとっても安心・安全な空間の提供につながっており、職員の働きやすさとサービスの質向上を両立させる重要な基盤となっています。今後も、5S活動を継続的に推進し、より快適で効率的な職場環境づくりを目指してまいります。当事業所では、業務の標準化と作業負担の軽減を目的に、業務手順書の整備や記録・報告様式の工夫を行っています。これらの多くは、レコードブック本部から提供された資料やフォーマットを活用しており、現場での統一的な運用と情報共有の効率化に寄与しています。
業務手順書は、運動指導・送迎・バイタルチェック・記録作成など、各業務の流れや注意点を明確に示しており、新人職員の教育や業務の引き継ぎにも活用されています。また、記録様式についても、利用状況報告書や個別機能訓練計画書など、必要な情報を簡潔かつ正確に記載できるよう工夫されており、職員の記録業務の負担軽減につながっています。
これらの整備により、業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の品質でサービス提供ができる体制を構築しています。今後も、本部との連携を活かしながら、現場の声を反映した改善を継続し、より効率的で質の高いサービス提供を目指してまいります。当事業所では、業務の効率化と情報共有の円滑化を目的に、介護ソフトの導入を行っています。使用しているソフトは、レコードブック本部から提供されたものであり、記録・情報共有・請求業務における転記作業が不要な設計となっており、職員の事務負担軽減に大きく寄与しています。
また、現場での記録入力や情報確認の利便性向上を図るため、タブレット端末の導入についても現在本部にて試験的に実施中です。今後、正式導入が進めば、リアルタイムでの記録入力や利用者情報の確認が可能となり、業務のスピードと正確性がさらに向上することが期待されます。
これらのICT活用は、職員の働きやすさだけでなく、利用者様へのサービスの質向上にもつながる重要な取り組みであり、今後も本部との連携を図りながら、段階的な導入と活用を進めてまいります。 - やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
当事業所では、職員間の円滑なコミュニケーションを重視し、毎日ミーティングを実施しています。このミーティングでは、利用者様の状態変化や対応方針の共有に加え、職員一人ひとりの「気づき」を大切にし、勤務環境やケア内容の改善につなげる取り組みを行っています。
例えば、「利用者様の表情がいつもと違う」「運動中の動きに変化があった」などの細かな観察を共有することで、早期の対応や個別支援の質向上が図られています。また、業務上の課題や不安についても自由に発言できる雰囲気づくりを心がけており、職員同士が支え合いながら働ける環境を整えています。
ミーティングで出た意見や提案は、必要に応じて業務改善会議や管理者との面談に反映され、現場の声を活かした運営が実現されています。今後も、日々の対話を通じて、職員の主体性とチーム力を高め、より質の高いケアの提供を目指してまいります。当事業所では、介護保険制度の理解と法人理念の浸透を図るため、定期的な研修を実施しています。研修では、「利用者本位のケアとは何か」「尊厳の保持」「自立支援」「生活の質(QOL)の向上」など、介護の根幹となる考え方を職員全員で共有し、日々の支援に活かしています。
また、法人が掲げる理念やケア方針についても、定期的に振り返る機会を設けており、職員が自らの業務と照らし合わせながら理解を深めることができるよう工夫しています。これにより、職員の意識統一とサービスの質の均一化が図られ、利用者様にとって安心・信頼できる支援体制の構築につながっています。
今後も、制度改正や社会的ニーズの変化に対応しながら、継続的な学びの場を提供し、職員の専門性と倫理観の向上を支援してまいります。当事業所では、職員のモチベーション向上とケアの質の向上を目的に、ケアの好事例や利用者様・ご家族からの謝意に関する情報を、毎日のミーティングで共有しています。ミーティングでは、職員が日々の支援の中で得た気づきや、利用者様の前向きな変化、感謝の言葉などを報告し合い、チーム全体で喜びを分かち合う文化を育んでいます。
情報の共有は、連絡帳の返事やご家族からの手紙・電話、送迎時の会話などを通じて得られた内容も含まれており、職員が利用者様やご家族との信頼関係を築く上での大切な要素となっています。こうしたポジティブなフィードバックは、職員のやりがいにつながるだけでなく、ケアの方向性や工夫の参考にもなっています。
また、好事例は必要に応じて記録・蓄積し、研修や業務改善の場でも活用。職員間でのノウハウ共有を促進し、サービスの質の均一化と向上を図っています。今後も、日々の現場から得られる貴重な声を大切にしながら、チームとしての成長と利用者様へのより良い支援を目指してまいります。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
運動指導するスタッフは全員元気で、スポーツクラブ経験者などが揃っています。ひとつひとつの運動を説明していきながら、一緒に体を動かします。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
元気な方が多く、皆さん和気あいあいとトレーニングされています。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
8:00~17:30
賃金体系
220,000~
休暇制度の内容および取得状況
年間120日
ケアの詳細(具体的な接し方等)
利用者の一日の流れ
午前 AM~9:00お出迎え,9:00(30m)検温・血圧測定,9:30(45m)ウォームアップ・集団運動,10:15(30m)ティータイム,10:45(45m)個別運動,11:30(15m)クールダウン,11:45(15m)帰り支度,12:00~お見送り
午後 PM~13:45お出迎え,13:45(30m)検温・血圧測定,14:15(45m)ウォームアップ・集団運動,15:00(30m)ティータイム,15:30(45m)個別運動,16:15(15m)クールダウン,16:30(15m)帰り支度,16:45~お見送り
送迎に関する情報(地区、曜日、個別対応(寝たきり等)の可否等)
介助で移乗ができる。
個別の機能訓練の詳細
自主トレ個別トレーニング作成