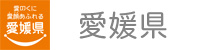2025年10月31日13:21 公表
老人保健施設ミネルワ
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
0/100人 -
最大受け入れ人数100人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
(2025年09月28日時点)
サービスの内容に関する自由記述
・短期入所期間中でも筋力がおちないように努力いたします。
サービスの質の向上に向けた取組
■楽しく働きやすい職場を目指し、テクノロジーの活用で職員に時間の余裕や心の余裕が生まれることにより、働きがいを感じ、利用者への質の高いケアを提供できる。
テクノロジーを活用しながら業務改善に取り組むことが、人材育成・チームケアの質の向上・情報共有の効率化であり、働きがいのある組織づくりが弊社の目指す姿である。
■令和3年度より3年計画でICT機器と見守り機器の導入によりシステムを構築し、弊社の理念・行動指針と現状の課題とのギャップが縮まりつつある。令和6年度、スピード感をプラスしたワンランク上の情報共有システムの『インカム』を導入することにより何事もリアルタイムで施設全体がチームとして動き出し、多職種間で情報共有が促進され、迅速に対応できる。業務改善活動に取り組む中で、①記録・報告様式の工夫にICT導入(令和3年度)②業務の明確化と役割分担に介護ロボット導入(令和4年度)③生産性向上をモデル事業所として実践(令和5年度)④今まで以上のスピード感で情報共有の工夫・コミュニケーション、業務全体の効率化を図ることができ、生産性向上(業務改善)の取り組みを更に加速できる。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
「生産性向上ガイドライン」に基づき、令和3年度には職場環境の整備(5S)・OJTの仕組みづくり・理念、行動指針の徹底を見直し、令和4年度には記録・報告様式の工夫に対応し「ICT機器導入」、令和4年度には業務の明確化と役割分担テクノロジーの活用に対応し「眠りSCAN導入」、令和5年度には手順書作成に対応し「多機能ベッド導入」(愛媛県介護生産性向上推進モデル事業所)(介護労働安定センター愛媛支部による伴走支援を活用)、令和6年度には情報共有の工夫に対応し「インカム導入」(愛媛県介護生産性向上推進モデル事業所)、令和7年度には業務の明確化と役割分担:業務全体の流れを再構築に対応し「介護労働安定センター愛媛支部による伴走支援を活用」している。
令和3年度よりプロジェクトチーム体制(18名:各部署管理者)を構築し、現場担当2名とサブリーダー2名が中心となり、機器導入前の研修・導入後のフォローアップ研修等について月1回の運営会議、月1回の全体会議(全事業所)、月1回施設全職員ミーティングで現状を報告する。
令和5年度「多機能ベッド導入」時より、介護現場主導の生産性向上プロジェクトチームを立ち上げる。施設職員を介護3チーム、看護1チームの4チームで構成し、各チームリーダーとサブリーダー・主任・副主任・看護師長 全15名で構成する。
令和6年度より生産性向上委員会に関する指針を策定し、生産性向上統括リーダーを筆頭に委員会メンバーが6名、サポートメンバー8名の計15名が施設の構成プロジェクトメンバーとし、更に法人内の通所リハビリテーション事業所・デイサービスセンター事業所・グループホーム事業所から生産性向上リーダーを各1名選任し、月1回開催の生産性向上委員会に参加し現状報告をしている。
外部の研修会に関しては、生産性向上に関する介護労働安定センター愛媛支部主催のセミナー(Zoomオンラインセミナー含む)には必ず参加し、セミナー内容(資料等)を全職員へ医療・介護連携サポートサービス「メルタス」を利用し情報共有している。令和5年度から3年間の受講セミナー・受講研修をまとめた「生産性向上専門会議室」には98件のデータ(各企業のセミナーも含む)があり、職員はいつでもどこでも24時間、スマホで閲覧できる。生産性向上取組みのはじめの一歩は、仕事で日頃感じている疑問や、解決したいこと等、職員が気づいたことを自由に記載することから始まる。当施設では「152枚の気づきシート」が生産性向上そして介護DXに導いてくれました。
職員から提出された「152枚の気づきシート」を9項目に分類後、実施体制プロジェクトチームを立ち上げ・役割分担し、問題点・課題を洗い出す。因果関係図より課題の原因分析をし、課題解決策を具体化する。見える化された中で何が今、最優先課題として取組むべきかを検討する。
「152枚の気づきシート」のように見える現場の課題抽出には、心理的安全性の高い環境(職員が何でも言える職場)づくりが必要である。
見える化された課題をどう解決していくか、デジタル化であれば、業務の効率化が目的であり、仕事が楽で簡単になる。特定の業務に絞った取組みが効果的で効率的な業務改善となる。そして生れる時間の有効活用による生産性向上の取組みが、介護サービスの質の向上・人材の定着・確保につながり、業務改善の繰り返しが介護DXに導き、介護DXが更に業務改善をアップデートさせる。
厚生労働省の直接介護と間接業務の24項目を基本に業務を標準化・見える化する。業務時間調査により日中の場合、直接介護が54.1% 間接業務が32.4% 休息・待機・その他が11.9% 余裕時間が1.6%である。夜間の場合、直接介護が48.9% 間接業務が33.2% 休息・待機・その他が12.0% 余裕時間が5.9%である「生産性向上ガイドライン」の一番目の取組みである「職場環境の整備(取組前と取組後)」5S活動を、令和4年末、生産性向上と言われだした頃、どう職員に理解してもらうか問題であった。「整理整頓」とはよく使われてきたが、簡単にきれいにしようぐらいのレベルであった。紹介によりトヨタの5Sという漫画が手に入り、全職員に読んでもらおうと医療・介護連携サポートサービス「メルタス」を利用し、全職員宛に投稿する。
令和6年度4月より施設各委員会、介護3事業所がまず5Sを理解(整理:いる物、いらない物を区別し、いらない物は処分する 整頓:いる物を使いやすく整える 清掃:きれいにし良い環境をつくる 清潔:整理・整頓・清掃が維持できるようにする 躾:マナーや礼儀が身に付き、基本を習得する)し、職場環境の整備に取組んでいる。月1回の生産性向上委員会にて各担当者が現状報告し改善に取組んでいる。令和5年度愛媛県生産性向上推進モデル事業所に採択され、「手順書の作成」に取組む。152枚の気づきシートよりあまりの腰痛者の多さの原因分析をし、既存ベッドの機能的問題により身体的負担が増大していることを確認し、因果関係図より、解決の最優先課題は多機能ベッド導入が共通目標となる。手順書はすべて動画とし、ベッド搬入の手順書・動画操作手順書(9項目)(新人・初心者が理解し易い内容)・動画業務手順書(7項目)としYouTubeに限定公開を検討するが、初めての動画編集ソフトキャンバを使ってのYouTube動画作成のため勉強会を実施等、問題を一つ一つクリアしながら取組んできた。令和4年度に初めてコロナ集団感染を経験した時のベッド移動問題も教訓とし、多機能ベッド導入に向け、導入前には①事故予防 ②在宅復帰促進 ③環境整備・緊急時早く動く ④移動・移乗・介護が楽、4項目の課題をあげ、導入後の職員アンケートにより評価を確認する。結果、①~④の4項目に対し、職員の92%が評価。負担軽減・食事・対応・誤嚥リスクに対し職員の100%が評価を得られる。
令和3年度導入した介護ソフトの一つの機能である医療・介護連携サービス「メルタス」が、各事業所で入力したデータを集約し、法人内全事業所が情報共有するシステムを使用している。利用者情報・報告・連絡・相談・申し送り・会議室カンファレンス・掲示板、回覧板・会議室等、業務中枢機能である。
職員の事務作業の負担が軽減、ストレス軽減により離職率の低下、科学的介護の実現により若手人材の確保、生産性の向上がみられる。事務作業に費やしていた時間をケアにあてることで利用者と向き合いケアの質の向上、定着率アップにもつながり、職場環境の改善やQOL向上やADL維持の向上がみられる。住み慣れた地域で、安心してできる限り自立した生活を営めるよう医療と福祉の連携による質の高いサービス提供が法人理念である。「すべては地域のために」と令和3年度、地域包括ケアシステムに向けて、いち早く法人内で推進できるよう「法人内包括ケアシステムの構築」(法人内を一つの地域と考える)を目指しICT 機器を導入し、全事業所が情報共有する体制を構築する。
介護現場では PDCA サイクルに準じ対応しているものの、紙ベースでの処理には限界があり日々の事務作業に追われ、本来の目的である「利用者と向き合う=サービスの質の向上=利用者の満足度向上」が失われているのも現状であった。
課題解決にあたり時間を確保していくために、現状の紙消費量の月間・年間使用量を調査し、さらに書類作成の月間・年間事務処理時間を看護師・介護福祉士・リハビリ(PT・OT・ST)・管理栄養士・介護支援専門員・支援相談員の職種別に分類し、「現状」と「ICT 機器導入による1年目~3年目の目標」を設定する。
「法人内包括ケアシステム」構築に向け、記録、情報共有、請求業務を一気通貫で行えるようにICT機器を導入し、老人保健施設内での多職種連携と法人内全事業所との情報共有を目指す。
【紙使用量】年間紙使用量66,788枚を3年間で83%55,206枚削減目標とした取組の結果、削減目標の84%56,340枚削減する。
結果内訳:1年目(令和4年度)31,600枚 47%削減 2年目(令和5年度)48,900枚 73%削減 3年目(令和6年度)56,340枚 84%削減
【書類作成業務】年間業務17,803時間を3年間で75%13,200時間削減目標とした取組の結果、削減目標の77%13,630時間削減する。令和4年度見守り機器導入により、介護従事者の介護時間の短縮、介護負担の軽減、利用者・介護従事者の満足度、ストレス軽減により離職率の低下、科学的介護の実現により若手人材の確保、生産性の向上を期待し「眠りSCAN」(100台)を導入する。
介護記録ソフトと連動し、一人ひとりの睡眠状況・生活習慣のデータ化により個別ケアに取り組み、在宅ケアマネジャ-や家族と情報を共有し、日中・夜間に適したケアプランを作成する。
『睡眠・覚醒・起きあがり・離床』と就床している時の『心拍数・呼吸数』の見える化を実施し、利用者一人ひとりの排泄パターン・転倒リスクの高い利用者のパターンの生活リズムを把握して、一人ひとりに合わせた個別ケア(サービス)の提供ができ、利用者の安心・安全と満足度の向上につながる。
通信環境の整備により離れた場所でも見守り機器を設置した複数の利用者の状況把握ができるとともに、ベッドからの起き上がりを感知した際には、職員が離床前に訪室でき、転倒事故等を防ぐことができる。また、利用者の状況の見える化により、睡眠を妨げることなく利用者の状態に応じた居室への見回りが可能で、利用者の満足度に繋がる。連動したスマートフォン・タブレットを使用することにより介護者の無駄な動きが減り、身体的・精神的な介護の軽減につながる。
更に、見守り機器から蓄積される利用者の情報をデータ化し、個々のケア計画に活用することで、介護の質の向上につながる。
通信機器の整備により短縮された時間をケアにあてることで利用者と向き合い、心身ケアの質の向上と満足度向上につなげる。居室で過ごす利用者の状態を見える化することで介護従事者は適切な対応がしやすく、精神的な負担の軽減となる。定着率アップにもつながり、職場環境の改善や利用者のQOL向上やADLが維持される。
【巡回・処理時間のゆとり時間確保】巡回・処理時間一日あたり240分要し、2年間で一日あたり23%一日あたり54分のゆとり時間確保目標とした取組の結果、ゆとり時間確保目標の27%一日あたり64分確保する。
令和6年度ICT機器と連動した眠りSCAN、眠りSCANと連動したスピード感をプラスしたワンランク上の情報共有システム「インカム」を導入する。移動負担、心身への負担が軽減されるだけでなく、効率的なコミュニケーションが図れ、業務改善で生まれた時間をサービスの質を高めるために使用する。何事もリアルタイムで施設全体がチームとして動き出し、多職種間で情報共有が促進され、更に業務効率化が加速する。
インカム導入における課題を7項目に絞り、導入後に検証する。
①医師回診 医師回診(平均60分)に参加していた多職種(医師・看護師・介護士・OT/PT/ST・管理栄養士・ケアマネジャー・相談員)が60分間を各々の業務を優先しながら、リアルタイムで情報共有し、回診に参加できるようになる。
②入所多職種カンファレンス 開始までの時間を5分削減することにより、月4時間のゆとり時間が生まれ、またリアルタイムで意見交換もできる。
③入浴時 一日一人あたり処置対応までの2分間の削減により、月5時間のゆとり時間が生まれ、利用者を待たせることなく迅速な対応ができる。
④事故予防 眠りSCANとインカムの連動により、ヒアリハットは増加するが、職員同士の迅速な対応により、事故予防の意識が高まる。
⑤夜間の看護師と介護士連携 緊急時にワンプッシュで連携できる安心感は高く、情報共有で迅速な救急対応が可能となる。
⑥看護と介護の申し送り 多職種が業務を優先しながら情報の共有ができ、医療面で看護の申し送りを聞くことで事前に利用者の状態を把握できる。
⑦家族様面会 ご家族様の面会対応がスムーズになり、ハプニングにも臨機応変に対応し、リアルタイムで面会状況を把握できるようになる。令和4年度に業務の明確化と役割分担(2)テクノロジーの活用で眠りSCANを導入し、介護助手としても1名採用している。令和7年度再度業務の見直しとして、業務の明確化と役割分担(1)業務全体の流れを再構築について、5月~12月の期間、介護労働安定センター愛媛支部の伴走支援にて生産性向上プロジェクト7名と生産性向上プロジェクトサポートメンバー8名の合計15名が介護部門と看護部門に分かれ直接介護と間接業務の細分化に取組でいる。
令和6年12月勤務体制別に業務時間調査を実施する。生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得申請手続きに提出した日中と夜間の類型別割合である。
日中の場合、直接介護が54.1% 間接業務が32.4% 休息・待機・その他が11.9% 余裕時間が1.6%である。
夜間の場合、直接介護が48.9% 間接業務が33.2% 休息・待機・その他が12.0% 余裕時間が5.9%である。
厚生労働省の直接介護と間接業務の24項目を基本に業務を標準化・見える化する。業務の明確化・役割分担により間接業務を効率化・削減し、間接業務12項目の一部を介護助手が担う。介護福祉士が直接介護に専念できる職場環境を整えることが、介護サービスの質の向上に効果的であり、更に生産性向上を加速させる。当施設の業務を明確化する上で、直接介護・間接業務そしてグレーな部分が見られるため、より細分化し、現場の課題を見える化により業務内容・役割分担がはっきりし、どの業務にどれくらい時間が掛かっているか確認することにより、間接業務を減らすことができる。どの業務を改善する必要があるか、改善した業務がどれくらいあるか、現場の業務量を分析することにより直接介護の時間を増やすことができる。
間接業務内容の細分化により、介護助手が担える業務を時間帯別に表示し、シニアの方は勿論であるが、勤務できる時間制限のある主婦や特に学生さんに介護事業を理解してもらう上でも主にアプローチしていきたい。年内には時間帯別に介護助手としての必要人数が決定するので、職員網・学校・ハローワーク・愛媛県社会福祉協議会等を通じ、介護助手における間接業務の体制構築を進めていく。情報の共有を目的として、介護現場を支える①生産性向上委員会 ②ノーリフティングケア委員会 ③感染症対策委員会 ④事故・身体拘束・虐待防止委員会 ⑤レクレーション委員会 ⑥入浴委員会 ⑦褥瘡・排泄委員会 ⑧NST・口腔ケア委員会の指針・計画・研修・議事録を共有し、年度末には各委員会が取組んだ生産性向上についてパワーポイントでの発表を実施する。
令和5年度から3年間のセミナー・研修をまとめた①生産性向上専門会議室98件 ②ノーリフティングケア専門会議室17件 ③高齢者虐待防止専門会議室15件 ④感染症対策専門会議室23件 ⑤BCP専門会議室12件 ⑥眠りSCAN専門会議室40件の情報をメルタス(医療・介護連携サポートサービス)に集約し、職員が最新の情報を共有することで協働化し、チームケアで職場環境の改善に取組んでいる。
併設されているサービス
通所リハビリテーション、デイサービス、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所が併設されており、協力病院も近くにあり、在宅サービスにスムーズにつなげます。
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
・個人の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってスタッフ全員が心をこめて充実したサービスを行います。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
・できるだけ家庭的な雰囲気の中で生活を送り、短い期間でも快適に過ごしていただける環境づくりにつとめます。