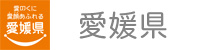2025年10月31日13:23 公表
済生会介護支援センター姫原
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
0/0人 -
最大受け入れ人数0人中、現在の受け入れ可能人数0人です。
(2025年09月21日時点)
サービスの内容に関する自由記述
-
サービスの質の向上に向けた取組
-
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
業務改善活動の体制構築について
当施設では、厚生労働省が示す「介護現場における生産性向上に資するガイドライン」に基づき、介護サービスの質の維持・向上と職員の業務負担軽減を両立及び生産性向上の取組みを施設全体で共有し、継続的に実行していく体制を作る為、業務改善委員会・ICT委員会を立ち上げ 構成メンバーは各部署から選出しました。
1.委員会の設置
委員会は施設長をはじめ、各部門(介護、看護、事務等)の代表職員によって構成され、定期的な会議を通じて課題の抽出、改善策の検討、効果検証などを行います。
また、現場職員の意見を積極的に吸い上げ、改善活動に反映させるため、現場との双方向のコミュニケーションを重視した運営を行っています。発足当初は、月1回開催現在は、隔月開催
2.外部専門家の活用
介護労働安定センターからICTコンサルタントを招き、定期的にICT委員会を開催。助言をいただき、得られた知見やノウハウは施設内にフィードバックされ、業務改善委員会やICT委員会の活動に反映される仕組みを整えて、生産性向上を推進している。
このような体制を構築することで、業務の「見える化」や「標準化」を図り、効率的かつ質の高い介護サービスの提供に努めています。今後も継続的な改善活動を通じて、生産性の向上と働きやすい職場環境の両立を目指します。Ⅱ 業務の見える化と改善活動の流れ
● ステップ1:現状把握
• 業務手順の見直し
• 業務内容を分類(ムラ、ムダなどが無いか)
• これにより、業務負担の偏りや非効率な作業の実態が可視化され、改善のための具体的な手がかりを得る
● ステップ2:課題の抽出とテーマ設定
• 例:情報共有の非効率さ、記録業務の手間、申し送りの属人化など
● ステップ3:改善の実行と評価
• 小さな改善(Kaizen)から開始
• ICTツールの導入(記録ソフト、インカム、業務支援アプリ等)
● ステップ4:定着化・水平展開
• 成果をマニュアル化・標準化
• 他の部署・施設にも展開「整理」については、必要な物と不要な物を区別し、不要な物を排除することを徹底しており介護施設では、物品や書類が多岐にわたるため、そうすることにより作業効率の向上と誤使用の防止に努めている。
「整頓」については、必要な物をすぐに使えるように配置・表示(テプラ等で)し介護用具や医療備品を定位置に配置し、誰でも一目で場所が分かるようにすることで、時間のロスを防ぎ、緊急時にも迅速な対応ができるようにしている。
「清掃」は、職場を常に清潔に保つことにより、不具合の早期発見や感染症の予防に寄与し、特に高齢者を対象とする介護施設では、衛生管理の徹底が利用者の健康を守るうえで不可欠であります。
「清潔」は、整理・整頓・清掃の状態を維持するためであり、また職場全体に衛生的で快適な環境を保つことが、職員や利用者にとって安心感のある空間がつくられる。
「躾」は、5Sを継続するためのルールやマナーを守る習慣づけに無くてはならないものであり、組織全体で5Sの意識の共有化、一人ひとりが責任を持って行動することの裏付けとなり、長期的な職場環境の改善につながる。
以上のように、5S活動を継続的に実践することで、介護施設内の安全性・効率性・快適性が向上し、職員の働きやすさだけでなく、利用者にとっても安心できる環境づくりが実現され、施設全体の5Sの意識を高め、質の高い介護サービスの提供に努めていくことができる。業務手順書の作成および整備により、各業務の進行手順や注意点を明文化することで、業務の標準化を図り、新任職員や非常勤職員にとっては、業務内容を理解しやすくなり、業務の質を安定的に保つことに努めている。また、手順の可視化により業務の見直しや改善点の発見にもつながり、職場全体の業務効率化につながる。さらに、ICT機器や介護記録ソフトの活用によって、記録・報告業務のさらなる効率化も可能となり、これにより、現場職員は本来業務である利用者へのケアにより多くの時間を割くことができ、職員の負担軽減および働きやすい職場環境の実現にもつながっている。
介護現場においては、利用者へのケア提供に加えて、記録業務や情報共有、請求関連業務など多岐にわたる業務が日常的に発生している中で、業務の効率化と職員の作業負担軽減を図るうえで、介護ソフトおよび情報端末(タブレット端末等)の導入を令和5年5月より介護システム入れ替えと同時に実施しました。特に、記録・情報共有・請求業務への転記が不要な一体型の介護ソフトを導入することで、入力した情報がそのまま各機能と連携され、二重入力や転記ミスを防ぐことが可能になります。これにより、記録業務に要する時間を大幅に短縮できるほか、職員の精神的・身体的負担の軽減にもつながった。また、タブレット端末などの情報端末を現場に配備することで、ケアの合間にその場でリアルタイムに記録を行うことが可能となり、記録の正確性や即時性が向上した。記録内容は即時に共有されるため、申し送りやカンファレンスにおいても情報の伝達がスムーズに行えるようになり、これにより、利用者の状態変化に迅速に対応でき、ケアの質の向上しつつある。
Ⅵ眠りスキャンおよびインカム導入による効果について
当施設においては、令和7年度介護ロボット補助金申請に眠りスキャン・インカム導入を申請中であり、夜間の見守り支援および職員間の連携強化を目的として、「眠りスキャン」および「インカム」を導入予定としております。これらの機器の活用により、以下のような具体的な効果を期待しています。
1. 職員の身体的・精神的負担の軽減
眠りスキャンによって利用者の呼吸・心拍・体動の状態を常時モニタリングできるようになり、夜間の巡視回数が削減。これにより、職員の身体的な負担(夜間の移動・起床回数の多さ)や精神的緊張(急変への不安)が軽減され、夜勤時の業務負担の軽減につながる。
2. 利用者の安全性と快適性の向上
眠りスキャンの導入により、異常なバイタル変化や離床の兆候をリアルタイムで把握できるようになり、迅速な対応が可能となる。これにより、転倒や体調悪化などのリスクを早期に察知・予防でき、利用者の安全性が向上する。また、必要以上に訪室する機会が減ることで、夜間の安眠環境も保たれ、利用者の快適性・QOL向上にも寄与する。
3. 職員間の連携強化と業務効率の向上
インカムの導入により、職員間の情報共有がリアルタイムかつハンズフリーで行えるようになり、緊急時の対応や介助要請の伝達が迅速化。これにより、複数名での対応が必要な場面でも連携がスムーズになり、業務の効率化とチームワークの強化が実現。
4. 記録業務の簡素化と正確性の向上
眠りスキャンの計測データは自動で記録・蓄積されるため、従来の手書きによるバイタル記録や巡視記録の一部が省力化。これにより記録作業の負担が軽減され、かつ客観的で正確なデータが記録されるため、ケアの質の向上や職員の事務負担軽減に寄与する。
5. 人材定着率の向上への寄与
これらのICT機器の導入により、職場の働きやすさや安心感が向上し、特に夜勤業務に対する不安やストレスの軽減が図られる。結果として、職員の離職防止・人材定着の促進にも一定の効果が得られる。
以上のように、「眠りスキャン」および「インカム」の導入後は、介護現場の安全性・効率性・快適性を高める重要な取り組みとなり、継続的な運用と活用方法の見直しを通じて、より良い介護環境の実現を可能とする。令和7年4月より介護職員が本来の業務である利用者へのケアに十分な時間と労力を注ぐことができるよう、施設内における業務内容の明確化および適切な役割分担を推進している。特に、食事の片付けなどの間接業務については、業務員、事務所からのサポ-ト体制により介護職員への負担軽減に努めている。その効果により、少しでも早く利用者への寄り添う時間が確保出来ている。現在、効率的な体制の構築中である。間接業務を介護職員がすべて担うのではなく、業務員、他職種を活用することで、ケア業務との分担を明確にし、職員の負担軽減を図っている。より専門性の高いケアの提供に集中できる環境づくりを進めている。
併せて、各職種の業務範囲を整理したうえで、シフト体制の見直しや業務手順の再構築を行い、業務負担の偏りや非効率を解消し、これにより、職員一人ひとりが役割を明確に理解し、チーム全体で協働できる体制を整備したい。
今後も継続的な業務改善を通じて、介護の質の向上と職員の働きやすい環境の両立に努めていきたい。令和6年度より、各種委員会(細かく分けると21委員会)管理部門・内部外部との交流関係・安全対策・栄養管理・ICT業務改善・教育人材育成等の委員会を発足し介護現場における業務効率の向上および職員の働きやすい職場環境の実現に向けて、施設全体が連携・協働しながら業務の合理化を目指している。
具体的には、各種委員会ごとの指針・計画策定を行うことで、意思決定の効率化を図ります。
さらに、法人契約による福利厚生システムに加入し、福利厚生を充実させ、職員のリフレッシュの一役を担っている。
このような取組を通じて、介護サービスの質を維持・向上させながら、限られた人材資源を有効に活用し、持続可能な運営体制の構築を図っている。
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
-
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
-