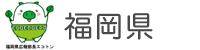2025年11月05日09:34 公表
小規模多機能施設 「ひより」
| 介護サービスの種類 |
小規模多機能型居宅介護
|
|---|---|
| 所在地 |
〒820-0013 福岡県飯塚市上三緒1番地11
|
| 連絡先 |
Tel:0948-21-7400/Fax:0948-21-7403
|
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
4/29人 -
最大受け入れ人数29人中、現在の受け入れ可能人数4人です。
(2025年09月25日時点)
サービスの内容に関する自由記述
(1)健康維持・管理
毎朝の血圧・脈拍・体温、必要に応じて酸素飽和濃度を測定しており、状態に応じて医療機関やかかりつけ医に相談・受診しています。家族から状況を伺ったり、定期的に協力医療機関と連携を取り合いながら健康管理を行っています。
(2)入浴
週3回入浴を行っています。入浴日に入浴出来ない時などでは、個別に対応しています。
(3)食事
季節に合わせた旬の食材を使用し、利用者様一人一人の嚥下や咀嚼能力に合わせた食事形態で提供しています。
(4)レクリエーション
毎日体操や個別レクレーションを実施し、体力・身体機能の維持・向上を図っています。気候の良い時には屋外に散歩に行きます。
コロナ禍前は毎日のレクリエーションの他にも、季節に合わせて外出レクリエーションを実施していました。利用者様の馴染みのある場所、行ってみたい場所等を聞き出し、それを他の利用者様と共有することで、親近感や連帯感が生まれ、その後においての生活意欲の向上にもつながっています。現在は、外出する機会は減っていますが、感染対策を行いながら、外出支援を検討しています。
サービスの質の向上に向けた取組
小規模多機能施設「ひより」は、グループホームを併設している施設です。この併設のメリットを活かすために「ひより」は認知症ケアに特に力を入れています。様々な資格を持った職員が、その人に合ったきめ細やかなケアを心がけて、「家庭的で尊厳ある生活」「楽しみと安心な生活」「地域社会とつながりある生活」をサポートさせていただいています。
令和4年10月より、地域高齢者の方の生活支援サービス「ケアモビひより」を開始しました。高齢者が住み慣れた地域での暮らしを継続していく為には日常生活の中での「困った」を解消する生活支援サービスが必要になってくると考えています。加えて、高齢者の社会参加の機会を拡大していく事で、地域が元気になっていく事も期待されます。ケアモビでは移動(モビリティ)をお世話(ケア)することで高齢者の「困った」をサポートし、持続可能な介護システムの維持に貢献していきたいと考えています。
ケアモビの活動を始め、地域の方々に「ひより」を知っていただける機会が増えました。近隣の方や市内の方にケアモビを利用していただき、在宅で生活されている方々の支援が出来る事を嬉しく思います。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
-
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
-
-
-
-
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
-
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
-
-
-
- 両立支援・多様な働き方の推進
-
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
-
-
-
- 腰痛を含む心身の健康管理
-
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
-
-
-
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
-
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
-
-
-
-
-
障害者就労移行支援サービスへ、清掃・リネン交換・洗濯等を依頼している。
-
- やりがい・働きがいの醸成
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
-
2か月に一度、地域自治会のいきいきサロンへ参加しており、地域住民の方との交流の場となっている。
-
-
併設されているサービス
当事業所はグループホーム(2ユニット)と併設しています。併設と言う事もあり、利用者間の交流を持つ機会が多く、行事等もグループホームの方と一緒に行っています。職員の配置は違っても馴染みの関係が出来ており、小規模多機能の利用者様がグループホーム入所となられた場合でも、環境の変化が少なくサービスの移行が可能です。実際に、小規模多機能からグループホームへ移行された利用者様が複数名おられますが、周りの環境変化が少なく済んだ事もあり、認知症の進行においても最小限となり穏やかに生活する事が出来ています。
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
職員は20歳代~70歳代までおり、幅広く勤務しており、年代における経験や知識を共有しあうことで、それぞれ高めあえるよう協力することができています。「働きやすい職場づくり」に力をいれ、職員教育や定期的な面談などを実施し、ストレスを溜め込まないよう配慮し、利用者さんへ笑顔で接することができるよう支援しています。また働きやすい職場作りの一環として、自社にて妊娠・出産・育児休暇を経て仕事復帰した職員や、育児中の職員がいます。定年は60歳より65歳へと引き上げました。このような職員を支える事が出来るよう体制を作り、他の世代の職員の理解も得られるようになり、困った時に協力し合える体制が整ってきたと考えています。
有資格者への処遇にも力を入れるようになり、資格や経験・能力に応じた人員配置を行う事で、資格に対する意識も高まり、向上心を持って仕事が出来るようになってきました。認知症ケアに力を入れていることもあり、認知症ケア専門士の資格取得者を増やすよう努力しています。研修においても、職員が自ら率先して参加しており、それらを仕事で活かす事が出来るような研修参加となっています。
職員同士が良い人間関係でいることで、情報の伝達や共有・連携が取れ、利用者様に対しても良い介護が出来ると考えています。ICTの利用により、情報共有がスムーズになっています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
お一人お一人が、役割を持って生活されています。食事の準備・片付け・洗濯・他の方のお手伝い等、今まで培われて来た経験や知識が発揮できるように役割や助言・付き添い等を支援しています。
「自分が誰かの役に立っている」と言う気持ちを持つことで、生活意欲も高まり、張り合いを持って生活出来ています。これまで経験のなかった事でも「やってみたい」という意欲を引き出し、挑戦して身につける事が出来、それが笑顔や生きがいにもつながっています。
趣味活動の支援も行っており、塗り絵や折り紙等の作品を施設内で展示し、人に観てもらう事で、より一層の意欲向上となっているようです。
毎日のレクリエーションにおいても、家族の前では出ない様な表情を見せられるかたもおられます。カラオケ機を利用した認知症進行予防の為のレクリエーションプログラムにも積極的に参加されています。また午後からは、個別に歩行訓練等を行うことで、残存機能を維持できるように援助しています。そのことで、毎日楽しくいきいきと生活しています。
ユマニチュードの理念を取り入れており、利用者さんが出来る事を奪わないよう、身体機能の維持・向上を目標とし寄り添った介護を行っています。
ケアの詳細(具体的な接し方等)
入浴形態(一般浴、機械浴)
一般浴(個浴)