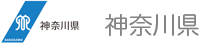2023年10月26日14:02 公表
やました通所リハビリテーション
サービスの内容に関する写真
-

集団体操
集団の効果を活用し、意欲を引き出します。
年3種類の運動をローテーションして行っています。1日90分程度の体操を休憩を挟みながら行います。運動をメンイに意欲的に取り組まれる方が多いようです。 -

個別運動療法
個々に合わせた運動療法を実施しています。生活の質の改善を図っていきます。写真は、体幹強化練習になります。 -

マシントレーニング
レッグプレス:下肢筋力の改善を図っていきます。立ち座りや歩行の安定を目的にしています。他に、レッグエクステンション、ローイングのマシンがあります。
受け入れ可能人数
-
受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
5/20人 -
最大受け入れ人数20人中、現在の受け入れ可能人数5人です。
(2023年08月25日時点)
サービスの内容に関する自由記述
高齢者や障がいをお持ちの方がお元気で自立した生活をされていくためには運動機能の維持向上は大変重要な要素のひとつです。そこで私どもの「やました通所リハビリテーション」では医療と介護が密接に連携して介護保険のリハビリテーションを提供しております。内容をご紹介しますと、集団体操、理学療法士・作業療法士による個別運動療法(要介護の方のみ対象)、トレーニングマシンによる筋力増強訓練をそれぞれの方のニーズや疾患、お身体の状態に合わせて週に1~2回、1回3~4時間のプログラムか1回1時間~2時間の短時間のプログラムで実施致します。また月に2週行う「リハビリ教室」は、認知機能活性化のためのプログラムを提供しています。認知機能活性化により、運動機能へのフィードバックを図っています。個別運動療法では、ご自分でできる運動療法の確認、その他日常生活や介護に必要な様々なアドバイスも行っています。その結果、利用者の方々の1年後の運動機能は十分維持向上され、特に介護予防通所リハビリテーションについてはバランス能力と歩行能力に有意な改善が認められています。また、2012年5月より「やましたリハ通信」を年間3回発行し、当通所リハビリテーションの情報を各居宅支援事業所のケアマネージャーや利用者の方へ発信しております。医療保険から引き続いてリハビリテーションの継続を希望される方は、是非ご利用をお勧め致します。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
サービスの質の向上に向けた取組
当通所リハビリテーションでは平成21年5月よりリハビリテーションに特化した施設として、3時間以上4時間未満の単位でサービスを提供してまいりました。特に高齢者の方の日常生活動作の改善と転倒予防を目的とした個々の生活に主眼をおいたリハビリテーションを実施しておりますが、利用される方の年齢や疾患、運動機能等は様々でリハビリテーションに対する考え方も多様化しています。例えば3時間は長くてできない、個別療法だけやりたい、他サービス利用にリハを併用したいといった要望が寄せられていました。そこで、平成29年9月より、医療保険の運動器リハビリテーションからスムーズな移行を行うためにリハビリだけに集中して取り組みたい方を対象とした実施時間の短い「1時間以上2時間未満の短時間通所リハビリテーション」も開始致しました。そして平成30年の医療・介護の同時改定では、要介護者の医療保険リハビリテーションから介護保険リハビリテーションへの移行が今まで以上に緊密に求められています。今後も利用者の方それぞれの生活に眼を向けたリハビリテーションを提供してまいりますのでどうぞ宜しくお願い致します。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
-
併設されているサービス
-
保険外の利用料等に関する自由記述
-
従業員の情報
-
従業員の男女比
-
従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
看護師、理学療法士等の医療系スタッフと介護福祉士、リハビリ助手の介護スタッフが連携して業務を行っています。月に2週行う「リハビリ教室」は、認知機能活性化のためのプログラムを提供しています。
利用者の情報
-
利用者の男女比
-
利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
利用者の方々は、それぞれご自分の疾患やお身体の状態に応じて、運動機能の維持・向上及び日常生活動作の改善を目的に、リハビリテーションに対しとても意欲的に取り組まれています。